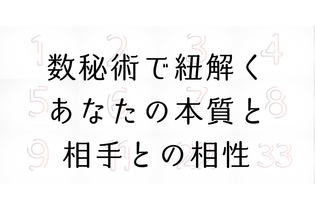失われた青春を同窓会ラブで取り戻せ【恋愛難民、王子様を探す】第1話
男日照り暦5年のOL・鎌谷素子は男慣れしておらず、恋愛にも消極的。そんな素子に対して攻撃的な態度を崩さない天敵・高山聡子が、ある日突拍子もない提案をぶつけてくる。恋愛難民と化した女は、無事運命の王子様を見つけて失われた青春を取り戻せるのか? 連載「恋愛難民、王子様を探す」#1をお届けします。

雑音とアルコールに溢れた大衆居酒屋。はす向かいに座っていた長嶋君がぐっと身を乗り出し、少しトーンを落とした声で囁いた。
「鎌谷さんさ、こういうの苦手でしょ」
驚いて顔を向けると、ぱちんと火花が散りそうなくらい視線がかち合った。瞬間、梅酒のロックがぐるんぐるんと体内を駆け巡る。絶句して頬を紅潮させる私を見て、長嶋君は口元を片方だけくいと上げ、涼しげな笑いを浮かべた。
■コンプレックスは終わらない

高校の同窓会に初めて顔を出したら、青春ドラマの主人公もかくやと思われる華々しいメンバーばかりがひしめき合っていて、私は開始1分で白旗を上げた。しかし、すぐに帰るわけにもいかず、むにゃむにゃしているうちに山手線ゲームが始まっていた。
山手線ゲームとは、リズムに合わせて山手線の駅名を順番に言っていき、言えなかった者が一気飲みをするという単純明快なゲームだが、私は山手線の駅名にも詳しくなければ一気飲みも苦手だ。そして、こういう場も苦手だ。連なる苦手意識が漏れ出してしまった結果、長嶋君に「苦手でしょ」と囁かれるに至る。
それにしても、バスケ部のエースとして一等星の如き輝きを放っていたクラスの人気者・長嶋君が、私の小さな躊躇を捉えたことに驚いた。私のことなんて視界にも入ってないだろうと思っていたから。
「鎌谷さん酔ってるみたいだから、他のメンバーで続きやるべ」
「おお、大丈夫?」
「無理しないで~」
さすがスクールカースト最上位に君臨していただけあって、みんな屈託のない笑顔を向けてくれる。根明な人間は嫌味がないのだ。直視できないほどの眩しさに目をやられ、私は俯きがちに「ごめんね、ありがとう」とつぶやいた。
卒業してからいくらか外見に磨きをかけ、多少垢抜けた印象を作り上げたはずだが、昔のコミュニティに放り込まれるとそんな付け焼刃は通用しない。見栄と過剰な自意識で作られた一張羅は溶けてなくなった。身ぐるみはがされた田舎者の気分だ。地元は同じはずなのに!
■午前零時の罵り合い

飲み会が終わると、そそくさとその場を去った。中央線に揺られ、三鷹のシェアハウスにたどり着いたのは午前零時。一刻も早く寝床に入りたいと願っていたのに、共用リビング前で不躾な声に呼び止められる。
「ちょっとそこの陰気な人」
「私のことじゃあるまいな……って、それ、私の!」
ソファの上でふんぞり返っている高山聡子の手には、先日、自由が丘で買ってきた“幻のシュークリーム”の袋が握られている。握られているということは、中身はもうないということだ。聡子はどこ吹く風といった顔で、あっけらかんとしている。
「これ、あんたのだったの。おいしかったよ」
「名前を書いておいたのに信じられない。窃盗罪だ」
「あ、ほんとだ。気づかなかったわ」
「この泥棒猫!」
「あんたに言われると心外ねえ。ところで、同窓会はどうだったの? さぞかし華やかな一軍メンバーだったんだろうけど」
私が目を丸くすると、「やっぱり」と聡子は鼻を鳴らした。
「ってことは、長嶋もいたわけね。行かなくて正解だった」
「そういえば……聡子、高2のときに長嶋君に告白してたね」
「ふん。私の素晴らしさがわからない男なんてこちらから願い下げよ。末代まで祟ってやる」
高校男児にして聡子の腐敗し切った性根を見抜くとは、さすが長嶋君だ。心の中で拍手を送る。
聡子は気の強い美人で、中学時代から男をとっかえひっかえしている。あまりに回転が早いので、高校入学前に聡子の恋愛遍歴の把握は諦めた。私と聡子は小学校からの腐れ縁だが、見た目から性格まですべてが対照的で、共通点はひとつもない。それなのになぜいちいち私につっかかってくるのか謎だ。
気付くと、聡子が蛇女のようなねっとりとした眼差しでこちらを凝視している。ぎょっとして身じろぐと、にやりと笑って舌なめずりをした。
「あんた、長嶋に惚れたな」
「な……、そんなわけ」
「少なくとも気になってるはず」
「いやいや、一言二言しゃべっただけだし」
「ふーん。それだけで女心を掌握するとは、つくづく食えない男よ」
私からすると、聡子も十分に食えない女である。私の一瞬の表情で芽吹くか芽吹かないか程度の恋心を見抜くとは。
「あんた、長嶋の連絡先は聞いてきたんでしょうね」
「いやいやいや、そんなわけないでしょうが」
「あんた、ばかぁ?」
聞き馴染みのあるセリフをしかめっ面で吐き捨てられ、より一層腹が立ってきた。なんでシュークリーム泥棒にここまで言われなきゃいけないんだ。抗議の言葉をぶつけようと息を吸った瞬間、聡子が「よし」と言って立ち上がった。爛々と光る眼は、まるで女豹だ。
「長嶋と付き合わせてあげよう」
「……はい?」
「私が指示を出すから、あんたは忠実に従いなさい」
「はあ?」
「男日照りを何年続ける気? あんたは長嶋が気になってる。私は長嶋に一泡吹かせたい。利害が一致してるんだから、協力しなさいよ」
あとはまた今度ね、と言い残して、聡子は自室に消えていった。天上天下唯我独尊といわんばかりの一方的な態度に苛立ちが募るばかりだったが、聡子の口調からはただならぬ自信が匂い立ち、妙な説得力を漂わせていた。
■さよなら青春シンドローム

聡子の狡猾さを駆使すれば、ともすると、長嶋君と赤面必至の睦言を交わし合い、あんなことやこんなことを楽しむ薔薇色の生活が手に入るのではなかろうか。そんな甘い考えが頭をよぎる。
学生時代に未熟な乙女心をこねくり回してこじらせ尽くした私だが、ついに失われた青春を取り戻す時がやってきたのかもしれない。そう思うと不思議と力が湧いてきた。
憎き聡子を利用して、奴よりも先に幸福の頂に立つのだ――。
自分を鼓舞するため、鼻息荒く冷蔵庫を開ける。こんなこともあろうかと“幻のシュークリーム”をもうひとつ買っていたのだ。勢いよく取り出すと、なんということだろうか、コンビニの100円シュークリームにすり替わっていた。ご丁寧にもマジックで「残念無念」と殴り書きされている。
――許すまじ、聡子。骨の髄まで利用してやる。
噛りついた100円シュークリームは口の中でとろりと甘さを滴らせ、たちまち喉の奥へ消えていった。
(第2話につづく)