【それでもわたしは食事する】第1話|傷だらけの40代と舌バカなシェフ
お疲れ気味の43歳女性にふと訪れた、偶然の出会い。魅力的な容貌で、耳馴染みの良い声を備えたその人は、魔法のようにおいしい料理を生み出すシェフなのだが……。五味零さんの連載「それでもわたしは食事する」第1話です。

■夢のようなイケメンが、悪夢のような料理を食べていた
東京にはいろいろな人がいる。いろいろな人のなかには変な人もいるけれど、彼らに遭遇する確率は意外と低かったりする。それなのに、わたしのそばにはいま、変な若者がいる。
10代や20代の若者のやることを理解できる40代はなかなかいない、という意見は脇に置いておくとして。その若者は、彼の同世代が見てもギョッとしそうな行動を取っていた。
元旦の早朝のことだ。徹夜明けでボロボロの姿をさらけだして、わたしは思わず呟いた。
ここは新宿駅付近にある牛丼チェーン店。店内にはわたしのほか、窓際の席にひとりの若者が背を向けて座っているだけだった。寝不足の頭はもうほとんど機能していなかったんだと思う。ほかにいくらでも席は空いているのに、なぜかその若者と同じ列に並んで座ってしまった。そのせいで、特盛りの牛丼に“持参したジャム”を乗っけて食べる、奇妙な男が視界に入ってしまった。
服装も髪型も今風で、顔もなかなかのイケメンだ。だけど食べ合わせを見る限り、なんというか、失礼を承知でいうなら……舌がバカすぎる!
最初は「正月の朝早くから牛丼なんてオール明けかしら、若いなあ」と思いながら、チラ見しただけだった。そのまま何事もなければ、すぐに目線を手元に戻し、ホロホロチキン牛丼を口にかき込むはずだった。
それなのに、席をひとつ挟んだ隣には、予想外の光景が広がっていた。20代前半とも後半ともとれる男は、例のジャム丼を美味しそうに食べている。さらにそこへ、これまた持参品であるカップのアイスクリームを丸ごと放り込んだ。ちょっと待て、今、上着のポケットからアイスが出てこなかったか?
驚愕したわたしの手から箸が滑り落ちる。同時に、今ごろ口の中におさまっていたであろうキチンも、どんぶりに詰め込まれたご飯の上に落下した。目が離せなかった。イケメンだからではない。先ほども申したように、舌がバカすぎるからだ。
わたしは今年で43になる。それなりに食べ物の味をインプットしてきたつもりだし、わりと許容範囲も広いほうだと思う。そんなわたしでも、許せたのはジャムまでで、さすがにアイスクリーム丼は理解しがたかった。
わたしは静かに正面に向き直る。窓の外を身を縮こめて歩いている人たちを眺め、暖かい室内にいる自分がいかに幸せかを噛み締めた。同時に、舌バカな若者の存在を頭から削除する。都合の悪いこと、理解できないことなんかは、こうしてやり過ごすのが一番いいのだ。
■43歳、不幸真っ盛り。傷跡は増えるばかり
どうして最悪な出来事というやつはまとまってやって来るのだろう。年末のすべてを捧げた案件は、どこかの部署のミスで白紙に戻った。そしてその原因を、上司はわたしの力不足だと指摘してきた。いっきに10円ハゲが6つくらいできそうなくらいにはストレスだった。
それから、婚約者が逃亡した。40代、結婚間近でまさかの失恋。悲惨すぎる。傷は消えても痕は残る、と誰かが言っていた。振り返れば、わたしはいつも傷だらけだった。新たな傷が増えるたび、これまでに蓄積してきた傷跡がくっきりと浮かび上がってくるような気がした。
静かな失恋だった。その人の最後の言葉は「冷蔵庫の奥になんかこびり付いてるよ」で、なんの前触れもなくわたしの前からいなくなった。てか、なんかってなんだよ。悲しむ間もなく多忙な日々を過ごしているわたしは、その言葉から1週間経ってもまだ、何がこびりついているのか確める余裕がなかった。せめて、こびり付いているものの正体くらいは教えて欲しかった。
あとは、歯の詰め物が抜けたことと、愛用していたハイヒールのヒールが折れてローヒールになったことと、リビングのど真ん中に転がっていたゴキブリの死骸の隣で飼い猫が冷たくなっていたことなんかがあった。
猫に関しては、交際5年の彼よりも付き合いが長かった。マンションのベランダによく遊びに来てた子で、何度か食べ物をおすそ分けしているうちに、うちの子になった。猫には帰る場所が複数あると聞くので、もしかすると他にも寝床があったかもしれないけれど。わたしは、わずかに口を開いたまま眠るように亡くなっている猫を抱きしめ、安易に決めてしまった名前を呼びながら泣いた。もっと意味のある名前を付けてあげればよかったと、今さら後悔した。これらはすべて、年が明けて1週間のうちの出来事だ。今なら不幸自慢で負ける気がしない。
■舌バカの正体は天才シェフ?
さすがに悪いものはも出し切ったようで、婚約者と出かけるつもりで入れた有給の日は珍しく何も起こらなかった。。休日を持て余したわたしは家の近くのカフェにいた。婚約指輪をはめたままの薬指を見つめていた。するとその延長線上で、真新しい建物が目に入る。
くすみひとつない白壁に、木材をそのまま使ったような木目調のドアがぽつんと付いている。複雑な文様を描くアイアンフェンスが、ケーキに巻かれたフィルムのように建物を囲い、おしゃれを極めた外観だった。こういった類のものは、だいたいが美容室か洋菓子屋だったりするはずなんだ。
気になったわたしはカフェを出て、四角いショートケーキみたいなその建物の前まで行ってみる。予想は見事に外れた。どうやら料理屋らしい。朝からコーヒー1杯しか飲んでいなかったことを思い出した。ちょこちょこ買い食いするせいで出費がかさんでいたが、年末年始も働いていた自分へのご褒美という理由をひねり出し、入店することにした。
低く落ち着いた声が出迎えてくれる。声フェチなわたしはそれだけでときめいた。けれど、うっとりしたのも束の間、店の奥から現れた若者を見てすぐに凍りついた。それに呼応するかのように若者も、なぜか凍りついた。
あのときの舌バカさん。思わずそう言いそうになった。そう、この若者こそが、例の牛丼屋でジャム&アイスクリーム丼をこさえていたあの男なのだ。
そう言ったのはわたしだ。舌バカさんはわたしと同じく固まったままで、まるで鏡を見ているみたい。
え……? いったいわたしをどのときの、誰だと思っているのだろう。久しぶり、と一方的に声をかけられて覚えている素ぶりをする人は、だいたい目の前の相手のことを覚えていない。もしくは、覚えているけれど再会するのが気まずいかのどちらかだと、わたしは思っている。
それはそうと、この男だけは料理屋にいてはいけない存在だ。まさか料理担当じゃあるまい。生きた心地がしないまま席に着き、とりあえずメニューを開いた。フィンランドやスウェーデンなどの国名が目に入る。北欧料理専門の店のようだ。舌バカさんと馴染みのない国の料理。リスクが高すぎる。わたしはなるべく味に間違いがなさそうな料理を選んで注文した。
■一度も味見しない。その珍妙な理由とは
「舌バ……いえ、お兄さんが作られているんですか?」
程なくして運ばれて来た料理を一瞥し、思わず質問した。舌バカさんは爽やかに「そうです」とだけ答えた。舌バカさんのくせに、まさかの料理担当。年始からすでに散らかり放題の私生活から気分を一掃しようと入店したのに、こんなオチがあったとは。わたしはその笑顔に絶望した。
仕方なく料理に目を落とす。一見まともそうに見えるミートボールと一緒に、2種類のジャムとチーズのようなものが1種類、それから粒マスタードとマッシュポテトが添えられている。悪夢のジャムの再来。そう思わずにはいられなかった。
片方のジャムにミートボールをディップし、おそるおそる口に運んでみる。絶対、控えめに言ってもまずいよ。
いい意味で想像とは違った。ジャムの程よい甘さと苦味に、鶏肉の旨味がものすごくマッチしている。控えめに言って、最高だった。
わたしにも食べられる味付けの料理が出てきてほっとしたところで、舌バカさんは不可解なことを口にした。
「はい。味見、しないんです」
「一度も?」
「一度も。僕が味見するとまずくなるんですよ。みんなおいしいおいしいって食べてくれるけど、僕は自分の料理がどれだけおいしいかをまったく知りません」
舌バカさんは自信満々で言った。それを受けて、わたしはゆっくりと料理に向き直り、ミートボールをもうひとつ口に運んだ。粒マスタードもいい感じ。わたしは料理の味を噛み締めながら、牛丼屋で遭遇したときと同様に、舌バカさんの存在を頭から削除する。そして、自分ひとりの世界に没入し、「今度はいつ有給とれるかなあ」なんて考えてみる。都合の悪いこと、理解できないことは追求しないのが人生の鉄則。ここでも40年以上かけて培ったスルースキルを発動した。
東京にはいろいろな人がいる。いろいろな人のなかには変な人もいるけれど、それに遭遇する確率は意外と低かったりする。それなのに、わたしの目の前にはいま、変な若者がいる。舌バカさんなシェフ。これが彼との出会いだった。











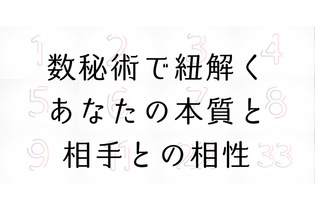










管理栄養士/ライター。恋心に寄り添うレシピを織り交ぜた恋愛小説を書いています。Kindleでは別作品の電子書籍も販売中。