小川たまか
1980年・東京都品川区生まれ。立教大学院文学研究科で江戸文学を研究中にライター活動を開始。 フリーランスとして活動後、2008年から下北沢の編集プロダクション・プレスラボ取締役。主に教育・働き方・性暴力などを取材
母を手放す #1 距離が関係を守ること
「重い」「しんどい」と苦しむ女性が多い母娘関係。もうすこし楽になりたい。母の呪縛から自由になりたい。そう思うなら、母を許すこと。それは手放すこと、解放すること。母娘関係をやわらかくするアイディア、ここにあります。


「母娘関係を楽にする」というテーマで寄稿してくださいと言われ、すぐその場で引き受けたものの、よくよく考えてみると、こんなに難しい話もない。母との付き合いは生まれてから35年間、今に至るまでずっと続いていて、その長い歴史の中で喜怒哀楽全てと、それ以外のもっと複雑な感情も抱いてきた。たぶんお互いに。母のことを考えるのは、自分がなぜこういう人間なのかを考えるのとほとんど同じだ。考えれば考えるほど書きたいことはたくさんあるし、母がこの文章を読むかもと考えると書けないこともたくさんある。それでも2000文字ほどのコラムに一つだけまとめるなら。
私は25歳の頃まで大学院生をしていて、実家暮らしだった。その頃が今までの人生で一番の低迷期。経済的に親に依存しているくせに研究に身が入らないこと、自分が社会にコミットできていないことへの焦りで、毎日「死にたかった」。母とは毎日のように一緒に夕食を食べていた。私がつくることも、母がコンビニでお弁当を買ってくることも、ときには外食してお酒を飲むこともあった。仕事からくたくたになって帰ってくる母の話を、「うんうん」と聞いた。
大学院を卒業して「フリーライター」という名刺をつくり、少しして実家を出ることを告げると母はぽつりと言った。「ご飯食べながらあなたと一緒に話すことが一日の楽しみだったのに」と。
家を出てからは新しい生活でそれなりに忙しくなった。母から来るメールへの返信も疎かになった。といっても、私はもともとメール不精で、友達への返信も2~3日くらいは遅れることがある。それを気にする友達はいなかったし、私もプライベートのメール返信にそこまでこだわらない。でも母は違った。朝のメールに夕方まで返信しないと、「どうしてるの?」「無事なの?」とメールが来る。次第に内容がエスカレートして、「どうしてメールの返信がないの?」「お母さんのことはどうでもいいの?」。5つ上の姉が「若い子が返信忘れるなんてよくあること」と言ってくれたらしいが、母は納得いかなかったのだと思う。最終的に「わかった、もうあなたはいないものと考える」というメールが来た。
友人の一人は、「束縛する彼氏みたいだね」と言った。私は恋人からもそんな束縛をされたことがなかったし、母を扱いかねていた。もうメールが来なければいいのに。しばらく疎遠になっても構わない。自分の生活のほうが大切だった。
でも、話を聞いていたもう一人の友人が言った。そんなの簡単、というように。「自分からメールしてみたら。メール来てから返信するんじゃなくて」。
メールが来るのがうっとおしいのに、自分からメールを打つ。何だか矛盾しているし、それだけのことといえばそうなのだけど、それから、メールが来る前にできるだけ自分からメールするようにした。そんなに頻繁にではなかったけれど。それでも母は、嘘のように落ち着いた。
仕事でするような丁寧さ、慎重さ、ときには作為的な朗らかさで母にメールを送るようになって、ああ、母と私は他者になったと思った。家族だって、母娘だって他者であり、他人。気を遣わなければ関係が壊れてしまう。「気を遣う」というよそよそしさは距離をつくるが、距離は関係を守ることもある。私が母に気を遣い始めた頃、母もまた私に気を遣い始めたのかもしれない。それは幸運だった。ギリギリのところでバランスを取ったと今になって思う。遅い遅い親離れ・子離れだった。
■自分と母との境界線はどこなのか
母はずっと中学の国語教師をしていた。私も姉も昔から本を読むのは好きだったが、文学や日本語に詳しい母を誇りに思い、心酔していたのは姉よりも私の方だろう。大学院修士課程の2年目の終わり、どうしても修論が書けなくて中退したいと言った私に、母は「あなたが日本文学で博士号を取るのは、お母さんの夢だったのに」と言った。結局もう1年かかって、みっともない修論を書いた。それが限界だった。
親からの期待がプレッシャーだった、親の敷いたレールの上を……という子どもがいることは話に聞いていたけれど、自分もそうだったのかもしれないと思うようになったのは仕事を始めてしばらく経ってからだ。
母のことは大好きだし、責めるような気持ちはない。母が私に与えた影響について考えたことで、かえって昔より今の方が良い関係を築けていると思う。何より自分自身、生きるのが楽になった。
でも適切な距離を取れるようになったこととは別に、考えることがある。お母さん、自分とは何だろう。どこまでが自分で、どこからが母なのだろう。どうして私は文章を書いているのだろう。昨年、心理カウンセラーの男性は私に、「タマネギの皮をむくようなもの。本当の自分というものはない」と言った。たとえ答えがなくても、あなたのことを、私はずっと考え続けるのだろう。











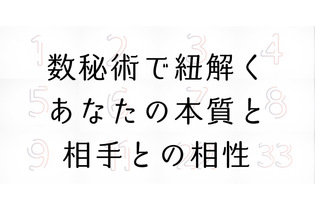










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。