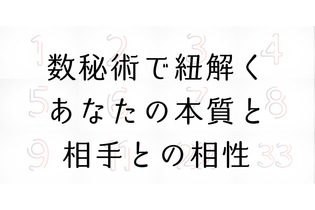私ってさびしい女ですか?
私は自由である。風のように海のように空のように生きている。なんて書くとかっこいいけれど(そうでもないか?)、つまり、私を拘束してくれるものは、月に何度かの〆切ぐらいしかないってこと。


会社勤めではないから就寝時間は決まっていないし、服装だって何のルールもない。誰かの食事を作る義務もなければ、稼いだお金はすべて自分のために使える(たいした稼ぎではありませんが……)。パソコンさえ持っていけば、いつ旅行に出たとしても何の差し支えもない。気の向くまま好きなようにしていても、誰にも何の迷惑もかからない。
確かに、若い頃、こういう状態が理想だった。将来を心配して、今の自分を律するなんてつまらない生き方だとも思っていた。中年と呼ばれる年齢になっても、それは変わらない。
しかし、若い頃は知らなかった。自由とはイコール孤独を受け入れた上で成り立っている、ということを。そう、人にあてにされないから自由でいられるのだね。 自由を欲するのなら、同じ分量だけ孤独を抱えなければならない。
な〜んてかっこつける私に、友人がいった。「人間、誰だって死ぬ時は一人よ。家族がいようが恋人がいようが、たった一人で死んでいくの」 離婚歴のある彼女は、子どもたちと恋人と一緒に住んでいる。思いやりにあふれた人だから、きっと私をなぐさめるつもりだったのだろう。しかし、こっちの孤独はそんな観念的なものではなく、日常のいたるところにころがっていて、思わぬ時にばったり出くわしたりする。その上、不便とセットになっていることもけっこう多い。
今は両親がいる自宅とそこからクルマで十五分の仕事場を行ったり来たりの、ハーフ一人暮らしだけれど、数年前までは東京で独り住まいだった。夜中まで飲んでいてもたいていのバーからはタクシーでワンメーター程度という港区某所の、主に外国人向けのマンションで自由を謳歌していた。
原稿を書き終えると誰かを呼び出しては飲み歩き、誰もつかまらなくても知り合いのバーにいって夜を使い果たす、そんな生活だった。とにかく忙しかったし、孤独を感じる暇もなかった。
けれど、体調を崩したりすると、唐突にそれはやってくる。高熱と頭痛で思考は止まり何も食べられなくなっても気軽に呼び出せる人は、なかなか思い浮かばないものだ。で、孤独と枕を抱えて寝ている時に限って、〆切催促の電話がかかってくるわ、宅急便のドライバーがインターフォンを鳴らすわ……。一人暮らしってつらいなあと実感するのはこういう場合だ。
孤独は必ずしも、静寂の中に潜んでいるわけではない。案外、インターフォンの音だったり、もしくは都会の喧噪だったり、にぎやかなふりをして日々の暮らしに紛れ込んでいる。
独身者はそれとどう向き合うべきなのか。それはもう、二者択一しかない。多少の束縛や我慢を受け入れて脱出するか、上手に飼いならすか、のふたつにひとつ。私は、まったく自覚のないまま、後者を選んでいた……らしい。
今では、すっかり慣れて、それを楽しむことさえできるようになった。例えば、一人打ち上げ。長かった原稿の終わりはたいてい深夜か明け方になるのだけれど、そんな時は一人でシャンパーニュを開け(最近はノンアルコールビールですが)、鏡に向かってグラスを差し出し、「お疲れちゃん」と自分に乾杯をする。かなり不気味な光景なのは百も承知……。
なんてエピソードを、こうして大げさに書いたり他人に話したりするのだけれど、それもまあ、孤独の解消法のひとつかもしれない。読んでくれる相手、もしくは聞いてくれる相手がいるってことだから。
孤独という言葉には、どうしても、負の印象がつきまとう。でも、悪いことばかりじゃない。塩味が甘味を引き立てるように、孤独を感じる瞬間があるから、大切な人との係わりの価値がわかる。
要はバランスではないだろうか。独身だからって自由気ままなだけではないし、家族がいても孤独を感じることは少なからずある。誰しもが、両方を抱えて生きている。その配分こそが個性だし、その人の生き方なのだ。
Text/Ririko Amakasu
甘糟りり子
あまかす りりこ
作家。1964年横浜生まれ。玉川大学文学部卒。
都市に生きる男女と彼らを取り巻くファッションやレストラン、クルマなど
の先端文化をリアルに写した小説やコラムで活躍中。『中年前夜』
『オーダーメイド』など著書多数。読書会「ヨモウカフェ」主宰。