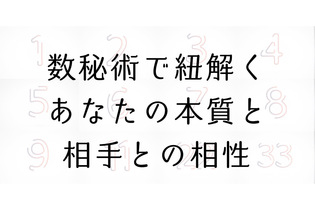3月の約束と、6月のアーモンド。
「わたしは、いつも胸を締め付けられるような懐かしいJ-POPばかりを聞いていた」エッセイスト中前結花さんが音楽にまつわるエピソードを綴る連載「いつもJ-POPを聴いていた」、2年越しの続編がスタートします。第1回は、レミオロメンの名曲『3月9日』、そして先輩と交わした約束のこと。

「ああ、ええと、わたしと奥様の関係は……」
マイクを握って、顔を上げる。人前に出ることはそれほど苦じゃないタイプではあると思っていたけれど、これほど急にマイクを握ることもめずらしい。目の前では、テーブルに着いた人たちの視線が一同にこちらに注がれていて、弱ったな……とわたしは思った。
ただ、そうは思いながらも、「こんなことが起きるかもしれないなあ」という予感が朝からなんとなく胸の内にあったのが本当のところだ。昔から、“胸騒ぎ”と“突然の抜擢”には、なぜだかそれなりの自信がある。
その日、わたしは過去の職場でお世話になっていた先輩の結婚式に招待してもらっていた。ずいぶんとシャンパンも飲ませてもらっていたけれど、どれも“ノンアルコール”だから、気分は高揚していても、幸い頭は素面だった。
「ノンアルコールもたまには役に立つじゃないの」
とわたしは思う。
コロナ禍の結婚式は、すべて他とは勝手が違った。
この日まで、毎朝テレビのワイドショーを眺めるたびに、
「先輩の結婚式はどうなるだろうか……」
といつもそればかりを考えてきた。
予定どおり開催されるのか、開催できないのか。もちろんそれが大きな問題ではあるのだけど、先輩の性分をちゃんと知っているものだから、開催するにしてもしないにしても、胸を痛めながら、悩んで悩んで決めるのだろうな……と考えて、こちらまで胸がチリチリと痛んでしまう。
そして結果、最小限に人数は絞られ、式は開催された。席は一人ひとりアクリルパネルで覆われて、両家のご両親はリモートで出席。換気や除菌は徹底して行われていて、不安な想いをすることは、一瞬たりともなかった。その気遣いに、「やっぱり先輩らしいな」とわたしは心から思う。
そして、もうひとつ。式では、H Jungle with t の『GOING GOING HOME』なんかが流れたりして、ゆらゆらと揺れて歌う浜ちゃんの姿を思い出しながら、懐かしさと一緒に、なんだかふっと心も揺さぶられた。
「これだから、同世代の人の結婚式はいいよなあ」
と、わたしはしみじみ思う。
と言っても、新郎である旦那さんとは8つほど離れてはいるのだけど、わたしにとっては、自分よりも10ほど上の人ぐらいまではみんな同世代だ。
『J-POP』と呼ばれはじめた、平成のはじまりを彩った頃の音楽や、その頃のエンタメをいたく好み、歳上の人とばかり気が合うわたしは、どうやら実年齢と少しチグハグなところがあるようだった。わたしは、いつも胸を締め付けられるような懐かしいJ-POPばかりを聞いていた。
*
けれど、その日会場に向かいながら聞いていたのは、レミオロメンの『3月9日』だった。
「あれって、卒業ソングじゃなくて、結婚式の曲らしいよ」
と誰かから聞いたのはもうずいぶん前の話だけど、わたしのよく聞くプレイリストの中では、レミオロメンはまだまだ新しい方だ。以前から、先輩のことを考えると、この曲がよく流れる。
しっかり者で、それでいて誰よりも繊細で。負けず嫌いと「これでもか」という気遣いが同居するような、そんな強くて弱くて、とてもやさしい女性だ。それにわたしはこの先輩から、ある時とてもとても大切なことばをもらった。
幸せな心地から、足取りは軽くなる。
「先輩、泣いたりするのかな……」
と、ちょっと意地悪なこともドキドキと考えてみたりした。

そうして、アクリルパネルに囲まれた席ではあれど、美味しい料理とたのしい催しをただゆったりと安心して楽しんでいると、式も後半に差し掛かったところで、その機会は突然訪れる。司会の男性の、
「実は、デザートのケーキの中に、アーモンドが入っているお客様がいらっしゃいます!」
という声が響いたのだ。
今思えば、どうしてわたしはこの瞬間から確信していたんだろう。
「ああ、きっとわたしのケーキだ……」
そして本当に、ケーキの中からそのとき、“コロン”とアーモンドはこぼれ落ちた。
「ほら、やっぱりね……」
と、わたしは胸の内で即座に納得する。だって、朝からなんだかそわそわとしていたんだもの。
そんなわけで、
「では前へ!」
と呼び出され、わたしは今、汗ばむ手でマイクを握っているのだった。
ぱっと右手側に目線を向けると、ほどけるような笑顔で微笑む新郎新婦の顔がある。なんだか余計に照れてしまって、わたしは仕方なく、手前の方に座っていた初対面のやさしそうな女性に目を合わせながら、ようやく話しはじめる。こくり、こくり、と頷いてくれた彼女は、はたして誰だったのだろうか。その表情と相槌に大変に助けられた。
「ああ、ええと、わたしと奥様の関係は……、わたしにとって、新婦のMさんは、前の前の前の……前の? 職場でお世話になっていた先輩です。実は、一緒にお仕事をさせていただいていた期間は、ほんの1年半ちょっとなんです。それも、気づけば、もう7年ほど前のこととなってしまいました。だけど、以降は疎遠になるどころか、それからはプライベートでも、本当にお世話になっていて。辛いことや嬉しいことがあれば、甘えてすぐ連絡をさせてもらうような間柄で、先輩は、その度に、相談に乗ってくださったり、喜んでくれて。
特に忘れられないのが、これももう5年近く前ですけれど、わたしが、わたしが、いちばん辛いときに……」
そして、わたしは5年ほど前の、3月のある朝のことを思い出していた。ぼんやりと天井を眺めながら、ただどうしようもなく、ソファの上に足を抱えて座り込んで、もう何時間も何時間もそのまま体を動かすことができなかった。ごはんも喉を通らない。
今思えばそれは、ずいぶん遅いけれど、わたしがはじめて経験した“失恋”……だったのかもしれず、だけどなんだか事情がとても複雑だった。誰でもかれでもに構わず話せるようなポップさには大層欠けたエピソードだったのだ。
けれど、今なら笑ってどんな場所でも話すことができる。
「駅の書店でなんとなく手にとった雑誌を見て、ただ何気なく、見よう見まねで、玄関に“盛り塩”をしてみたんです。そしたら、その日から彼が忽然と姿を消して、家に帰ってこなくなっちゃったんですよ。だから、“盛り塩”の効果だけは、わたし信用してるんです(笑)」
身近な人のいわゆる“失踪”や、交番や警察に通い続けながら泣き続ける辛さも、時が経てば人はやんわりと受け入れてしまって、笑ってそんなふうに話せるのだから、「日にち薬」とは本当に偉大で、人間とはとっても恐ろしい。
もっとも、彼とはその翌月ようやく連絡が取ることができ、体は無事で、彼なりに背負っていた事情があったのだと、理解は難しくとも承知することはできたから、
「すべてを忘れてしまおう」
と無理にでも決め込んでしまうことができたのだけれど。
それでも、当時は本当に苦しくて苦しくてしょうがなかったのも、またどうしようもない事実だった。とても身近な友人にだけ、
「耐えきれない」
と連絡をしてしまうわたしに、みんなは決まって同じことを言った。
「だから、言ったんだよ!」
「これで良かったと思う、もっと良い人がいる」
わたしは力無く「うん、そうかもしれない……」と答えるほかなかった。
ただ、そのすこし前、母を病気で亡くしたとき、彼に支えてもらった、とわたしは本当にありがたく感じていた。だから、わたしは彼を一生をかけて支えなければいけないのだ、と、どこか胸で勝手に決め込んでしまっているところがあった。だけれど、本当はそう思うことを支えに、なんとかわたしが生かされていたのかもしれない。
“友人の評価はイマイチでも”愛する、とは「実際にはこういうことなのだ」ということを、そんな時さえ、ミスチルの歌詞を振り返りながら、わたしは、まざまざと思い知っていた。
これから、日々の苦しいことを、嬉しいことを、わたしは誰に話して生きていくんだろうか。誰と分け合っていくんだろうか。舫綱(もやいづな)を離された小舟がぷかぷかとあてもなく流されていくように、本当に、ひとりぼっちになってしまったような心許なさが後から後から押し寄せてくる。
けれど、そのときの先輩からの返信をわたしは今でも忘れることができない。彼を責めるのでもなく、わたしを励ますのでもなく、ただたったひとこと
「わたしは、ゆかちゃんのことすごく好きだよ」
とあった。
涙は出尽くしたかと思っていたけれど、また類の違ったような涙が急にこみ上げて、眉間がジリジリとすごく熱くて痛くなる。母を失い、彼を失い、わたしは誰にも愛されていないものになったのだと、大切なものではなくなってしまったのだと思っていた。「ひとり」を思い知っているような気分だった。
気づいたことは 1人じゃないってこと
瞳を閉じれば あなたが
まぶたのうらに いることで
どれほど強くなれたでしょう
あなたにとって私も そうでありたい
レミオロメン『3月9日』
そして、続けざまに、
「今から出てこれない? 何時でもいい、待ってるよ。ちょっと歩こうよ」
と誘い出してくれたのだ。
わたしはヨレヨレの服のまま、化粧もそこそこにヒールのない靴で外に飛び出した。
「そうか、『ひとりじゃない』じゃないか」
ということを、もっと強く感じたいと思った。
指定された「清澄白河」の駅につくと、
「よし、こういうときは歩きながら話そう」
と、先輩はどんどん川の方へと降りていく。そして、何時間も何時間も川沿いを歩きながら話を聞いてくれた。
「良いとか悪いとかはわかんないけど、好きなものは仕方ないもんね」
「とにかく、よくがんばったよね」
「どんな形でもいいから、幸せでいてほしいよ」
と何度も伝えてくれる。
「わたしも、Mさんに幸せでいてほしいです……」
と泣きながら伝えると、
「そうなんだよ!(笑)だからさ、お互い、幸せになろうね。幸せでいよう」
と、そのとき足をクタクタにさせながら、夕暮れの川沿いでわたしと先輩は、笑いながらではあるけれど、とても真剣に約束をした。
そして、何処だかもわからない、たどり着いた先の適当な焼き鳥屋に入って、久々にお肉にかぶりついたら、なんだか心にようやく血が通いはじめた気がした。そのとき、わたしは初めて「いぶりがっこ」というのを食べた。おいしいおつまみは、だいたいこの先輩から教わったものだった。
「お姉さんだからね」
と言って、3つしか違わないけれど先輩はよく奢ってくれる。
「わたしが辛いときは、今度は励まして!(笑)」
と言って、そこで先輩とは別れた。
ぱっと見上げると空はもう本当に真っ暗で、だけどよくよく見ていれば、小さな星はちゃんといくつもあって、それは忘れられない大事な大事な夜になった。わたしも誰かが暗い暗い淵にいるときは、「大事だよ」とわたしの気持ちをいちばんに伝えてあげたいと思った。誰かにとってわたしも、そんな人でありたい。
そこから数年、特に恋愛とは関係なくとも、ふたりで飲んではどちらかが何かに胸を痛めて涙を流したりもして、その度に
「だいじょうぶ、だいじょうぶ」
と励まし合ったりした。
なぜだか一緒に働いている頃から、この先輩が涙しているとわたしも泣いてしまう、ということが度々あって、本当に本当に、ずっとずっとこの人のことがわたしは大好きなのだと思った。

そして一昨年、先輩は結婚した。
偶然、初めて行った日比谷の映画館で「ねえ!」と声を掛けられて振り向くと、そこには先輩と、体が大きくて本当にやさしそうな男性が立っていた。
「え、あ!! 旦那さんですか? お世話になってます!!」
と頭を下げたら、
「はじめまして、こちらこそ」
とその男性も丁寧に頭を下げてくれる。そのふたりの立ち姿を見ただけで、わたしは
「ああ、よかった」
先輩は幸せになれたんだと、本当に心からそう思えた。
それから夫婦のお宅にお邪魔したりして、3人で楽しくお鍋をつついたりさせてもらうようにもなった。いい人といい人がふたりで住む部屋は、すごくすごくやさしい場所だった。
「幸せになったんだなあ」
と、わたしは真冬でもうれしくて飛び跳ねるようにして帰った。
コロナで延期が続いたけれど、今日、ようやく、そんなふたりの披露宴なのだ。
どこまでも心が尽くされた配慮いっぱいのおもてなしと、ふたりの人柄が本当によくわかる選曲。そして、余興まで新郎新婦のふたりが楽しませてくれた。旦那さんの大好きな志村けんさんに因んで、ヒゲダンスでちょっとした大道芸まで披露してくれたのだ。
「おうちで練習したのかな」
とふたりの様子を想像すると、ふふふと嬉しくなって、ちょっと涙が溢れた。
だからわたしは、涙をふいたハンカチをぐちゃぐちゃにして握りながら、マイクに向かってしまうことになる。
「——特に忘れられないのが、これももう5年近く前ですけれど、わたしが、わたしが、いちばん辛いときに……、川沿いを何時間も一緒に歩いてくれて。いろんな話を聞いてくれて、聞かせてくれて。だから……本当にいい人なんです。本当に。大好きなんです。おふたりのお宅にお邪魔させていただいたとき、そんなMさんがとっても楽しそうにされていて。わたしは……ああ、泣いちゃいけないけど。ごめんなさい。とにかく、すごく嬉しかったです! 最高だなって思いました! 末長く、本当にお幸せに。おめでとうございました」
頭を下げ、拍手を浴びると、わたしはプレゼントを受け取って席に戻った。
隣の席のよく知る先輩に
「突然だったのに、よく喋れたね」
と囁かれたから、
「わたし、こういうの、絶対当たるんです(笑)」
と前を向いたまま囁き返した。
アーモンドが、わたしのケーキに入っていて本当に良かった。暗い淵でなくたって、いちばん明るくて幸せな場所にいるひとにも「好き」とちゃんと自分の気持ちを伝えることは、やっぱりとても大事で幸せに思えた。
旦那さんの横で微笑む先輩も、カメラ越しにご両親に手を振る先輩も、チョビヒゲを着けて踊る先輩も。すごくきれいで本当に本当にかわいかった。
先輩は、あの日の約束を叶えてくれている。

会場を後にするとき、プチギフトと一緒に、わたしにだけ先輩は小さな小袋をくれた。
「これ、なんですか?」
聞けば、ふたりで神田明神まで行き、わたしの幸せを祈ってお守りまで買ってきてくれたという。思わず吹き出しながら
「ちゃんと幸せになります(笑)」
と伝えると、ふたりは頷きながら微笑んでくれる。その顔は、とても「夫婦」だった。いつまで経っても、「わたしもこんなふうでありたいな」と思わせてくれるひとがいることは、どれほど心強いだろう。
帰り道、そっと袋を覗いてみると、厄払いと恋愛成就のお守りが丁寧に包まれていた。弱ったな……とわたしは思った。
ただ、そうは思いながらも、「そんなことが近々起きるかもしれないなあ」という予感がなんとなく胸の内にあるのも本当のところだ。昔から、“胸騒ぎ”と“突然の抜擢”には、なぜだかそれなりの自信があるから。
くしゃくしゃのハンカチを小さなバッグに詰め込みながら、『3月9日』を聴いて、すっかり暗くなった同じ道をまた帰る。曲はバラードなのに、胸はずいぶんと弾んで仕方なかった。
Photo/片渕ゆり(@yuriponzuu)