「エロって一体なんだろう?」紗倉まなが“AV女優”に抱く果てしなさとその先にある希望
DRESSの『運命をつくる私の選択』は、これまでの人生を振り返り、自分自身がなにを選び、なにを選ばなかったのか、そうして積み重ねてきた選択の先に生まれた“自分だけの生き方”を取り上げていくインタビュー連載。第二回のゲストは、AV女優の紗倉まなさん。

18歳の時にAV女優への道を選んだ紗倉まなさん。その後トップ女優として活躍する傍ら、自身の日々を綴ったエッセイや独自の世界観を築く小説を続々と発表。気鋭の文筆家としても注目を集めています。思春期の葛藤をはじめ、変化した母との関係、仕事を通して感じる自己表現の形、筆を執る意味、そして今の世の中に思うこと。数々の選択の折に感じた想いをお話していただきました。
取材・文:丘田ミイ子
編集 :小林航平
■家族離散の中で自立を見つめた思春期

――紗倉さんはどんな子ども時代を過ごされたのでしょうか?
家で絵を描いたり工作するのが好きな、どちらかというと静かな子どもでした。友達も多い方ではなかったのですが、習い事をたくさんやっていたので都度いろんなコミュニティには関わっていましたね。経済的に余裕のある家ではなかったのですが、書道、水泳、バレエ、英会話、ダンス……あらゆるジャンルのことをやらせてくれました。英才教育というよりは、私がなにが好きでどんなことと合うのか。両親がそういうきっかけを模索して試そうとしていてくれたのかなと思います。網羅していくうちに淘汰され、好きなものが残っていくような。そんな感じがありましたね。一番好きだったのは書道。ひとりで淡々と続けていけるのが自分の気質に合っていたのかもしれません。
――少し形は違いますが、作家として筆を執られている今の紗倉さんにも通ずるようなエピソードですね。家で過ごすことが多い中、ご家族とはどんな時間を過ごされてきたのでしょうか?
両親のことは好きだったんですけど、父と母双方の立場を考えて立ち回ることが自分の役目のように思っていた時期がありました。これは一人っ子あるあるかもしれないんですけど、夫婦喧嘩が勃発した時には、母には「お父さんひどいよね」、父には「お母さん言い過ぎだよね」と、それぞれをフォローするみたいな……(笑)。家族の中のバランサーのような役割を勝手に担っているようなところがあったんですよね。本音を言えなかったというよりは、そもそも本音と呼べるものもなかったんだと思います。それよりも、いかに家にいる時間を快適にするか。両親が離婚する中学の時まではそんな感じがありました。
――ご両親の離婚を経て、家族の中での立ち位置やご自身の中になにか変化がありましたか?
両親の離婚が直接影響しているかは分からないのですが、タイミング的に自立を見つめるきっかけにはなったと思います。「我が家は解散です、これからは一人ひとりが自立しながら生きていきましょう」というところで家族が合意したのですが、その後まもなく進路を選ぶ折にきて……。「家もこういう形になったのだから、いっそ親から離れて寮に身を投じてみたい」。実家から離れている高専を選んだのは、そんな精神的自立の芽生えがあったのかもしれません。
――高専は五年制の寮生活ですよね。これまでとは違う生活が待っていたのではないかと思うのですが、学校生活はどんなものでしたか?
入学前の説明会でコンクリートを作る授業を見学したんですけど、一度作ったものを壊していくっていう工程をひたすら見せられて……。「こんなこと毎日やってるの? 楽しそうだな」と思ったんですよね(笑)。「黙々と作業することが好き」という幼いころからの根幹が影響していたのかもしれません。寮の部屋は飾り気がなく、ベッドと3着くらいしか入らないロッカーと事務机と椅子。勉強して寝るという要素だけで完結したような部屋でした。
■18歳、ひとりで決意したAV女優への道

――その高専在学中にAVのお仕事に進む決心をされたんですよね。その選択に至るにはどんな経緯やきっかけがあったのでしょうか?
「あの時の自分はなぜこの仕事を選んだんだろう?」。そんな自問自答は年々更新されていくんですよね。ネガティブな意味合いではなくて、純粋に「あの時の自分の一番の気持ちってなんだったのかな?」って探るような心持ちで……。それくらい漠然としたものでした。先々の未来を想定して考え抜いてから入るべき業界だとも思うんですけど、同時に考え過ぎていたら選ばなかった仕事なのかもしれないとも思ったり。自分の心を思いもよらぬ方向へ動かしてくれそうな真新しい機会に触れたいという思いがずっとあったので、衝動的な勢いで始めたところもあったのかなと思いますね。
――自分の中のひとつの革命というか、そういった感覚が近しいでしょうか?
最初はそうだったかもしれません。そもそも、どんな女優さんがいるかも、どういった業界なのかもよく分かっていなくて、社会の中でブラックなイメージがあることすら知らない。そんなまっさらな状態からのスタートでした。振り返ってみると、作ったコンクリートを潰していくのを見て「面白そう、この学校に入ってみたいな」と思ったのと同じようなきっかけと熱量だったような……(笑)。そんな気がしています。
――知らない世界に飛び込むことに不安もあったのではないかと思うのですか、誰かに相談したり打ち明けたり、そういったことはありましたか?
なかったですね。親友には話そうとも思っていたんですけど、相当噂が回って知られている状態でのスタートだったので、あえて大きく打ち明けるっていう選択はなく……。「このお仕事で生きていこう!」みたいな覚悟も今思うと全くなかったし、ちょっと覗いてみたいなっていう感じで事務所に応募したんです。その後も面接や採用・不採用の結果を待ったりと就活のようなステップがあったので、「これ、受からないかもしれないなあ」と思ったりして……(笑)。
――進路のことに関わらず、他者に迷いや思いを話すことはあまりしない方だったのでしょうか?
誰かと本音を曝け出してぶつかり合うみたいなことって、今まで一度もないかもしれません。「関係が崩れちゃうんじゃないか」という気持ちもあるし、いかに互いが心地よい関係でいられるかっていうことに重きを置いているタイプだったんですよね。こういうことを言うと、「さみしいね」とか「冷たいね」と言われることもあったんですけど、私の場合は大事に思っているからこそ“言わない選択”をとることもあって……。 思っていることを言わないことで人間関係を心地よいものにしておきたい。言ってしまえば、そんな気持ちがその時の私の“本音”であり、コミュニケーションのひとつの形だったんです。大人なってからは伝える選択をとることもあるけど、コミュニケーションって言葉だけじゃないなって。そういったことは常々考えていますね。
■自立を経て変化した母子の関係

――そんな中、お母さまには自らAV女優の道へ進む決心を打ち明けられたんですよね。エッセイや小説のモチーフの中にもそのエピソードが描かれていますが、当時の紗倉さんにはどんな思いがあったのでしょうか?
同業の方や周りの人からも「カミングアウトが一番分厚い壁だよね」「どうやって納得してもらったの?」なんて話が出ることもよくあるのですが、そう思うと我が家はまだ言いやすい環境だったのかもしれません。両親が離婚してからは母のことを“母親”としてではなく、“ひとりの人間”としてみている節があって、自分の選択が母に影響するとも思ってなかったんですよね。これまでは家の中のバランサーだったけど、離散したらその必要もなく、親子共に依存しないところがあったのかも。家族が密接に関わり合っていたらもっと言いにくかったんじゃないかなって。なので、ちょっと得した気持ちではあります。どっちがいいか悪いかは分からないんですけど(笑)。
――紗倉さんの選択に対するお母さまの反応はどのようなものだったのでしょう?
「あなたはなにに対しても興味を持たなかったから、興味を持てることを見つけられたことにびっくりしている」「この子はこの先どうやって生きていくんだろう?って不安だった」と。最初にそう言われたんです。私がなにかしらの目標や生きる道を提示したことで、母もようやくひとりの人間として一定の距離感を以って話してくれるようになったんですよね。
――親子や家族って対人関係としてフラットな関わりや対等な距離感を保つのが難しく、そういった悩みを持っている方も多いのではないかと思うのですが、その関係を築くにあたってはどんなやりとりがあったのでしょうか?
母自身が変わって歩み寄ってくれたことが大きかったと思います。昔はもっと感情的で過干渉な人でした。価値観のアップデートが苦手で、今でいうと「毒親」にカテゴライズされかねない一面もありました。私の成績を褒めてくれた近所の人に「うちの子は本当にバカなの」なんて言っているのを聞いた時は、子どもながらに「なんで違う人間なのにこんなに卑下されなきゃいけないんだろう」「この疑問をいつか晴らせるような生き方がしたい」って思っていました。でも、そんな心の奮闘の連続がいつしか自分の心を研ぎ澄ませ、選択肢をも広げるきっかけに繋がっていたんですよね。反面的ではあるんですけど(笑)。
――自立というのが、変化のひとつのフックになっていたのですね。
そうだと思います。仕事を始めてから、私も以前より自分の気持ちが言えるようになりました。「歳を重ねるほど親子の関係は大変なことになるんじゃないか」と思っていたのが、逆に丸くなってくれたというか……。母が都会で働いているということも影響しているかもしれませんね。社会に立ち込める平成や令和の匂いに「自分の感覚は時代から置いてけぼりなんだ!」と気づくこともあったみたいで……。それに追い討ちをかけるように私も「それは古いよ」とかやいやい言っていたら、いろいろ聞いてくれるようになったんです。
――自分の進む道を選び取ることや、それぞれのフィールドを持つことで関係性が変化したのですね。
今も「生存確認!」と言って連絡がよくくるんですけど、その流れで母の会社の愚痴を聞いたり、「大変だね、私の仕事ではそういうことはないわ」って答えたり……(笑)。私の選択と母の選択、それぞれの道で自立して生きることで、姉妹のような友人のような独立した関係性ができつつあるのかもなんて今は思います。なにかしらの組織に属することや社会で働くことの重みや責任。そんなことを働く母から教わっている部分もありますね。

■エロってなんだろう? 働くことで気づいた表現の在り方

――「働く」という言葉が出てきましたが、実際にこの道を選択し働くことで、ご自身の生き方や考え方が変化することはありましたか?
自分は果たしてこの仕事に向いているのだろうか。正直なところ、今でもそんな気持ちがあります。自分の中の手応えと世の中のジャッジの間にはいつも結構な差があって、確実な達成感を感じたことがあまりなくて……。あと、AV女優としてのお仕事をすればするほど、セクシーや色気の基準ってわからなくなってくるんですよね。
――なるほど……。たしかに、人によってその在り方には違いがありそうですね。
そうなんです。いろんな表現の仕方があって、「色気」「セクシー」と捉えるポイントも人によってさまざまなので。フェチズムも含めてエロってこんなに細分化されるんだなって。時代的にもここまで情報が炙り出された状態で「エロって一体なんなんだろう?」って。日々その果てしなさを痛感しています(笑)。でも、だからこそ希望があるというか、自分のやり方で頑張ろうっていう気持ちにもなれるんですよね。AVは自分を支えてくれている自己表現のひとつ。そんな感覚があります。
――紗倉さんのお話を聞いて、お仕事の選択は人生におけるひとつのターニングポイントであり、その中で自己への新たな発見や考え方のアップデートが生まれていくものなのだということを改めて感じました。
AVのお仕事はそもそもが裸でなにも隠せない、自分のアイデンティティを前面に出す仕事です。そこに踏み切ったからこそ、いろんなことにチャレンジできる心持ちになれたようなところがあるんですよね。このお仕事を選択したからこそ、今の自分がいるんだなあって。現場は好きだけど同時に体力仕事でもあるので、先々のことを考えて「100%のパフォーマンスをどこまで維持できるだろう?」という思いが過ぎることもあります。「今日は要領得ないことやっちゃったな」とか、帰り道にひとり反省会を開いて悶々とする日々です(笑)。
■“えろ屋”という独自の肩書き、その選択に秘めた想い

――紗倉さんはご自身の肩書きを「えろ屋」と銘打たれていますよね。最新のエッセイ集『働くおっぱい』でも、その肩書きに対する葛藤について書かれていたのが印象的でした。「えろ屋」という独自の屋号、その言葉の裏にはどんな思いがあったのでしょうか?
コンプラ問題によって、メディアなどで自分の肩書きが「セクシー女優」と変換されることに違和感を感じていたことが発端でした。自分のやっていることを照らし合わせた時に、“セクシー”という爽やかな響きが自分の中でぬるく感じるようなところがあったんですよね。“セクシー”以上のことをしているから、そこをぼかされると傷つく部分もありました。
――なるほど。自分のお仕事と向き合ってこそ生まれた、ひとつの言葉にカテゴライズされることへの違和感がきっかけだったのですね。
勝手に変えられちゃうんだったら、いっそのこと自分で「AV女優」という響きや解釈に近いものを探そう! と思って、「えろ屋」という言葉に辿り着きました。下町感があってちょっと泥臭い感じの響きが自分に近いなって思って……。でも、本心を言うと「AV女優」と表記してくれた方がありがたいんです。それができるまではまだまだ壁が削れていないから、それまではこれを使おう! と。そんな思いからの選択でした。
――紗倉さんならでは切り口と言葉によって日々の想いや葛藤が綴られたエッセイや小説に心を動かされる方は多くいらっしゃると思います。文筆というお仕事への選択にはどういったきっかけがあったのでしょうか?
少し話が遡るのですが、高専時代からの親友が分厚い文芸誌を読み込んでいるような子だったんです。私は学校の勉強に関連する参考書しか読まないようなタイプだったので、文学には全然詳しくなくて……。彼女が自分の価値観を押し付けるようなことは決してなかったけれど、読書をしている時の佇まいがとてもかっこよかったんですよね。どんな場所でもどんな時でもブレずに淡々と物語の世界に没入できる人だったので、「そんなに傾倒できる趣味があるのっていいなあ」と思っていました。そんな彼女が「これ、あなたっぽいからよかったら読んでみて」ってくれた本がすごく面白くて。桜庭一樹さんの『少女七竈と七人の可愛いそうな大人』。それが私にとって鮮烈な、最初の読書体験でした。
――学生時代にそんな運命的な出会いがあったのですね。
小さいころはむしろ文を書くことが苦手だったのですが、高専で過ごす毎日がレポート地獄で書く機会そのものが増えたこともあり、「書くことへのトラウマ」が強制的に補正されつつもありました。そんな折に件の親友との出会いがあったんですよね。このお仕事をしはじめてからは、SNSやブログを更新することが自己PRにおける重要なツールだということも知りました。更新の度にだんだん書きたいことも増えてきて、「文章を書くって意外と楽しいかも」って思い始めました。ずっと苦手だと思っていたことが好きになったり、選択肢に躍り出るようなこともあるんだなって。
■執筆は自分の感情に気づくお守りのような時間

――文壇デビュー作の『最低。』、二作目の『凹凸』、そして最新作で野間文芸新人賞の候補作にもなった『春、死なん』。性をモチーフに、さまざまな立場に生きる人の姿が物語の中に切り取られていましたね。
小説を発表するたびに一喜一憂しています。褒めていただけることもありますが、酷評を受けることももちろんあって……。書いても不安、書かなくても不安なんですけど、それでもやっぱり書かずにはいられないところがあるんですよね。最初に小説を書いた時もそんな気持ちでした。自分が書かずにはいられないから書いているけれど、「脅迫概念に近い部分もあるんじゃないか」とか「自己満足だよなあ」とか思ってしまうこともあります。
――そんな葛藤の中で作品を発表し続けるという選択や、そのモチベーションはどのように保っているのでしょうか?
私の場合は、その場ですぐ自分の感情に気づけなくて、家に帰ってからだんだん腹が立ったり悲しくなったり。そんな思いを文章に叩き出すことが多いかもしれません。嬉しいことは嬉しい! で完結するんですけど、「あのモヤモヤはなんだったんだろう?」っていうのはいつまでも残るんですよね。でも、悲しみや苛立ちがあるからこそ、より奥行きのある自分の感情に気づけたりもする。
――日々のもどかしさや生きづらさが原動力になっているのですね。
そうですね。ネガティブな感情で築かれているエネルギーや土台があって、それらをどれだけ整えて人前に出せるか、みたいな……。モチベーションというよりも、自分で自分の首を締めつつ、同時に感情の気づきに救われながら書いている感じです。時々自分は世間に対してすごく押し付けがましいことをしているなあって思うんですよね。でも、“救い”という言葉が一番適切な気がしていて、お守りみたいに物語を書いています。
■人と人の間、役割の中で感じる「生きづらさ」を「生きやすさ」へ
――DRESS読者の方々をはじめ社会で生きる多くの人にとっても、あらゆる人間関係の摩擦やその日々でどういう選択をするかはひとつの悩みになっているかもしれません。
家や学校や会社、いろんなコミュニティの中で与えられた役割に苦しむ人もいれば、役割を与えられることで落ち着くという人もいると思うんです。ただ、その役割が大きな負担になったり、フェアじゃないと感じる瞬間が一番苦しいんですよね。あと、望んでいたはずなのに実際やってみたら思っていたものとは違ったとか……。そういう時に声をあげにくいことが生きづらさに繋がっているんじゃないかなって。
――親と子、恋人や夫婦、妻である自分や母である自分、こうあるべきという他者の声。たしかに、ひとりの人間である個人が役割の中で苦しむという場面は日々の中にあるものかもしれませんね。
役割を作ることも破ることも結局は自分にしかできない、だからこそ、人って常に変わり続けていていいものじゃないかと私は思っていて……。たとえば子どもがいる夫婦の中で、今までは家で子どもを見るいわゆる母親の役割をこなしてきたけど、今後は今父親がやっているような働く役割がやりたいとか。そのうち父親母親みたいな役割自体がなくなって、得意なことを分け合うようになるともっといいのかもしれない。固定概念の強い人に役割を強いられる辛さも分かるので、なるべく多くの人が自分の主義主張を共有できる環境であってほしいし、それを受け入れ合える柔軟な選択が取れる世界になってほしいなって。世の中への願いとしてはそんな気持ちがあります。
――人間関係の中で「生きづらさ」を「生きやすさ」に変えていくためには、どういったことが必要だと思いますか?
必ずしもではないけれど、コミュニケーションの量と理解というのはある程度比例するものだと思うんです。だから、さまざまな人間関係の中で「相手がこういうポジションだからできることはここまで」という線引きは少しもったいない気がしたり……。伝えることで関係性が強固なものになったり、フォローがしやすくなることってあると思うんですよね。
私自身が母とそういったことを実践してみて、「ここがウィークポイントなんだ」とか「ここは価値観が違うから折り合いをつけなきゃ」という新たな気づきもあって。それらが関係性の修復や再構築、ひいては「生きやすさ」につながったのかも? なんて思ったりもしています。どんな関係性においても「その人と一緒にいたい」という状況がある中では、互いに探り合って工夫する気持ちを持っていたい。同時にコミュニケーションって決して言葉だけではないとも思います。「全ては話さない」「伝えるよりも今は見守る」という形で関係性が良好になることもありますよね。対人関係の数だけそれぞれの選択があっていいのだと思っています。

紗倉まなプロフィール
1993年3月23日、千葉県生まれ。工業高等専門学校在学中の2012年にSODクリエイトの専属女優としてAVデビュー。15年にはスカパー! アダルト放送大賞で史上初の三冠を達成する。著書に瀬々敬久監督により映画化された初小説『最低。』、『凹凸』、エッセイ集『高専生だった私が出会った世界でたった一つの天職』、スタイルブック『MANA』がある。「ダ・ヴィンチニュース」で「働くおっぱい」、「withonline」で「紗倉まなのエロモテ課外授業」を連載中。










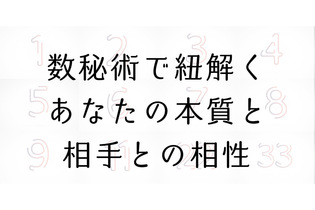










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。