涙の数だけ強くなれるとは限らない
急に涙がこぼれることがある。そういうシーンに出会うこともある。「泣く」という行為は、なんだかものすごく特別なもののように切り取られることが多い。けれど、その涙に意味を持たせてしまうことが、かえってその人から「泣く」ことを奪ってしまう……なんて大袈裟な話だろうか。エッセイスト・生湯葉シホが考える泣くことについて。

■牛乳パックを開いて泣いた日
「この姿勢がまずかったのかも」とSさんが言う。Zoom画面のなかで彼はリスみたいに両手を揃え、なにかを挟んで持つジェスチャーをしていた。「ここにクッキーサンドアイスがあるんですけど」と言いながら、Sさんは深夜、パソコンに向かってアイスにかぶりついていた日を再現する。
「そのアイス、最近はまってたから食べるの楽しみで取っておいてたんですよ。でも、夜中にお腹すいて冷蔵庫開けたらそれしかなくて、仕方ないから出すじゃないですか」
どんぐりを齧るようにクッキーサンドアイスを俊敏に食べながら、なんでこんなことに、とSさんは思ったという。このごろ仕事しかしていない。とにかく忙しくて、朝から晩までパソコンの前に座っている。唯一の楽しみだったはずのクッキーサンドアイスは、生きるための最低限の食事として、味すらよくわからないままで胃のなかに送り込まれている。「アイス食べてたら急に虚しさとか情けなさとか疲れがぜんぶきちゃって、なんか、気がついたらめちゃめちゃ泣きそうになってたんですよね……というかもはや泣いてたかも」とSさんは言った。
その話はオンライン会議の合間になされたほんの数分の雑談だったのだけれど、「ああ、あるなあ」と妙に印象に残っていた。漠然と溜め込んでいたしんどさがとつぜん沸点に達して、自分でも驚くようなタイミングでウワッと溢れそうになってしまう瞬間。
たとえば、私は飲み終えた牛乳パックを畳んでゴミ箱に入れようとしたとき、パックの裏に書かれた「リサイクルありがとう」の文字を見ていたら急にその“沸点”がきて、台所の床にしゃがんでぼろぼろ泣いてしまったことがある。
いま振り返ると、離婚が決まって気が滅入っていた時期だったというのは容易にわかる。けれど泣いたその瞬間まで、私は自分の気持ちが沸点に達しかけていることに気づいていなかった。
「リサイクルありがとう」はちょっと、びっくりするくらい心にきた。紙パックを畳むというひと手間、本当にささやかなひと手間を終えて目をやった先に、二段組の極小フォントで印字されていた文字。いままでも絶対に見たことはあったはずなのに、そのときばかりは釘づけになった。こちらこそありがとう、と心から思い、後日、思わず明治乳業にお礼のメールを出したほどだ。読んでくださったかわからないけれど、急に「あなたのところの牛乳に救われました」という怖い長文がきて担当者はびっくりしたと思う。
■「なんで泣くの?」「わかんないです」
クッキーサンドアイスも「リサイクルありがとう」も、当然だけれどそれ自体になにか大きな意味や啓示的なものがあるわけではない。ただ共通しているのは、生活のなかのささやかな動作がきっかけになって、自分でも予期していなかった涙のスイッチが入ってしまったという結果そのものだ。
なんでこんなとこで? と思うようなシーンで突然涙があふれてしまう、という出来事は生活のなかにありふれている。ある友人は、恋人と同棲を解消してからしばらくして、長らくゴミの日に出せていなかった段ボール箱の山を畳んでいるときに急にそのシーンがきたという。
「段ボール畳むのってなんかさみしいな、めんどいなって思いながらビニールひもを切ってたら急に泣けてきて、いま泣いたら“同棲解消の引っ越しがつらくて泣いている人”になるなと思って必死にこらえたんだよね。そのときまとめてたのは、ふつうにひとりで買ったAmazonの段ボールだったんだけど、これは勘違いされるな、と思って」
誰に勘違いされるんだと思わず笑ってしまったけれど、彼女の言っていることはよくわかる。泣くという行為には泣くに至るなりの明確な理由があって、その理由を満たしたケースにおいてのみ涙は流れる、と思っている人もたしかにいる。
前後の文脈がはっきりしていないシーンで突然泣く、という行為は、その場にいる相手を戸惑わせる。「え、なんで泣くの」と人に言われたことが自分にも数えきれないほどあるけれど、言語化することのできない漠然とした疲れやしんどさ、悲しさが気がついたら涙という予期せぬアウトプットになることは実際によくある。そうなったらもう、泣いている本人にもその理由はよくわからない。
私自身は涙もろいほうで、昔から個人面談やサシ飲みのような“人とじっくりと話す”というシチュエーションにすごく弱い。なんだかわからないけれど、自分のことを話しているとある瞬間にスイッチが入ってしまって、急にぼろぼろと泣けてくるのだ。そのスイッチが「箸置きの紙を使って折っていたミニ鶴が完成した」みたいな意味のわからない瞬間に押されてしまうことがあると、相手は当然混乱する。
迷惑をかけるのでその体質を直したい、と長年思っていたのだけれど、去年、なんの気なしに読んでいた記事でなるほどと思ったことがあった。それはライターのあかしゆかさんが書かれた、内科医の方に日々感じている悩みを相談しつつその解決のヒントを探るという趣旨の連載記事。よく泣いてしまうことで相手に気を使わせ、迷惑をかけている気がするから直したい、というあかしさんの悩み(同じだ!)に対し、医師である鈴木裕介さんは
と答えている。とてもシンプルな回答だけど、強い納得感があった。そうだよな、別に好きで出てる症状じゃないんだよな、と思い、それ以来泣いているときに「なんで泣いてるの?」と人にぎょっとされることがあっても、「わかんないです」と素直に答えるようになった。
■「泣きたいときは泣けばいい」と言われても
こうして考えてみると、私たちが泣くことをできるだけ避けたり、それを人に見られないよう取り繕ったりしてしまう背景には、涙に過剰な意味づけをしがちな他者の視線の存在があるという気がする。ここで言う“他者”には、泣いている自分を見て、なぜ泣いているんだろうと殊更に理由を追及してしまう自分自身もふくまれる。
「泣きたいときは泣けばいい」というやさしい言葉があるけれど、いざ涙が出そうになったときにその言葉を思い出して泣くことができたという記憶は、私自身のケースをふり返る限りあまり多くない(余談だけれど、「泣きたいときは泣けばいい」という言葉を人にあまりにも簡単にかける人は、本気で泣くことがいかに人の体力を奪うかを知らないんじゃないか。もちろん個人差はあるとは思うけれど、大泣きをすると目は腫れるし肌も荒れる。体のふだん使わない筋肉を使うからなのか、あとになって予想外の体の部位が痛くなることもある。実際に寝たまま泣き続けてすべての涙が耳のなかに流れ、中耳炎になったことがある人を知っている)。
ここまで書いてきたとおり、ほんとうに些細なことがきっかけで涙は出そうになるものだけれど、そのタイミングが仕事や飲み会といったオフィシャルな場でやってきたとき、「職場で泣くなんてまわりを心配させる」とか「盛り上がってる空気に水を差してしまう」とぐっとこらえる人も少なくないんじゃないだろうか。

■涙の数だけ強くなれるとは限らない
すこし前に仕事で会った方が、こんな話をしてくれた。
彼は昨年末に親族を病気で亡くしたばかりだったのだけれど、彼自身が新型コロナウイルスの濃厚接触者と認定されてしまい、病室に顔を出せないままで親族と別れることになってしまったのだという。仕事に復帰したあと、そんな話をオンライン会議の場でクライアントにふとこぼしたら、まったくの他人であるはずのクライアントが「それは……」と言葉を詰まらせて泣きはじめたというのだ。泣きはじめた相手を見て、ずっとこらえていたけれど自分も思わず大泣きしてしまった、と彼は言っていた。たしかに、目の前で泣いている人を見る以上に「泣いてもいい」が説得力を持って伝わることはないだろうと思った。
泣くことで消耗する体を知っているから、安易に「いつでも泣いていいんだよ」とは言いたくない。けれど私としては、それがたとえ人前であろうがちょっと唐突に思えるタイミングであろうが、泣きたい気分になった人がその場でためらわずに泣ける社会のほうが絶対いいよな、と思っている。
何度でも言うように泣きたいシーンは急にくる(こともある)ので、目の前に泣きそうになっている人がいても、それにいつでも気づけるわけではない。ただ、そういう場面にたまたま出くわしたときは、「なんで」とか「泣かないで」とか言わずにティッシュだけ差し出すようにしている。泣きやんでください、というメッセージにできるだけ思われないように。つられて泣きそうになったらそのまま泣いてしまう。泣きたい理由やきっかけなんて、涙もろい自分にとってはそこら中に溢れているので特別なことではない。視線がストレスにならないように、あとはもう背景のようにぼんやりしている。
その態度がいいことなのか、相手にとってうれしいことなのかはわからない。けれど、すぐに泣く私のような人間がそれを開示し、少なくとも自分の前では急に泣いてもびっくりしませんよ、というのを伝えていくのは意味のあることなのではないか。よく泣く人間はきっと涙をめぐる過剰な意味づけに晒されてきた経験が多く、大変だろうなと思う。だからいまのところは、「涙の数だけ強くなれる」ってあれなんなんでしょうね、泣くと疲れますよね、という顔で、ティッシュを差し出し続けていたい。











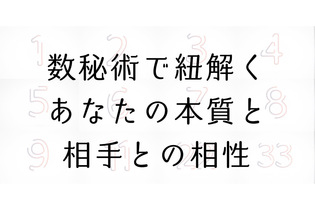










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。