
禁酒してみてわかったこと(死ぬまでにはしらふになりたい)
本稿を書いていた最中の生湯葉さんから「今日もしらふなんですけど発見がものすごくあってすごい。まず飲まないと夜と朝がシームレスに繋がってることを理解できる(飲むと気絶するように寝てしまうので気がついたら夜が朝になっている)し、急に死にたい……とか思わない。禁酒は本当にすごいですよ!!」と連絡が届きました。担当編集より。

先日、町田康の『しらふで生きる』というエッセイ本を読んだ。大酒飲みとして知られている作家の町田康が30年間毎日飲み続けた酒を突如やめるという内容なのだけれど、これがとてもおもしろかった。
町田さんは、健康上の問題が起きたわけでも酒が嫌いになったわけでもないのに、数年前の年末から一切酒を飲んでいないという。その理由がなんだかものすごいので、ざっくりと背景が伝わりそうな箇所を引用する。
気が狂っていたので、酒をやめる、などという正気の沙汰とは思えない判断をした。”
“たとえて言うなら、自ら悟りを開きたいと思って仏門に入り修行に励んでいるのではなく、一時の気の迷いで出家をして、そのまま一年くらい経ってしまった、という状態に近いだろう。”
――町田康『しらふで生きる』より
正直、最初は「町田さんが酒をやめたら誰が代わりに飲むと思ってんだ、裏切りやがって」という謎の苛立ちを抱いていたのだけど、エッセイを読み進めるうちに「な~んだ、気が狂ってたんならしょうがないよね」とあっさり溜飲が下がった。と、同時に、「私も気、狂わせてみよっかな、フフ」という気持ちに一瞬だけなり、なにをばかなことを、と気を確かにしてから麦焼酎のロックを2杯飲んで眠った。
■もしも「本当に」禁酒してみたとしたら?
ところが翌日、自分の頭のなかから「本当に禁酒してみたら?」という考えが消えていないことに私は動揺した。
私はいわゆる大酒飲みではない。のだけど、365日のうちのだいたい363日くらいは酒を飲んでいて、親知らずを抜いて激痛に襲われているとか、手術をした当日だとか、よっぽどの理由がない限りはアルコールを抜いたことがなかった 。
大した量を飲まないので酩酊するようなことはほとんどないのだけれど、それでもときどきは飲みすぎてしまって、知らない会社の同僚たちのバースデーパーティーの二次会のカラオケに参加したり(あとから動画を見たら「愛をこめて花束を」で一緒に泣いていた)、ミックスバーで仲良くなった店員さんとすしざんまいでオールし、知らない人のチェキにざんまいポーズで写ったりしていたから 、翌日に記憶が戻るたびに酒をやめたほうがいいんじゃないかとチラッと思ったりはした。でもそんな考えが半日以上持ったことは一度もなかったし、「吐いたりして迷惑もかけてないんだからまあいいじゃん」という強気の姿勢でいた。
けれどずっと気にかけていたことはあって、それは酒を飲むとなにごとにも感動しやすくなってしまう、という問題だった。たとえばビールを飲みながら見た映画はしらふで見た映画よりもなんとなく自分のなかでの評価が上がってしまう傾向があったし、酒を飲んでから街を歩くとやたらと景色が輝き、カラオケ館の看板とか蝉の死骸とか、目に映るすべてのことがメッセージに思えてくるのも怖かった。
町田康風に言えば、酒を飲んでいる世界が“正気”であり、しらふの世界こそ“狂気”なのだろうけど 、本当にこっちサイドが正気でいいのか、じゃあ体質的にアルコールが飲めない人は常に狂気のなかでこのやばい世界に対峙しているのか、自分だけが飲酒という魔法に死ぬまでかかり続けていてもいいのか、そんなのってずるくないか? という疑問が次々に湧いてきて、よし、一旦もう禁酒してみよう、やれるところまで試してみよう、と思い立ったのだった。
■禁酒1日~3日目:酒蔵見学の夢を見て泣く
禁酒を思い立ってから1日目、友人から「飲みたいんだけど今月いつ空いてる?」とLINEが入った。流れるように日程を確認しようとして、お~っと騙されないぞ 、と思う。友人に禁酒の旨を伝えると、「今月の後半までは持たないと思うから後半にしよう」と悪い返信がきた。夜になると当然のように飲みたい気持ちが湧いてきたものの、きょう我慢しないとそもそも禁酒というもの自体がはじめからなかった幻のイベントになってしまうと思い、必死に耐えて夜10時に寝た。
つらかったのは翌日だった。朝起きた時点でもう飲みたい。ただ、仕事に集中しているときは酒のことを忘れられるのを経験として知っていたので、酒のことを忘れるために泣く泣く仕事をした。原稿を書き終えて顔を上げると日付が変わっていて、うわラッキーじゃんと思う。いつもならここで我慢できずに金麦を開けてしまうところなのだけれど、この日は幸いもう眠かったので、強烈な飲みたさに襲われる前に寝ることにした。
3日目、目が覚めると部屋の窓から朝焼けが見えて驚く。仕事で徹夜をしたあとか、ひとりで飲み明かしたあとにしか見たことのなかった朝焼けというものを起床後すぐに見ていることがあまりにも信じがたく、そうかこれが噂に聞く“狂気”の世界か、と怖くなって二度寝した。
眠っていたら夢を見た。父とふたりで酒蔵見学に行き、試飲コーナーでしこたま日本酒を飲む夢だった。じつは父は長年の飲酒がたたり 1年ほど前から食道がんの闘病をしているので、実際にはほとんど酒が飲めない。手術前、主治医の先生に言われた「お父さんはこれまで何十年も食道の粘膜を痛めつけてきたんですよ、もうこれからは痛んだ粘膜とともに生きていくしかないんですよ」という言葉の恐ろしさは私もよく覚えていた。
ふたたび起きるとぼろぼろ泣いていた。それは闘病中の父を不憫に思って、とか楽しかった父との晩酌を思い出して、とかではなく、この期に及んで「飲みてえな」と感じている自分の浅ましさがつらくなったからだった。
■禁酒4日目:しらふで初めて考える
そもそも、私はどうしてこんなに酒を飲みたいんだろう?
飲酒が習慣になったのは22歳くらいのときからだと記憶している。いろいろあって酒を飲まないと人としゃべれなかった時期があり、当時は気を大きくするために飲んでいた。幸い、私は体質的にアルコールに強くなく、ビールでもサワーでも4杯ほど飲むと泥酔して寝てしまうので、まともに人としゃべることができる2~3杯程度で抑えていた。しかしその後またもやいろいろあって自我が育ち、もしかして自分はもう酒を飲まなくても平気なのでは、と気づいたころには、しゃべるためではなく“酒を飲むため”に酒を飲むようになっていた。
飲むために飲むようになると、もうしゃべるとかしゃべらないとか人がいる・いないは関係なくなり、“酒と私”はセットの存在になる。そうするともう、友人知人も飲酒する私を場の背景として扱うようになるので、背景として常に酒を持ち続けていなければという妙な気負いがこちらにも生まれ、ますますアルコールから離れられなくなりいまに至る(みなさんに私の言葉はまだ通じていますよね? )。
禁酒を始めてから4日目に目を覚ましたとき、体は長年の酒の負債から解き放たれてしばらく経ったせいかすっきりとしていて、顔もむくんでおらず、眠気も少なかった。飲酒しているときは、気絶して目を開けたらなぜか翌日になっているというカイジの一日外出みたいなシステムで目を覚ましていたのに、酒を飲まないと、夜がしだいに朝になってゆくという自然の摂理がよくわかった。試しにそのまま仕事に取りかかってみると、自分のいまやるべきことに集中できて異様なほど捗る。気になっていたアニメを見ても本を読んでみてもその内容が妙な熱を伴わずフラットに頭に入ってくるので、ここはおもしろい、とかここはつまらない、というのを明瞭に感じた。一連の変化を振り返り、「ひょっとして心身ともに健康になりつつあるのでは」と私は感激していた。
そしてふと思う。いまこのコンディションで酒を飲んだら、最高においしいんじゃないか?
■飲酒ふたたび
その日の夜、戸棚の高いところにしまっていたワンカップ大関を取り出してきて飲みながら、禁酒に成功した4日間 のことを考えていた。しらふの状態で見た世界ではすべてのものごとの輪郭がくっきりとしており、美しいものは美しいまま、つらいことはつらいことのまま、そのどちらでもないものはそのままの姿でただそこにあった。そうか、酒を飲まない人が見ていた景色はあれだったのかと、常にしらふでいる人たちに対して強い尊敬の念が湧いた。酒を飲まないままで社会に対峙している人はほんとうに、ほんとうにえらいと思った。
飲酒というのはたぶん、眼鏡を外してぼやけた街の灯りを見ながらきれいだきれいだとはしゃぐのに似ている。しらふでこの世を見つめ続ける勇気のない自分のことを卑怯者だと思うし、できるだけ早く、せめて死ぬまでにはしらふでい続けることに慣れたい、と強く思う。ところで、友人に「飲もっか」とLINEを返してから4日間、既読無視され続けている 。
※ この記事は2020年2月14日に公開されたものです。










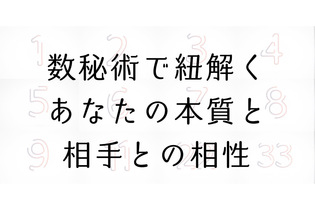










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。