恋人の元カノたちはみんな発光している
恋人の元恋人たちは、眩い輝きをまとって美しい幻想として私の前に現れる。現実に生きる私は幻に存在する彼女たちにかなわない。生湯葉シホによる嫉妬という感情がもたらすものへのエッセイです。ああもう馬鹿馬鹿しいって、自分でも思ってる。

友人と並んで歩いていたとき、「シホさんって背何センチ?」と急に聞かれた。150だよと言うと彼女はちょっとホッとした顔になって、「よかった、152くらいかなって思ってた」と笑った。152だと困るの? と聞くと、「ほんとくだらないんだけど」という前置きのあとに、こんな話をしてくれた。
■152.5センチという数字に宿る魔力
彼女は先日彼氏と同棲を始めたばかりだったのだけれど、彼が前の家から持ってきた荷物のひとつに体重計があった。ある日、彼女がリビングに置かれた体重計になにげなく乗ってみると、「170.5cm/25歳」という文字が表示された。それは彼氏の身長だったから、自分のデータも新しく入れようと思って「設定」のボタンを押した。
するとそこには、彼氏も含めてふたり分のデータがすでに入っていた。もうひとつのデータは「152.5cm/25歳」だった。
家に帰ってきた彼氏に「152.5センチの女の人と付き合ってたことがある?」とアキネイターみたいな質問をぶつけると、彼は「姉貴だよ」と答えたという。けれど彼女は、彼氏のお姉さんが成人してから一度も彼と住んだことがないのを知っていた。
その日を境に、彼女は152.5センチという文字を見るだけで彼の元恋人の姿かたちを想像して自動的に腹が立つようになってしまった。「もしもシホさんに152.5センチの知り合いがいても私には絶対に会わせないで、自分がなにをするかわからないから」と言われたときは笑ってしまったけど、でも、私にもその感覚はよくわかる。
■早く恋人の元カノになりたい
むかし、恋人が直前まで付き合っていた人の名前が私と同じ「シホ」だと知ったことがある。Facebookを見ていてその事実に気づいたとき、貧血を起こした。
もちろん名前の一致は単なる偶然で、恋人の話を聞いていても、前の恋人に未練があって同じ名前の私と付き合った……ということではないとわかっていた。それでも、彼に名前を呼ばれるたびに自分の心がめちゃくちゃに歪みそうになってしまうのがつらくて、途中からは名前と関係のないあだ名で呼んでもらっていた。
小説家の角田光代が書いた「恋人の前の彼女」についてのエッセイを読んだのは、ちょうどそのころだったと思う。正確な出典を思い出せなくて申し訳ないのだけれど、角田さんはたしかその文章のなかで、(相手が自分のよく知っている人物でない限り)人の元恋人は常に幻だから、幻の美しさにはどうしても敵わないことが悔しいのだと書いていた。
その文章を読んだ途端、記憶の奥底に眠っていた無数の「恋人の元カノ」のエピソードが美しい幻のかたちを伴ってゆらゆらと立ちのぼってきた。ロックフェスにむかしの彼女と一緒に行ったとき、最後のアーティストの演奏をなぜかステージの端に腰かけてふたりで聴いたと話してくれたこと(20年以上前の話で、当時のフェスはそのくらい自由だったのだとその人は言った)。彼女との出会いを聞いたら、「なんか歩いてて会った」とはにかみながら言われたこと。
幻のなかの彼女たちの姿はどれも恐ろしいほどに美しくきらきらしていて、行ったこともないロックフェスのステージの背景では夕日が沈みかけており、恋人とその彼女はゆるやかに手を繋ぎながらその様子を見ている。後ろではオアシスがwhateverを演奏している(最後のアーティストが誰だったかなんて知らないけれど、そんなシーン絶対whateverに決まってるのだ)。ふたりはときどき音楽に体を揺らしながら、自分たちが出会った留学先のロンドンの小道の朝もやを思い出している(ロンドン? 知らない、でもそうなのだ)。
幻には実体がない。恋人のむかしの彼女たちはなぜかみんな発光しているから、顔は見ようと思っても見られない。彼女たちはみんな私が絶対に着ないような服が似合って、私の行ったことのない街に住んでいて、私のように急に泣いて恋人をびびらせたりしない。身長は152.5センチかもしれない。幻は怪物みたいに肥大化していく。
角田さんのそのエッセイの結論は、「いつか恋人と別れて、私も早く彼の『前の恋人』の幻になりたい」だったと記憶している。わ、わかりすぎる。私も当時、嫉妬で狂いそうになる日が続くと、いつか彼と別れたら自分の名前を憎まなくてもいい日がくるはずだからその日までがんばろう、と歪んだポジティブさでつらさを乗り越えていたのだ。あれから5年くらい経って、私は無事に自分の名前を人に呼ばれてもなにも感じなくなることができた。

■自分が並みの人間であることの苦しみ
嫉妬という感情はつくづく馬鹿馬鹿しい。私だってほんとうは、恋人の元彼女たちが発光などしないふつうの人間であるとわかっている。というか、いちど同じ相手を好きになっている以上、音楽の好みや趣味や性格が自分とある程度似ている可能性すらある。だとすれば、彼女たちが恋人の元恋人でさえなければ、いい友人になれていたかもしれない。そんな絶好の機会を、嫉妬という感情に奪われてしまうことが腹立たしい。
哲学者のロラン・バルトは名著『恋愛のディスクール・断章』のなかで「嫉妬するわたしは四度苦しむ」と書いている。彼によると、嫉妬する人はまず嫉妬そのものに苦しみ、嫉妬している自分を責めて苦しみ、自分の嫉妬が恋人を傷つけるのをおそれて苦しみ、嫉妬という卑俗な感情に負けたことに苦しむのだという。そしてそれはつまり、「自分が並みの人間であること」が苦しいのだと。バルトはものすごいことを言う。私はこれを読んで5回傷ついてしまった。
嫉妬なんてしたくない、理不尽な理由で人のことを一方的に憎んだり神聖化したりしたくないという気持ちは、たしかに「自分はそんなことをするような並みの人間でいたくない」という気持ちと強く結びついている。恥ずかしいけれど、自分はどんな人ともできるだけフラットに接したい、好きな人がかつて好きだった人のことも好きでありたい、そんなことに精神のバランスを崩されるような人間でいたくないというエゴが私のなかには確実にある。
けれど最近、肩こりがひどくて整体に行ったら、整体師さんにこんなことを言われた。
「本当は心も体も一切歪みのないバランスのいい状態というのがベストなんですけど、人間がそうなれるのって死んでるときなんですよね」。
このエゴを突き詰めた先にあるのが死なのかもしれないと考えると、すこしだけ怖い。










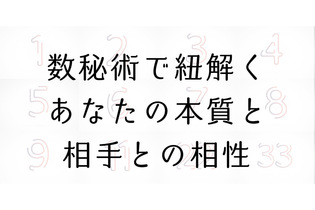










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。