「保護フォルダ」が命より大切だった頃 【平成女子のインターネット回想録 #1】
実家の私の部屋はもう物置扱いで見る影もないけれど、帰省するたびにひとつだけ「まだちゃんとそこにあるか」を確認して、そっとしまうものがある。勉強机の一番上の引き出しにある、水色のガラケーである。

■パカパカできるだけの箱になってしまったガラケー
遡ること約十年前。中学生にしてすでに自宅のパソコンで毎日ネットサーフィンしていた私に、親はケータイをなかなか買い与えてくれなかった。
「パソコンでメールできるんだからいいでしょ」
「ネットもパソコンの方が画面が大きくていいじゃない」
その通りなのだが、同級生の“みんな”と同じものを持って、同じようにメールしたくて、私はずいぶん駄々をこねた。
そんなこんなで、折りたたみ式でカメラがついたいわゆる「ガラケー」を手に入れたのは、高校にあがってから。
飛び上がって喜んで、フランス語のフレーズの入った、オシャレぶったメアドを作った。親は「パケ・ホーダイプラン」には入れてくれなかったが、メールだけは送り放題のプランだったから、とにかくたくさんメールした。
そんな思い出のガラケーは、実家の引き出しにもう6年ほど放置されている。充電器もどこに行ったかわからないし、充電できたとしてもバッテリーがもうだめになっているだろう。
ただのパカパカできる箱である。
そんなガラクタ同然の端末の存在を、なぜだか私は気にかけている。
当時想いを寄せていた人とのはずかしいメールの記憶が、端末と一緒に残ったままだからだ。
■命より大切な「保護フォルダ」
高校生活の後半、はっきりと好きな人がいた。吹奏楽部の先輩である。
彼はもう大学生だったが、夏のコンクールの手伝いに高校に出入りしていた。全然モテるような容姿の人ではないし、私も最初はなんとも思っていなかった。
しかし練習後の帰り道で話したり、同級生も交えて一緒にご飯に行ったりしているうちに、「なんかこの人面白いな」と気付き、コロッと好きになってしまった。
年上というだけで輝いて見えた時期だったんだろう(そう思いたい)。

メールアドレスを手に入れるのは難しくなかった。ホールでの練習など校外に出ることがあると「連絡先」として部活関係者のメアドが紙で回ってくる。
その人のメアドは名前も誕生日も英単語も何も入ってない、そっけない英数字の羅列だった。それもまた大人っぽくてカッコよかった。
問題は、メールするきっかけを用意することだ。苦心して、差し入れでいただいたお菓子(アルフォート)のお礼を送ることにした。
「いつもありがとうございます、チョコおいしかったです」
何を今更、という内容である。いろいろ推敲したが、これしか書けなかった。「あなたに気がありますよ」というのがバレバレのメールだ。
絵文字も顔文字も使わず、えいや!で送信ボタンを押した。押してから2秒で後悔した。そのまま寝込んでやろうとベッドにうつ伏せになったが、気になって何度も携帯を見てしまう。
返事は1時間くらいで来た。「お、わざわざありがとう」だけだった。でも嬉しくて、しばらく自分の部屋でひとりでにやにやしていた。
ガラケーメールは1000通までしか保存できなかった。と記憶している。
だから大事なやりとりは、とりあえず保護をかけないと親からの「今日ごはんいる?」のような有象無象のメールにどんどん流されて、いつのまにか消えてしまう。
だからこの「お、わざわざありがとう」も保護フォルダに入った。

それからも甲斐甲斐しく私はメールをした。
「ところで、先輩は今日は何を食べたんですか」
どうでもいいことだが、訊くと「親子丼です」と写真で食べたものが送られてくる。毎回妙に素っ気なくて、それだけ?と思いつつ、それでも返信してくれるのが嬉しくて、楽しかった。
そのメールも保護フォルダに入った。
毎日、返信を待ちわびて端末を握りしめ、無意味に「センター問い合わせ」を繰り返して、そのうち諦めて寝て、朝起きたら届いている。そんなメールたちだから、可愛くてしかたない。
そのうち「おはようございます」と送ったら、「おはよう」と戻ってくるようになった。調子に乗ってきた私は、メール一通に入れ込む話題を少しずつ増やしていった。
先輩も大学の話、バイトの話、予定している旅行の話などをしてくれた。
嬉しかった。
自分から出した話題に相手が反応してくれることも、相手が新しい話題を出してくれることも、何もかも嬉しかったから、すべての話題に丁寧に触れるようにメールを構成した。そうするとものすごい長文になる。
そして返ってきたすべてのメールをいちいち、保護フォルダに放り込んだ。
そんなやりとりは高2の秋頃から高3の春まで毎日一往復程度続いたが、直接好意を伝えるタイミングがなく、先輩には大学生の彼女ができて、あっけなく終わった。
先輩は私の気持ちにもちろん気づいていただろうに……。ショックだった。
そんなわけで、私の「保護フォルダ」に新しいメールが増えることはなくなった。
■スマホで「あのね」「なに」「なんでもない」ができるようになった
時が経ち、私は大学生になった。
iPhoneを手に入れ、破れた恋の思い出が詰まったガラケーは引き出しにしまい込んだ。
メールを送ることも、センター問い合わせをすることもなくなった。
そして彼氏ができた。
彼との連絡手段は、当時大学内で広まり始めていた「LINE」だった。
メールがしっかり書き込んで送るお手紙としたら、LINEは気楽なおしゃべりだ。
「メールみたいに振られた話題に一段落ずつ返事しなくていいのか?」
「スタンプだけ送って変じゃないか?」
送った相手の顔がわかるせいだろうか。気軽な言葉で不快にさせていないか、最初はいちいち不安になっていた。
でもすぐに、話しかけるようにメッセージを投げ込むことに抵抗がなくなって、
「あのね」
「なに」
「なんでもない」
毛づくろいするみたいに送るのが平気になっていった。
今日のゼミが散々だったこと、バイトのシフトのこと、読んだ本の話、見た映画の話。
それぞれを組み合わせて長い文章を書いていたのがメールだとすれば、バラバラに一つずつやりとりするのがLINE。
一個一個のやりとりが軽くなったことで、ガラケーの頃のように、端末を握りしめて、返事が来るのを待つことも少なくなった。
返事がもらえないなら「今なにしてるのー?」とスタンプと一緒に送ればいいのだ。
ガラケーも先輩も、もうすっかり過去になってしまった。
■もしもあのときLINEがあったら
大人になった今、思う。
もしも高校生のあのときLINEがあったら。
私は先輩に「好きです」と送っていたような気がする。
敗因はメールを丁寧に書いてやりとりすること自体に夢中になってしまったことにある。つくづく気持ち悪い妄想だが、成り行きでお付き合いできていたかもしれない。
あの頃に戻りたいとは全然思わない。
LINEの気軽さは最高だし、スマホがあれば何でもできる。
でもガラケーを握りしめて返事を待っていた高校生の淡い思い出も、それはそれで愛おしい。
水色のガラケーに残っているのは私の無念の集大成である。
回り道して、メール一通一通に一喜一憂して。馬鹿みたいだ。
今だからこそ笑えるけれど、そのまま処分してしまったら当時の自分が絶対に浮かばれない。
今度実家に帰ったら、きっとまた勉強机の一番上の引き出しをそっと開けてしまうのだろう。









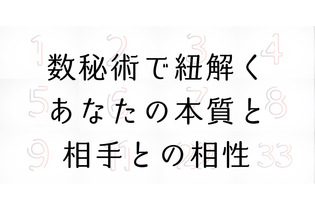










平成の大部分の時間はインターネットに溶かしました