
「LGBT」なんて言葉がなかった時代。ゲイの男性と結婚した中村うさぎが振り返る、愛情に満ちた20年
ゲイの男性と「友情婚」をした作家・中村うさぎさん。ふたりの間に流れていたのは心温まるような愛情だった。まだLGBTという言葉も浸透していなかった20年前、うさぎさんはどうしてゲイとの友情婚を選んだのか。その当時から現在までの歩みとは。

世間が押し付ける「常識」や「普通」を跳ねのけ、自らの欲求に従い、まっすぐに突き進んできた作家・中村うさぎさん。
買い物依存症、整形手術、デリヘル勤務など、自身の体験を赤裸々に綴った著書は毎回大きな話題を呼び、彼女を唯一無二の存在へと押し上げた。
そんなうさぎさんが現在の夫と結婚したのは、いまから約20年前。相手となったのは、香港からやって来たゲイの男性・Kさんだった。
「私にとっての幸せは、昨日と同じ今日が来て、今日と同じ明日が来ること」
■仲良しのゲイを助けるため、その場の勢いで決めた結婚

Kさんと出会った当時、うさぎさんはアラフォー。ひとり目の夫との結婚生活に終止符を打ち、「鉄の処女期」に入っていた時期だ。
「ひとり目の夫と離婚した頃で、男にはこりごりしていた時期だったんです。もう恋愛なんてしなくていいやと思っていた。だから、遊び相手はもっぱら女かゲイの子たちで。しょっちゅう新宿二丁目に通っては、飲み明かしていたんです。そこで出会ったのが、今のパートナー。当時、彼はまだ学生だったので暇人で、私みたいな自由業をしている人からすると格好の遊び相手だったんですね。いつ呼び出しても来てくれるし。それで急激に仲良くなっていったんです」
そんなKさんも学校を卒業するタイミングで学生ビザが切れ、母国へ帰らなければならなくなってしまった。けれど、日本で暮らしたいという気持ちが強かった彼は、うさぎさんに相談を持ちかけたという。
「彼の母国である香港はすごく小さな国で、ゲイ活動もおおっぴらにはできない。それに比べて日本にはゲイタウンがあるし、彼には付き合っている人もいたんですね。だから、このまま香港には帰りたくない、と。それで、入国管理局に連れて行って、ワーキングビザの申請を手伝ってあげようと思ったんです」
異国の地で困っている友人を助けてあげよう。うさぎさんの胸中にあったのは、小さな善意だった。しかし、それがなぜ「結婚」というカタチになったのか。
「そこにいた担当者のオヤジがすごく態度の悪い人で。『何の技量もない香港人に対していちいちワーキングビザを出していたら、日本は移民だらけになるでしょ』なんて言うんですよ。もう頭にきちゃって。『じゃあ、どうすれば良いんですか!』と問い詰めたら、『日本人の女性と結婚でもすれば良いんじゃないですか』なんて言うんです。それで私も、『じゃあ、そうします!』って啖呵を切ってその場を出てしまって」
売り言葉に買い言葉。頭に血がのぼったうさぎさんは、Kさんを連れてその場を飛び出した。そこで「本当に結婚する?」と確認したところ、Kさんは喜んでくれた。
「もう二度とノンケの男と結婚するつもりもなかったですし、ゲイと結婚したってなにも困らなかったんです。そしたら彼も、『なにも知らない女性を騙して結婚することはできないけれど、すべてを理解してくれているあなたとだったら大歓迎です』と言ってくれて。それで、彼と“友情婚”をすることになったんです」
■お互いに恋愛は自由。しかし、それが彼を傷つけることに

夫婦になったとはいえ、その関係性はあくまでも友だち。だから最初は、別居生活を送っていたという。けれど、Kさんが体調を崩してしまったとき、一緒に住むことでお互いに支え合うこともできると思い至り、そこから同居生活をスタートさせた。
一緒に住むにあたり、ルールも決めた。それは、「お互いの恋愛に口を出さないこと」と「セックスを家に持ち込まないこと」のふたつ。以降、夫婦としての生活をしつつも、外で自由に恋愛を謳歌するという生活が始まった。
けれど、ホストにハマり続けたうさぎさんの姿を見て、ある日Kさんが想いを吐露した。
「私が男に夢中になっている姿を見せたことがなかったから、すごくビックリしていたみたい。『絶対に金目当てだよ』なんて注意もしてくるようになったんだけど。でも、“お互いの恋愛に口を出さない”ってルールを決めていたから、私も彼の言葉には耳を貸さなかったんです。そしたらある夜、彼が泣いたんです」
ホストにハマるうさぎさんを見て、どうしてKさんは泣いたのか。その理由を問いただしたところ、彼の口からこぼれたのは、「あなたはもう私が必要じゃないのね」という、孤独感に打ちひしがれる言葉だった。
「一度目の結婚がダメになった理由が、“相手に必要とされていない”と感じたからだったんです。ふたりでいるのに孤独を感じる状況というのは、ひとりぼっちでいるよりもはるかにつらい。そんな状況がすごく嫌だったのに、今度は私が相手にそれを感じさせてしまっている。それに気付かされて、すごく反省しました。でもまあ、その後もホストには行っていたんですけどね(笑)」
■「夫は私の人生の重し。彼のおかげで、正気でいられる」
うさぎさんがKさんと結婚したのは、彼が日本に滞在するための“救済措置”だった側面が強い。それを叶えてあげた以上、他に望まれることもないだろう。うさぎさんはそう思っていた。
しかしながら、Kさんはそうではなかった。利害関係だけでつながっているのではなく、いつしか親愛の情が芽生えていたのだ。
彼のなかに大きな感情が芽生えていることを知ったのは、うさぎさんが税務署と揉めていた頃。住民税を滞納していた彼女は、Kさんと一緒に税務署に呼び出されていた。
「そこでいろいろ怒られちゃって。その帰り道、彼に謝ったんです。普通の女と結婚していたら、こんな厄介事に巻き込まれなかったかもしれないねって。そしたら彼がこう言ったの。『あなたがどう思って結婚してくれたのかは知らない。だけど私は、婚姻届にハンコを押すとき、これを押したら、この人の人生を半分背負うことになるんだなって思ったんだよ』って」
日本に滞在するためだけに結婚したのではない。彼の胸の内を知り、うさぎさんはこれまでの自分の態度を振り返ったという。そして、Kさんは、うさぎさんへの愛情をこう表現した。
この言葉は、うさぎさんの胸に響いた。そしてうさぎさんは目を細めながら、Kさんのことを「重しのような人だ」と評する。
「結婚相手って、“重荷”でしかないと思っていたんです。自由に生きたいのに、あれこれ制限をかけられてしまう。でも、Kは重荷ではなく、“重し”。ほっといたらどこかに飛んでいきそうな私を、ある程度のところに留めてくれている。彼のおかげで、私は正気を保っていられるんだと思うんです」
■はみ出す者に対する差別はなくならない。それでも……
うさぎさんとKさんが結婚した20年前。その当時はまだLGBTという言葉も浸透しておらず、ましてや、ゲイと友情婚をする女性の存在もなかった。
それから20年。時代は変わり、パートナーシップのカタチも大きく変革した。しかしながら、はみ出すような生き方をする人たちに対して、SNSなどではそれを非難する声がいまだやまない。
「時代は変わったなんて言われているけれど、私たちが思うほど、社会は多様化を許していないんだと思うんです。LGBTについてもこれだけ運動が活発化してきていても、こないだの『新潮45』の件みたいに、誰かが差別的な発言をするとそれを封じ込めようとする。だけど、本当に怖いのは、表面化されなくなった差別だと思うんです」
頭ごなしに否定するだけでは、「差別」はなくならない。水面下に鳴りを潜めた差別心は、さらにどす黒い感情へと変質してしまう危険性すら孕んでいる。
「まだ『オカマなんて気持ち悪いな』って発言があるほうがマシ。でも、それを言っちゃいけないという風潮があるから、言わないんだけど、心の奥底では思っている。それが欲求不満になって、やがては怒りとか憎しみに変わっていく。だからこそみんな、匿名のSNSで鬱憤を晴らすんだと思うんです」

長年、人間というものを見つめ続けてきたうさぎさん。そこで見えてきたのは、「人は誰しもマジョリティになりたがる」という本質的な弱さだ。
「人間っていうのは、ある程度の“規格”を求めてしまいがち。『男とはこうあるべき』『女とはこうあるべき』『結婚とはこうあるべき』っていうフレームがないと、怖くて不安になるんですよ。だから、そこに当てはまらない生き方をしている人を、執拗に攻撃してしまうんでしょうね」
枠に当てはめた生き方をすることで、人は安心する生き物である。うさぎさんは、人間をこう冷静に分析する。そこにあるのはある種の“諦め”にも似た感情とも思える。
「でもね、結婚のカタチなんてひとつじゃなくて、その人の生き方に応じた“十人十色”のスタイルがあって良いと思うんですよ。『こうあるべき』なんて崩してしまって。ただ、そこに不安を感じる人もいる。私は自由に生きてきたけど、そうなれない人たちのこともわかってあげたいなとも思います。そして、自由に生きる人と規格を大切にする人、双方が叩き合うのではなく、まずは対話すれば良いと思う。闘うことも大切だけど、意見を交わすことで歩み寄れるかもしれないでしょ?」
編集後記
インタビュー終了後、うさぎさんを迎えに来てくれたKさん。うさぎさんを支え、「段差があるから気をつけて」とやさしく声をかけるKさんの姿からは、惜しみない愛情が溢れているように感じられた。
セクシュアリティも異なり、子どものいないふたりは、「生産性」という価値基準からすれば、逸脱した夫婦とされてしまうのかもしれない。しかし、ふたりの間で育まれてきた愛情は、決して生産性などというもので判断できるようなものではないだろう。
今後、うさぎさんたちのような関係性が珍しいものではなくなることで、きっと救われる人たちがいるはず。そう感じられる取材だった。
取材・Text/五十嵐 大
中村うさぎさんプロフィール
1958年2月27日生まれ、福岡県出身。『ショッピングの女王』シリーズや、『死からの生還』『他者という病』『あとは死ぬだけ』など、実体験を元にした著書を多数出版。現在は『うさぎとマツコの往復書簡』『新宿二丁目の女王』『中村うさぎの死ぬまでに伝えたい話』を連載中。
DRESSでは10月特集「名前のない関係たち」と題して、愛する誰かと心満たされる人生を送るヒントをお届けします。










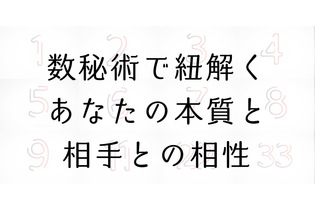










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。