17歳のとき、34歳は現役を引退していると思っていた
女としてのレースから一刻も早く棄権したかった。

「あの女、男の前ではぶりっこなんだよねぇ」
ドーナツ屋のバックヤードで、村上さんは腹立たしげに言った。彼女は店で一番古株のバイトだ。
村上さんの視線の先には食洗機があり、バイトの中で一番可愛い女子大生と、同じくバイトの中で一番かっこいい男子大学生が並んでカップを洗っていた。
女子は、小首を傾げて上目遣いで男子を見たり、「えい!」と彼の腕に洗剤の泡をつけたりしている。村上さんは、少し離れたバックヤードからその様子を眺め、その女子の「ぶりっこ」に悪態をついているのだ。
17歳だった私は、村上さんのその言葉を聞いてぎょっとした。
彼女は34歳の主婦だった。
34歳は、17歳からするとおばさんだ。私は、おばさんが大学生に対して「女」「男」という言葉を使ったことに驚いた。
自分の母が男子大学生のことを「男」と言い表していたら、私はそこに気持ち悪さを感じる。まるで異性として意識しているみたいで。それと同じ感情をこのときの村上さんに抱いていた。
しかし、村上さんにとって、男子大学生は「男」で女子大生は「女」なのだ。
まさかこの人、まだ「現役」のつもりじゃないだろうな。
現役プレイヤーは常に、異性から恋愛対象として「アリ」か「ナシ」かをジャッジされる。
あまつさえ「この中なら誰がいい?」といった格付けの対象にされる。本人にエントリーした覚えがなくても、勝手にレースに参加させられるのだ。
一方、現役を引退すると、「アリ」か「ナシ」といったジャッジをされることはなくなる。すべての異性にとって、考えるまでもなく「ナシ」だからだ。当然、格付けレースにもエントリーされない。
大学生は当然、現役のプレイヤーだ。一方、私から見て、村上さんはもう現役を引退している。現役を退いた人は、観客としてプレイヤーたちを観戦することを許される。ときにはコーチとして、プレイヤーに助言を与えることもできるはずだ。
しかし、村上さんの「あの女、男の前ではぶりっこなんだよねぇ」は、まるで自分がライバル選手であるかのような口ぶりだ。
いや、大丈夫ですよ。あなたはもうとっくに引退しているんだから、他のプレイヤーを気にしなくてもいいんですよ。あなたはもう、ここにいる男の子たちの「この中なら誰がいい?」といった話題に名前が上がることはないんです。
だから、男だの女だの意識しなくていいんです。ぶりっこを見ても、「あら、若い子はいいわねぇ」って目を細めていればいいんです。そのほうが、あなただって楽でしょう?
……と、希望シフトを書き込みながら、心の中で語りかけていた。
今思えば、当時の私はとても傲慢で、浅はかで、何もわかっちゃいなかった。
私は、母の「女」の顔を見たことがなかったし、見たくなかった。
同じように、すべての大人の女性に対して「女」の封印を求めていたんだと思う。
■自分が34歳になって
私は昨年、34歳になった。
そう、当時の村上さんと同じ年齢だ。年齢も同じだし、主婦であることも共通している。
自分が34歳になってみて思うのは、この年齢で「女」を引退している人は意外と少ない、ということだ。私より年上でも、「この人、女だなぁ」と感じる人はたくさんいるし、そういった人たちに対しての嫌悪感もない。
むしろ、「あの人、いい年して女全開で気持ち悪いよねぇ」といった陰口を聞くと、10代の頃の自分を棚に上げて「そんなの他人の勝手だろうよ」と思う(しかし、10代の子が同じことを言っていたら「うんうん、気持ちはわかるよ。でもね、あの女の人は君のママじゃないから、そんなに嫌悪しなくてもいいんじゃないかな?」と思う)。
現役に見える人と、そうではない人の違いについて考えてみる。
周りを見ていると、年齢は関係ない。
既婚かどうか、子どもがいるかどうかも関係ない気がする。
そして、思う。
女として現役かどうかは、本人が「女」を自認しているかどうかではないだろうか。
他人が年齢や見た目で「あの人はもう現役じゃない」とジャッジするのではなく、本人が「女」として見られることを望まなくなったとき、本人の意思によってのみ引退できるのだ。
私のことをいうと、29歳で結婚し、翌年に「三十路の主婦」という肩書きを手に入れたあたりで女を引退できた実感がある。それは、ネガティブなことでもなんでもない。
私はずっと、「女」として見られることが苦手だった。「三十路の主婦です」と名乗り始めてからは、異性の友人が増えたし、若い女の子から慕われることも増えた。「女」としてではなく「個人」として見てもらえる機会が増え、グンと生きやすくなった。
しかし、すべての女性が私と同じように思うわけではない。引退を望まない女性だっているだろう。
他人に「女」の引退を望むことはとても愚かだ。
17歳の私は、村上さんに対してとても失礼だった。
■あざとくたって、いいじゃない
一方で、やっぱりあのときの村上さんには共感できないな、とも思う。
昨年、私はあのときの村上さんと同じ状況を経験した。
昨年まで働いていた職場で、大学生の女子スタッフが、同じく大学生の男子スタッフに甘えた声で話しかけていた。「ねーねー、うどんのトッピングは何が好き?」と問い、彼の「揚げ玉かな」の返答に対してキャハハと笑う。「ふつうー!」と言いながら、彼をつつく。
その微笑ましさに、目を細めた。
言わずもがな、彼女は揚げ玉が面白かったのではない。気になる男子の答えなら、お揚げでも天ぷらでも、なんだっていいのだ。彼女は少しでも彼に触れたいし、少しでも自分を可愛く見せたいのだ。
そんな女子を見て、「微笑ましい」以外の感情は浮かんでこない。
たしかに、彼女の態度は「あざとい」。
彼女のそういった態度を苦々しく思う女性もいるだろう(村上さんだったらきっと怒っていた)。私が子どもの頃から「男の前ではぶりっこ」という陰口は定番だった。
だけど、誰かが異性の前で「ぶりっこ」をしていても、第三者が傷つけられたり、不利益をこうむることはない。
第三者には、他人のあざとさを苦々しく思う正当な理由がないのではないだろうか?
もちろん、感情に常に「正当な理由」があるわけではない。「なんかわかんないけどムカつく」ことのほうが、圧倒的に多いだろう。
そんなときこそうんと理屈っぽくなって「他人がぶりっこしていても私にデメリットはないのだからいいじゃないか」と思えば、少しは楽になるかもしれない。
私は昔から、いわゆる「ぶりっこ」に対して腹が立たない。
それは、性格の理屈っぽさもあるのかもしれない。
■女としてのレースを棄権したかった
若い頃の私は、一刻も早く現役を引退したかった。
しかし、年齢が若いと否応なしに現役と認定されてしまう。
バイト先でも学校でも、男の子たちの「この中なら誰がいい?」レースにも勝手にエントリーされてしまう。
それが、たまらなく嫌だった。早く市原悦子みたいな可愛いおばあちゃんになって、女としてジャッジされる苦痛から開放されたかった。
なぜなら、どうせモテないから。
どうせ、私は恋愛対象として「ナシ」だし、「この中なら誰がいい?」というランキングでも最下位だからだ。
誰かにそう言われたわけではない。だけど、過剰なほど自己評価の低かった私は、そう信じて疑わなかった。
女としての格付けレースでビリにはなることは耐えられない。ビリになるくらいなら、レースを棄権したい。
だから私は、男友達に「あなたは恋愛とかそういうんじゃない」と言われると、とても安心した。
「そういうんじゃない」いただきましたー! と嬉しく思った。
ファッションひとつとっても、私のそれはすこぶる男ウケが悪い。若い頃の私はエスニックファッションが好きで、タイパンツやマクラメ編みのアクセサリーを身に着け、オノ・ヨーコみたいな黒髪を頭のてっぺんでおだんごにしていた。
好きでしていた格好だが、そのファッションは「サキは恋愛とかそういうんじゃないよな」という評価を定着させ、女としてジャッジされる機会から身を守ってくれた。
また、カラオケに行けばサンボマスターや銀杏BOYZを歌う(ファッションと音楽の世界観が一致していない)。もちろん好きだから歌っているのだが、結果的に、可愛い曲をリクエストされる苦痛から逃れることができた。
女性らしい服装が好きな女の子たちは大変だ。
aikoや大塚愛をリクエストされて、誰が一番可愛かったかジャッジされてしまう。その点、私は楽だ。だって私は、「そういうんじゃない」から。
女性らしいにも関わらずモテないのだとしたら、それは、私の容姿や人間性に難があることを意味する。しかし、そうじゃない。私はそもそも恋愛対象じゃないから、モテないのだ。
当時の私は、モテない理由を作り出すことでしか自尊心を保てなかった。
一方で、「女」を引退してからの私は、女性らしい服を着ることに抵抗がなくなった。異性の目を意識しなくなったことで、自分の女性らしい部分を封印しなくなったのだ。
今の私は、ワンピースばかり着ている。
■女としてジャッジされることから逃げなかった人たち
私は、自分が逃げたものと向き合ってきた女性たちに敬意を抱く。
女としてジャッジされることから逃げなかった女性が、なんの苦痛もなくそれを受け入れていたと、誰が断言できるだろう。
自分が陰で「アリ」だの「ナシ」だの言われることに、他人と比べて順位をつけられることに、苦痛を感じない人のほうが少ないと思う。辛い思いをした人も、たくさんいるだろう。
30代になってからの私は日に日に自意識が薄れて、どんどん楽に(鈍感に)なっていく。
「若い頃は異性の目を気にしちゃってめんどくさかったなぁ」と思う。
だけど、「たいしたことじゃないのにね」とは絶対に言わない。
渦中にいる人にとってはとてもとても「たいしたこと」で、そのことを私は、痛いくらい知っている。










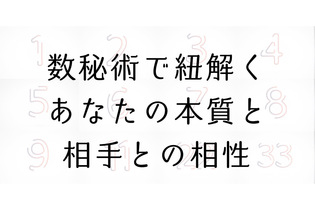










1983年生まれ。noteにエッセイを書いていたらDRESSで連載させていただくことになった主婦です。小心者。