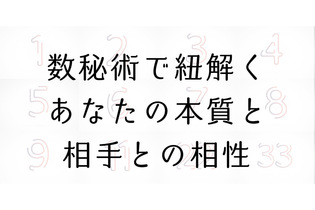【出産ストーリー】39歳で妊娠した大泉りかさんの場合
出産ストーリーは一人ひとり異なる。初産となる大泉りかさんの出産ストーリーを詳しくお届けする。難産ではなかったものの、壮絶な痛みや不安を乗り越えた出産ストーリーは、これから妊娠・出産する方にとって、参考になること、考えさせられることが多いはず。

■出産ストーリーの後半は、想定外の宣告で幕を開けた
「このままだと来週の水曜日には管理入院して、帝王切開になります」
出産予定日の12月28日を過ぎても産気づく気配がないまま、年も明けた5日の検診で担当医から受けたのは、そんな想定外の宣告だった。
計画出産が失敗に終わったことで、「どうせ年を越しちゃうなら、夫婦水いらずのお正月をゆっくり楽しませてもらおう」と、のんびりと過ごしていたことが仇となったのか、出産に向けて開いてくるはずの子宮口は閉じたまま、骨盤に向けて下がってくるはずの赤子の位置もまだまだ高いらしい。
予定日の近くになると、歩いたり階段の上り下りをしたり、雑巾がけなどをして身体を動かして、お産を進める努力をするものらしいけれど、「できれば三が日はまだお腹の中にいてほしい」なんてことを考えていたわたしは、正月らしく飲んだり食ったりしていただけ。あげく、予定日から1週間過ぎても「出てくる気配なし」と診断されてしまったのだった。
帝王切開を前提とした管理入院の予定日は6日後。それまでに子宮口が開くか、破水するか、陣痛が起きるかしないと、遅くとも翌日には手術になるという。経腟で産みたいと望んでいた……というよりも、当然、経腟で産めるとばかり思いこんでいたわたしは、突きつけられた現実に、ひたすら打ちのめされた気分だった。
■「子宮口よ、少しでも開いて」努力が始まる
出産予定日から2週間以上が過ぎてしまうと、胎盤の機能が衰えて赤ちゃんに影響が及ぶ恐れもあるという。その昔にはきっと、対処しようもなく不幸な目に遭うことになった母子もいただろう。
そういうことを考えると、「帝王切開で出す」という選択肢があるだけありがたいともいえるのだが、それでも、享楽に流されて正月中飲み食いばかりしていたことに対して後悔の念が湧いてくる。が、悔やんでも時間は巻き戻せないし、猶予だってあと5日ばかりはあるのだ。
子宮口が少しでも開いてくれれば、医師を説得し、陣痛誘発剤を使うことで、帝王切開は避けられるのではないかと考え、翌日から、わたしの努力が始まった。
具体的には、毎日10km以上歩くこと。しかし、ただ近所をぐるぐると回っていてもつまらないし、飽きてしまう。日に寄って行く方向を変えると同時に、「新しくできたカフェでパンケーキを食べる」や「マタニティリフレを予約し、そこまで歩く」といった目的を作った。
「体重をこれ以上増やしたくはない」とか、「これから物入りになるのに、リフレなんて贅沢」といった考えも、ちらりと頭に浮かんだが、これまでに築いてきた「仕事を終えると美味しいものを食べたり、旅行に行ったりする」というライフスタイルから、目の前にニンジンをぶら下げないと、がんばれない困った性分になってしまっている。
一方、ご褒美さえあれば、相当に踏ん張りがきくことも自覚しているので、そこはもう、自分を甘やかすことを許した。その他にも、1日50回のスクワット、廊下の雑巾掛け、7階の我が家まではマンションのエレベーターは使わずに階段で上り下りし、座るときはいつも胡坐。
さらにはお産が進むという、まるで枯草のような味わいのラズベリーリーフティーをがぶ飲みし、ダメ押しで整体院の先生に相談してお灸をしてもらった。
■帝王切開の可能性を示唆されて……
これを5日間、日課として強行したものの、やはり産気づく気配はないまま入院前日の夜。半ば諦めつつも「どうか、明日の検診には、子宮口が開いてますように!」と願いながら布団に入った朝方、ブチッと身体の内側で何かが弾けたような小さな音がした。
「もしや破水!」そう期待してトイレで確認したものの、羊水らしきものは漏れていない。そんな都合よくいくはずはないと落胆しながら就寝し、翌朝、病院で診察を受けたのだが、結果は、やはり破水だった。気づかなかった自分にびっくりした。
「やった! これで下から産めますよね!?」と喜んだのもつかの間、「これをきっかけに陣痛が起きないと帝王切開です」と医師はあくまでも慎重な姿勢を崩さない。子宮口の開きもまだ3cmほどで硬いらしい。
ヤキモキしながらもそのまま入院し、付き添いで来てくれた夫には「破水はしたけど陣痛もないし、手術になっても明日だから、今日はもういいよ」と一度自宅に帰ってもらうことにした。ところが、病院で出された昼食を食べ終えたあたりで、お腹が張り始めた。
NSTというお腹の張りと胎児の心拍とを同時に取れる機械で測ってくれた看護師さん曰く「陣痛っぽいけど、間隔が整ってないから、まだまだね。もしもこのまま強くなって本陣痛に移っても、産めるとしたら早くても夜中か、明日の朝」だという。
計画出産を失敗した時点で覚悟はしていたものの、夜中のお産の可能性が出てきたことで、新たな心配がむくむくと沸いてきた。というのも、わたしは痛みを和らげる和痛分娩を希望していたのだが、この病院では、麻酔医のいる平日昼間しか和痛の処置ができないことになっているのだ。
帝王切開か、和痛でない経腟分娩か。どちらにしても「わたしの望んだ出産のカタチ」ではない。が、今わたしを押し流そうとしている大きな流れに抗う手段もない。「なんとか明日、麻酔医が来るまで待ってくれ!」とお腹の子に向かって願った。
■理性と激しい痛みの間で揺れる
そんなふうに精神を掻き乱される一方で、肉体も激しく変化に晒されていた。生理痛に似た痛みが定期的に襲ってくる。試しにスマホに入れてあった陣痛カウントアプリに記録したところ、きっちり10分間隔の陣痛の波ができていた。
しかし、先ほど看護師が「早くても夜中になる」と言っていたことを思うと、ナースコールをしていいものか悩ましい。ヤキモキしているうちに、やがて波は5分おきに間隔が狭まってきて、おまけに痛みも声が漏れるほどの強さへと変わってきた。
さすがにおかしいと思って、「陣痛っぽいんですけど」と、ナースコールをした。訪れた看護師が再びNSTで測ると、しっかり本陣痛が来ているという。陣痛室と呼ばれる分娩室の一歩手前の部屋へと移動することになり、バタバタしながら夫にも電話をかけ、陣痛の進みが早いので再び病院に来てもらうように告げた。
ここから先はあっという間だった。陣痛室に入り、戻ってきた夫に付き添ってもらいながら、1時間ほど、内臓をぎゅうぎゅうと捩じられるような陣痛を味わった。いよいよ耐えかねて、「もう無理なんで、麻酔を!」と看護師にお願いしたところ、「麻酔を打つと陣痛が弱くなって、赤ちゃんが苦しむことになるから、このまま産んじゃいましょう」といさめられた。
和痛分娩にすると決めていたといっても、さすがに「赤ちゃんが苦しむことになる」と言われて心が揺らぐ。「ちょっと考えさせてください……」とわたしが譲歩を見せたのをいいことに、看護師は「お母さん、ここは我慢して! 赤ちゃんのことを考えてあげて」とさらに麻酔なしでの出産を執拗に説得してくる。
赤ちゃんを人質に取るような言い方をするもんだから、夫のほうはすっかり「がんばれよ、なっ!」と看護師の味方に回ってしまった。場としては完全に「母として、この痛みに耐えます!」と言わざるを得ない雰囲気だ。しかし、定期的に襲ってくる痛みは、尋常ではない。恥も外聞もなく「痛い痛い痛い痛い!」と大声で叫んだのは、長く生きてきて初めてのことだ。
激しい痛みと理性の狭間で「今すぐ麻酔を打ってほしい、けれども、わたしがここで麻酔を使ったせいで、赤ちゃんにもしものことがあったら……」と苦渋の選択に迫られていると、看護師が夫に言っている言葉が耳に入った。「赤ちゃんの心拍数もだいぶあがってて、苦しいと思うんです。まぁ、死んじゃうとかそういうことはないんで、安心して大丈夫ですけど」
■電動ドリルで掘られるような恐ろしい痛み
えっ、死んじゃう危険性はないの? それがわかれば迷うことはない。「もういいです。わかりました、麻酔してください!」。夫はえっ、と驚いた顔をした。けれど、本当に限界だった。しかも、この痛みがマックスではなく、ここからさらに、出産に向けて、痛みが増すはずなのだ。情けないと言われても、それを耐え切る自信はなかった。
わたしが決意を翻さないことがわかったのか、看護師は説得を諦めると、和痛分娩の手配を取り始めた。ベッドごと分娩室に移動し、ようやくこれで楽になれる、とほっとしたものの、麻酔医が到着するのは1時間後になると告げられた。
この期に及んであと1時間も苦しまないといけないとは……絶望しつつも、このあたりから痛みの質が変わってきた。先ほどまでは内臓を雑巾絞りするような苦しさだったのが、今度はもう少し身体の真ん中、場所でいうと骨盤の上辺りが、電動ドリルでグリグリと掘られているような痛みだ。
それが2〜3分おきに襲ってくるのだが、やり過ごす度に、100mを全力疾走したくらいの体力を消耗する。声はもう勝手に漏れるレベルは越していて、叫びっぱなしなものだから、ベッドの横に付き添っている夫が若干引いているのがわかる。
痛みが引くと、人と会話できるくらいにはなる。だからこそ、痛みの予兆が訪れるのがとにかく恐ろしい。何回くらい耐えただろうか。和痛だなんて中途半端なことをしないで、完全無痛の病院を選べばよかった、と後悔していたところで、麻酔医が到着、ようやくのこと、麻酔を打ってもらった。
■出産ストーリーは一人ひとり違うから
麻酔が効いてくる10分ほどを耐え終えると、だんだんと腹部の痛みが引いていくのがわかった。骨盤が無理やりに広げられる感触はしっかりとわかるものの、さっきまでに比べれば、だいぶ楽だ。「経験として陣痛もちょっとは味わいたい」なんて、どうして舐めたことを考えていたんだろう。
まさに命懸けというにふさわしい痛みから、ようやく逃れられて、心からほっとしたのもつかの間、30分ほどで再び痛みが戻ってきた。嫌な予感にとらわれながら「すみません、麻酔ってどれくらい効くんですか?」と近くにいた看護師に尋ねる。
「人によるけど、30分から1時間くらい」「じゃあ、産むときは?」「麻酔が切れると陣痛が戻ってくるんですけど、その痛みを利用していきんで産むんですよ」。再び陣痛が戻ってくるなんて、冗談じゃない。
「麻酔が切れる前に産みたいです!」と慌てて希望を出すと、看護師が内診をして子宮口の開きを確認してくれた。すると、すっかり開いて柔らかくなっているという。「では、分娩台に移動しましょう」とようやく、分娩台に乗ることができた。
夫婦間の取り決めとして「陣痛までは付き添ってもらうけど、分娩台に乗って出すところは立ち合いしない」と決めていたので夫には分娩室の外に行ってもらった。
そこからいきむこと30分くらい後に、ようやくのこと赤ちゃんはお腹の外に出てきた。陣痛が始まってから4時間とちょっと。初産としてはだいぶ軽いほうに分類されるだろうけれど、それでも、今までの人生の中で最も肉体的にキツい経験だった。
これがわたしの出産のストーリーだ。偶然にも入院中に、友人が同じ病院に入院してきて、わたしが退院したその日の午後に出産をした。しかし、「出産」という行為はもちろん、産んだ病院まで同じであっても、そこに至るストーリー――妊娠中にどう過ごしてきたかや、産むスタイル、出産の進み方――は全然違う。
「生」を始める最初から、こんなにも違うのだ。そういうことを考えると、人と自分とを比べて優劣に悩み、一喜一憂するなんてことは、まるで無意味ではないだろうか。なんていうことを、生まれたての我が子を胸に抱きながら考えていた。