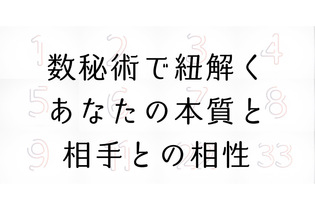女友達に共感するのが苦しくなるとき
女友達とは、何かを共有していれば、共感していれば、ずっと仲良くやっていけると思っていた。でも、年齢を重ねるにつれ「それは違うんじゃない?」と思う部分が出てくる。慣れたはずのやりとりを忘れてしまう瞬間とは。

「ねえ、どうしてそんなひどいこと言うの?」
お酒も飲める夜のカフェで、目の前にいる友人が大きな瞳を潤ませながら言った。滑らかに動いていた唇がピタリと止まる。
そんなにひどいこと言ったっけ、私、と戸惑う。
私が知らない彼女の職場の愚痴。子供の世話が大変だということ、でもとてもかわいいのだということ。少し前まで着ていた服が急に似合わなくなってしまったこと。
直前まで話していた内容を、慌てて巻き戻して確かめる。夫はいるけど子どもがいない私は、彼女が見せてくれる息子の写真に目じりを下げて喜んだ。
「そうそう、最近はあそこの服を気に入ってるの」
それから、彼女の愚痴について意見を述べた……というより、それは違うんじゃないの、あなたも悪かったんじゃないだろうか、と言った。何気ない会話のつもりだった。
■彼女はただ、女友達に頷いてほしいだけだった
反芻してから、しまった、とすぐに気がついた。
彼女は私の意見を述べていたんじゃない、ただ頷いてほしかっただけなのだ。そんな決まりごとをどうして忘れていたのだろう、と猛烈に反省する。
ごめんね、と小さな声で呟く。それから言い訳のように、何か参考になればいいと思ったんだけど、もごもごと付け加える。
私は、あなたのそんな言葉を聞きたかったんじゃないのに。
少し酔っているのか、彼女はそう言ったあと、涙ぐみながら手元にあったカクテルを空けた。私はというと手近にあったフォークの端を触りながら、彼女の機嫌が直るのを、じっと待つ。
でもね、私もあなたのそんな話を聞きたかったわけじゃないんだ、と心の中で呟きながら。
■女友達への共感がしんどくなったのは、30歳を超えてから
同じ制服を着ていた頃は、同じぐらいの丈のスカートを揺らして。
「うん、そうだよね」「わかる、わかる」
頷いていれば話はうまく回って、私たちって仲良しよね、こんなに似てるところがあるんだものね、と満足していたし、それが自分の本心だった。
こんな似た者同士なんだから仲良くならないはずがない、なんて。友達とのおしゃべりはそんな「感じ」でずっと続くと思っていた。誰とだって。
それが30歳を少し過ぎた頃から、あんなによく頷けていた首の動きが悪くなった。相手の表情も硬くなる。
ねえ、前はあんなに私の言うことに頷いてくれていたじゃない。どうして私とは違うことばかり言うの?
瞳が無言で責めてくる。私は私で辛くなる。
どうして、私とあなたが同じだなんて思っていたのだろう。小さな違和感は次第に大きくなって、気がつけば取り返しがつかないくらい、しこりになっている。
■またいつか頷き合う日はやってくる
最近になって、友達が減ったなあ、と感じることが増えた。正確には、今までのように気軽に会える友達が減ったというべきか。
いわゆる「大人」になってから30歳を超える頃まで、新しい恋人ができたり、仕事がますます楽しくなってきたり。結婚したり、離婚したり、子供を産んだり。
それぞれの時間も生活のサイクルも変わっていく。そんなことは知っていたはずだった。
寂しくないと言えば嘘になるけれど、成長であるし、幸せでもある。だから、会えなくても、おしゃべりする時間が減ったとしても気にならない。
むしろ、今はコミュニティも視界も違ってしまい、時間も忘れてしゃべっていた頃には戻れない。そのことを自覚しておくべきなのだ。
思いを共有するのは大切だ。でも、「そうだね」「わかる、わかる」と頷くのには疲れた。今になってようやく自我が生まれたのか。
私の言葉も聞いてほしいのか、それもまた、相手にとっては勝手な言い分なのかもしれない。
思いっきりぶつかり合うようなケンカももはやできない私たちは、曖昧に笑って、ちょっとだけやりとりを減らして、様子を伺いながらまた会う約束をする。次はちゃんと頷こう、余計なことを言うまい、と心に決めながら。
きっとまた同じようなことを繰り返す。そして、少しずつ、なんとなくうまくやっていく方法を見つける。そうしたら、また声高におしゃべりをし、笑い合うことができるのかもしれない。
そのときは、今より顔のシワも増えているのだろうけれど。