「後悔するかもしれない」けど、そのとき正解だと思えた選択をしていく
自分が抱えている痛みと向き合うことは難しい。どうすれば回復していくのかもわからない。一歩間違えれば、自分の傷を理由に、他の誰かに痛みを与えてしまうかもしれない。そうなってしまったら、きっと後悔するのではと、葛藤を抱えていたエッセイスト・碧月はるさん。そんな彼女を救った友人からの言葉について寄稿していただきました。

■「書くだけならいい。公開はするな」を無視して押した、公開ボタン
以前、個人ブログで告発文とも言える文章を公開した。ある企業との執筆に関するやり取りのなかで、あまりにも理不尽な事象が重なっていた。しかし私は、その気持ちを相手側に一切伝えられずにいた。単純に、怖かったのだ。それを伝えてしまったら、これまで築いてきた関係性もがんばってきたことも、すべて崩れてしまうのではないかとさえ思っていた。それほどまでにその企業の名前は大きく、私という個人はちっぽけであった。
声を上げて現状を打破し、同じような被害が起きることを未然に防ぎたい。そういった強い信念のもとに書いた……と、そう言いきれたならまだよかった。しかし、残念ながらそうではなかった。墓場まで持っていくと心に決めた事柄を表に出したのには、それなりの理由がある。だが書いているときの私は、涙と鼻水で顔をぐちゃぐちゃにしながら、時々それらを袖口で拭いながら、どうしようもない気持ちで文章を連ねていた。それはもうどこまでも、「自分のため」だけの文章だった。
辛かった。苦しかった。悲しかった。そして何より、悔しかった。奥底に沈めていた期間が長ければ長いほど、一度溢れたものは留めようがない。
脳内でもうひとりの私が必死に叫んでいた。
「書くだけならいい。公開はするな」
書き終えた文章を数回読み返したのち、私はその声を無視して公開ボタンを押した。
■飲みきれなかった煮え湯と、湧き上がる後悔
公開した文章は、想像以上に広く読まれた。予想に反して批判の数はさほど多くはなく、たくさんの方々が賛同と寄り添いの言葉をかけてくれた。抱え込んでいたものがほどけていく安心感。理解してもらえた安堵感。温かい感情が湧き上がると同時に、底知れぬ怯えもあった。自身の言葉がタイムラインを埋め尽くしていく。思いがけず広まっていく波紋を眺めながら、書いているときとは違う、もっと大きな波が容赦なく押し寄せてくるのを肌で感じていた。
煮え湯を飲んででも変えたいことがある。その一心で書き続けてきた2年間、幾度となくやるせない感情を下書きに眠らせては消去した。ためらい傷のようなそれらを覚えているのは私だけで、表に出さなければ知られようもない。
理不尽だと感じたことは山のようにあった。同じ時間を割き、同じことを頼まれたはずなのに、私以外の著名な人にだけ報酬があったとき。言ってもいないことを「あの人が言っていた」と歪曲されたとき。「不幸の数とフォロワー数が比例していてすごいですね」と揶揄されたとき。忘れられたらいいのに、と思う。でも私は、傷ついた出来事を「なかったこと」にできるほどお人好しじゃない。誤解のないように言い添えると、これらは先日公開したブログに関する企業とは一切関係のない、他の個人的なやり取りのなかで起こった事象である。
私は結局、煮え湯を飲みきれなかった。熱くて熱くて、吐き戻してしまった。後悔の塊がドッと押し寄せてきて、目の前が淡くぼやけた。慌てて安定剤を口に流し込み、身体を丸めて夜が更けていくのをじっと待った。止まらない通知。飛んでくるさまざまな声。9割の応援の声以上に、1割の痛烈な批判の声が大きく耳の奥でこだましていた。
■「あとから後悔するかもしれないけど、そのときはそれが正解だったんだから」
本当にこれでよかったのか。他にやり方があったんじゃないのか。何度もその考えが頭を掠めた。傷ついたことを「傷つきました」と公にする。それ自体は間違いじゃないと思いながらも、批判された側が負う痛みを否が応でも考えてしまう。
正解がわからない。自身の思考と他人の思考。それらが勢いよく渦を巻く。動かなければ。応えなければ。他でもない自分自身が発したことなのだから、しっかりしなければ。そう思えば思うほどに、身体は強張り心は委縮した。そんな折、ある友人からDMが届いた。そこに書かれた言葉を読み、私は大袈裟ではなく声を上げて泣いた。
まるで存在そのものを全肯定してもらえた気持ちだった。構成というフィルターを通さず、そのままに発した私の言葉。それは間違いなく、私の呼吸だった。知ってほしい。わかってほしい。理不尽な仕打ちを受けた側が、口を閉ざして孤独にさらされひとりきりで抱え込む。そんな状況がまかり通るのはおかしいよって、そう叫びたい気持ちを私は選んだ。公開ボタンを押す瞬間、私の“正解”はたしかにそこにあったのだ。
友人の言葉通り、表に出した数時間後、私のなかにはすでに後悔の念が生まれていた。それは今もなお、消えてなくなったわけではない。自信満々に「これで間違いはなかった」なんて、やっぱり言いきれない。ただ、ぎりぎりの状態で出した答えを否定しなくてもいいのだと、そう思えた。スマホを握りしめながら、友人の言葉を静かに反芻した。
赤ん坊としてこの世に生を受けた瞬間、私はすぐには泣かなかったらしい。助産師さんが生まれたての私を逆さ吊りにして背中を叩き、それでようやく私は「オギャア」と泣いたそうだ。そのときの話を私に教えてくれたのは、今は絶縁状態の母である。どのような思いで私にその話をしたのか、彼女の心情は知り得ようもない。ただ今回の件があり、ふとそのときの話を思い出した。私は随分と昔から、泣くことも息をすることも下手くそだったようだ。
■他の誰が何と言おうと、それが唯一無二の答えだった
温かい言葉を食べたあとは、決まって温かいものをお腹に入れたくなる。安心するとお腹が空くのは、大人も子どもも同じだろう。重い腰を上げて立ち上がり、自宅にある材料でオムライスを作った。ケチャップの香ばしい匂いと、卵のふんわり甘い香り。混ぜ合わせたそれらを口に運びながら、またしても喉が震えた。
坂元裕二脚本のドラマ『カルテット』で、バイオリニストの真紀さんがチェリストのすずめちゃんに言った台詞を思い出していた。
「泣きながらご飯を食べたことのある人は、生きていけます」
すずめちゃんは幼少期、「天才魔法少女」として父親の詐欺の片棒を強制的に担がされていた。当時の動画はネットにも流出しており、そのせいで行く先々で陰湿な嫌がらせを受け続けた。バレる、逃げる、バレる、逃げる。ひたすらにその繰り返し。失ったものの数は、計り知れない。
ある日、父親が危篤との連絡を受け、すずめちゃんは病院へと向かう。しかし彼女の足はそこで止まり、病院の目前で引き返してしまう。そんな彼女を見つけたのが、カルテットドーナツホールの演奏仲間である真紀さんだった。
一足先に病院を訪れていた真紀さんは、すずめちゃんの父親が亡くなった事実を知る。それをどうにか告げるも、すずめちゃんは聞きたくないと言わんばかりの様子で真紀さんの言葉を遮り続けた。
行かなきゃ。行きたくない。相反する葛藤の狭間で、ぽつりとすずめちゃんが呟く。
「家族だから、行かなきゃだめかな」
最初こそ病院に行くよう促していた真紀さんだったが、そんなすずめちゃんの様子を見て、きっぱりと言いきった。「行かなくていいよ」と。「でも……」と逡巡するすずめちゃんに、真紀さんは「いいの」と言った。そうしてふたりはお蕎麦屋さんでカツ丼を食べた。泣きながら、笑いながら、口いっぱいに頬張った。
親の死に目に立ち会わない。それは世間一般的には、あまり理解されない感覚だろうと思う。しかし、「立ち会わない」と決めるには、それなりの理由があるのだ。そう思わせるだけの何かが、これまでの時間のなかにあったのだ。真紀さんは、その痛みを知っている人だった。
いつかその決断を後悔するかもしれない。でも泣きながらカツ丼を食べていたあの瞬間、ふたりの決断はふたりだけのものだった。他の誰が何と言おうと、それが唯一無二の答えだった。
“いま”出した決断が、必ずしも絶対解であるとは言いきれない。それはどんな場合でも言えることで、人は迷ったり悔やんだりしながら、それらと折り合いをつけながらどうにか日々を生きている。だからこそ、自分が“そのとき”に出した答えを自分くらいは肯定してやりたい。他人から見た正解を軸に物事を判断する悪い癖を、私はいい加減捨て去りたい。
オムライスにこぼれた涙で、ケチャップの赤が薄く滲んだ。飲み込む瞬間しゃくり上げないよう気をつけながら、少しずつ食べ進めた。一口ごとに思った。生きていける。食べようと思えているうちは、きっと大丈夫。そうやって時間をかけて空にしたお皿を流しに運び込む頃、私の涙のおおよそは乾いていた。

■「弱い人なら傷つけてもいい」なんて、どこの誰が決めたんだ
私が取った行動のすべてを、間違いじゃないとは言いきれない。でも、間違いだったとも言いきりたくない。長い目で見て間違いだったとしても、友人が言ってくれたように、「そのときの私にはそれが正解」だった。
記事を公開したら批判が飛んでくることはわかっていた。誰かを批判するとき、こちらも批判される。それは避けようのないもので、表で書き続ける限りついてまわる悩みでもある。
公開直後の私は、批判と冷静に向きあうことができなかった。ついでのように飛んでくるただの“悪口”と正当な批判との境界線が淡くぼやけ、思わずすべてに目を塞いだ。端的に言えば、覚悟が足りなかったのだと思う。
批判のなかには、「強くなれ」という意のものも多分に含まれていた。その意見を否定したいわけではなく、「傷つけられないためには強くあれ」という社会の構造が根本から変わってほしいと願う。
間違いかもしれない。後悔するかもしれない。そんなふうに揺れ動く選択の裏側には、人の弱さが色濃く存在している。けれど、だからといってその弱さは執拗に責められるべきものだろうか。私はそうは思わない。人の弱さにつけ込む人がいたとして、責めを負うべきは「つけ込んだ」側ではないのか。
弱いから傷つけられる。弱いから搾取される。そんなことがまかり通ってたまるか。「弱い人なら傷つけてもいい」なんて、どこの誰が決めたんだ。
そもそも「強い」も「弱い」も、あまりに基準が曖昧だ。概念でしかないそれらを無理やり押しつけたところで、根本的な解決には繋がらない。私にとっての「強い」と誰かにとってのそれは、必ずしもイコールではない。
私にとっての「強い人」とは、誰かを守るために言葉を使える人だ。壊れる寸前だった私に、「胸を張って大丈夫」と言ってくれた友人みたいに。
そういう人になりたい、と思う。人間ひとりの腕はあまり長くなくて、届く範囲は限られていて、自分には大したことなんてできないと弱気になるときもあるけれど、届く範囲だけでも腕を伸ばし続けたい。あの夜の私みたいな人が半径5メートル以内にいたら、せめて言葉で駆け付けたい。それを望まずそっとしておいてほしい人だったなら、静かに後ろ側から見守りたい。
人は最後はひとりだし、他人を変えられると思うのは奢りでしかないのかもしれない。でも、少しの間だけ隣に腰掛けることはできる。声をかけることはできる。できることが少ないからと何もかも諦めてしまう前に、ひとつだけでもできることをしたい。
あの夜、ひとり縮こまって泣いていた私みたいに後悔の塊に圧し潰されそうになっている人が、今この瞬間もどこかにいるのだろう。そんな人に、届けばいい。頼もしくも温かい、友人が伝えてくれた言葉。私個人に向けて送ってくれた言葉を広く読まれる場所で書きたいと思ったのは、その願いがあったからに他ならない。










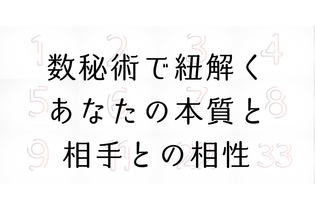










エッセイスト/ライター。各種メディア、noteにてエッセイ、コラム、インタビュー記事、小説を執筆。書くことは呼吸をすること。