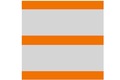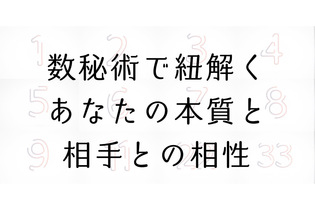妻から、自殺未遂をした夫へ【キス・オブ・ライフ #1】
河崎環さんによる「キス」をテーマにした連載がスタート。キスには恋愛や性愛のキスだけでなく、親が子にするキス、海外の挨拶としてのキス、出会いのキス、別れのキス、いたわりやねぎらいのキス……いろいろあります。各々の人生のワンシーンを印象的に切り取るキス、読むと思い出される情景があるかもしれません。


地震とも、雷ともつかない大きくて重たい音が、2階から轟いた。ウッドデッキへ開け放されたリビングの窓辺から風がひと筋吹き入って、揺れたウィンドチャイムが不規則な音階を奏でる。
ーー亮ちゃんだ。亮ちゃんが、何かした。
あたしは咄嗟に、亮ちゃんが暴れてタンスでも倒したのだと思った。左胸に顔を埋めて母乳を飲み続けている晴樹の口に横から指を入れて乳首から離し、戸惑って泣くハルちゃんをそのまま胸に抱いて2階へ駆け上がる。階段の最上段の向こう、高い吹き抜けのある主寝室に見えたのは、倒れたIKEAのスツールと、床の上に落ちてる、パジャマのままの亮ちゃんの背中だった。
■鬱の人を責めちゃだめだ

「亮ちゃん!? どうしたの?」肩で荒い息をしている亮ちゃんの顔を覗き込むと、首から赤い登山用ロープが伸びている。
「なぁにやってんのよおおぅ! 亮ちゃん! なにしてんのよぅ、あなたはぁ!!」
泣いてるハルちゃんを床に置いて、首から、首からロープを外さなきゃ。手が肩までガタガタと震えて、使い物にならない。2回、形だけの深呼吸をして、まだ震える両手でロープの輪っかを持ち上げるけど、ロープは思ったより硬くて治りかけてた指先のあかぎれが深く切れ、ロープに血がついた。なにやってんの、こんなことしたら死ぬよ? 死ぬんだよ? そんな言葉を何度も飲み込みながらやっと亮ちゃんの頭から外すと、あたしは、忌々しいロープを部屋の隅へ投げ捨てた。
ハルちゃんの長くのびる泣き声が響く中で、あたしと目を合わせずにメソメソ泣く亮ちゃんが情けなくて頰を張りそうになって、瞬間、グッと体を硬くして抑える。だめだ、鬱の人を責めちゃだめなんだ。
ほっぺたが熱い。床にへたり込んで、自分がいつのまにか止めどなく泣いていることに気がついた。ねえ神様、こんなことになっても、あたしはこの人を責めちゃいけないんですか。
3人目の子どもが生まれたばかりだっていう父親が、無茶な事業失敗のプレッシャーでヘルニアになって働けなくなって鬱になって引きこもって、首からロープを垂らしながらこんな大きな体を床の上で丸めてすすり泣いて、このロープはそんなことするために吉祥寺のマムートで買ったんじゃなかったよね? この寝室の高い天井にむき出しの立派な梁は、あなたがぶら下がるために渡したんじゃないよね? ハルちゃん、半年前に生まれたばっかりなんだよ? ハルちゃんの妊娠中から様子がおかしくなった亮ちゃんは、本当は息子が無事に生まれたことさえ喜べずに表情をこわばらせていたのが、あたしはすごく、すごく悲しかった。
■そうやって一生逃げるんだね、あなたは

お坊ちゃん育ちの亮ちゃんが、雇われ歯医者はもうイヤだって親にお金を出してもらって独立して、だけど歯科医院なんてどこの町も飽和状態。小綺麗でファミリー狙いの、特に戦略もないどうってことない新規のクリニックなんかすぐに閑古鳥が鳴く。
昔からつるんでる、同じように恵まれたお坊ちゃんばっかりの私立校サーフィン仲間の手前、俺はただの町医者じゃなくてビジネスマンなんだって肩書きが欲しかった亮ちゃんは、ダメな歯科医院の例に漏れず、自転車操業の本院の負債を補填するために分院を開業してしまった。
ダメな歯科医院が2つに増えただけで、根本的にはなにも解決しないまま、分不相応に抱えたスタッフの給料も、あの若い可愛い衛生士の家賃も払えなくなって、借金は増えるばかりで、そんな矢先に腰を痛めたからもう診療に立てないだなんて言い出して、逃げて、逃げて、ずっと逃げて。そうやって一生逃げるんだね、あなたは。
■男って、馬ッ鹿だな。

自分が泣きじゃくる声を聴きながら、ああ、誰も私の背中をさすってくれたりしないんだと思った。夫はまだ床の上で丸まったまま、身じろぎ一つせずどこか遠い一点を見つめてすすり泣いてる。息子も床を這いずって母親を求め、泣く声がただずっと大きくなって広い部屋いっぱいに反響する。男って弱いな。男ってこんなに弱いんだ。女がしっかりしなきゃ、泣くばっかりでなにもできやしない。馬鹿だな、男って。馬ッ鹿だな。
まだ震える手でハルちゃんを抱き上げて、よしよしと揺らしてあたしの涙と鼻水だらけの顔をほっぺに押し付けてキスをした。ずっと半分出しっぱなしだったおっぱいを咥えさせると、ハルちゃんはぴたりと泣き止んで痛いくらいにぐいぐい飲み始める。ひっきりなしにしゃくりあげていた自分の嗚咽が弱くなってきて、あたしは顔じゅうを覆うべとべとが冷えて乾いていくのを感じながら、梁を見上げてはあとため息をついた。壁掛けにしたサーフボード。時計は、午後2時10分。
ハルちゃんを片手で胸に貼り付かせたまま、立ち上がってティッシュを取りに行く。もう一方の手で何枚もザクザクとティッシュを引き抜いて、その半分で自分の顔をゴシゴシ拭いた。残り半分を亮ちゃんの顔の前に差し出す。「立てる?」と聞くと、亮ちゃんはそれには答えずに目をぎゅっとつぶって、小さい声で「ごめんね」と言った。謝ったようには聞こえなかったけれど、あたしはかがみこんで、夫の頰にそっとゆっくりめにキスしてあげた。ハルちゃんがつぶれないように、3人で変な形のハグをした。
■トム・フォードのサングラスをかけて

「幼稚園バスの時間だから、お姉ちゃんたち迎えに行ってくるから。何もしないで寝てて。何もしちゃだめだよ」。もし何かしちゃったとしても、もうそれはそれかな、って冷えた考えが頭のどこかにあることに気づいて、自分でちょっと驚いた。とにかく、バスのお迎えの時間だから、あたしは行かなきゃ。
ハルちゃんをカウチにごろんと寝かせて、空いた手で手早く厚めに化粧をする。泣き腫らした目をカモフラージュするために、目の周りにコンシーラーを叩き込んで、強めにアイラインを引いて。
濃い目の口紅で顔色を良くして、ハルちゃんをエルゴの抱っこ紐に入れて、幼稚園バスの停留所まで歩いて行こう。途中で実家のママとパパに電話したほうがいいかもしれない。年長さんと年少さんの娘たちをピックアップしたら、ママ友の家にそのまま預かってもらって、亮ちゃんをベンツで精神科に連れて行こう。うんそうだ、ハルちゃんが1歳になったら、あたしも働こう。よし、メイク完了。
幼稚園バスが来るまではトム・フォードのサングラスをかけて。女は、何があったってこうやって化けて誤魔化して歩き出せる。それができない男は、か弱い生き物だ。
「行ってきます。すぐ戻るからね!」
亮ちゃんに玄関からひと声かけて、あたしは、ガチャリと家に鍵をかけた。なんだろう、もう手は震えていなかった。