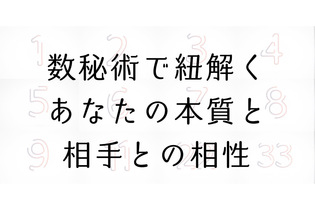雨宮まみさんが選ぶ、私を変えた5冊の本

本というメディアは、いつでも手に取れるものだと思いがちです。けれど、実際はそうでもありません。物理的にはいつでも手に取れる。開いて読むこともできる。ただ、そのとき心が求めている文章でなければ、まったく入ってこないのです。過去に強い印象を受けた本でも、再読してみると「この本のどこがそんなに良かったんだろう」と思うこともあるし、逆もあります。読むたびに深みを増していく本もありますが、どのパターンでも、二度と同じ気持ちで読むことはできないという点では同じです。

本を読むか読まないかは、こちらが思っている以上に一期一会。これだけたくさんの本が出ていれば、ほんの少し気になった、でも手に取らなかった、というだけでもう一生思い出さないで終わってしまうこともあります。それまでまったく読んだことのない作者の本に妙に気をひかれて「これは、いま自分が読むべき本のような気がする」と感じることもありますが、その気持ちだって、一週間ほったらかしにしておいたら消えてしまいます。とにかく、読書には、今しかない。今、読むか読まないか、それしかないのだとよく思います。本は私と出会い、読まれ、通り過ぎてゆく。通り過ぎていった本は、基本的に昔の恋人のようなもので、特に思い出したり、読み返したりすることはありません。ただ、あんなところが良かった、こんなところがすごかった、という記憶だけが残ります。
なので、今回のテーマである「私を変えた本」とはいっても、それらは過去に通り過ぎてきたどこかの地点に読み捨てられていて、ほとんど手元には残っていません。現在手元にあるものは、いままさしく私の人生に楔を打ち込んでくるような本です。その中から5冊を紹介します。
『しろいろの街の、その骨の体温の。』村田沙耶香(朝日新聞出版)
『死ぬ気まんまん』佐野洋子(光文社)

生きることについて、死ぬことについて書かれた2冊です。『しろいろの街の、その骨の体温の。』は、ただの子供からある日突然「女」として見られるようになった少女が、不安や焦りや劣等感、周囲との比較の自意識地獄の中でもがき苦しみながら、「本当に自分自身として生きる」ことへ初めて手を伸ばし、自分の意志で人生に触れる姿が描かれています。描かれている醜い闘争の中の美しい意志が、郊外の「しろいろの街」の風景の中でくっきりと映えています。
『死ぬ気まんまん』で描かれるのは、死ぬ前の風景です。ホスピスで、山の夕陽に照らされた森がまるでゴッホの描く絵のように葉っぱの一枚一枚までくっきりと見えたと佐野洋子は書いています。若い頃には自然なんか見なかった、と言う佐野洋子は、こんな自然のもとからさっさと出ていきます。
『1985年のクラッシュ・ギャルズ』柳澤健(文春文庫)
『井田真木子 著作撰集』井田真木子(里山社)

昨年、私を大きく変えた、嵐のような二冊です。「1985年の~」を読み、自分が探し求めていた「女の人生」に対する答えの一部が、プロレスのリングの上にあったのだと初めて知りました。いや、どこにでもその答えはあったのだろうけど、私にとっては、リングの上の女たちの姿や言葉に、本気で憧れることのできる何かを感じた、ということなのでしょう。
女は、ある日突然、女として生きることを社会から要求されます。それがどういうことなのかを描いているという意味では、『しろいろの街の~』と同じ分野の本と言ってもいいと思います。
同じく、プロレスの著作があることをきっかけに読み始めた『井田真木子 著作撰集』では、どんなテーマを扱っていても、真摯に向き合えば向き合うほど、まるで自分の話のようになっていく井田真木子という人のあり方が面白いです。客観を目指せば目指すほど、なぜか主観に近いものに着地してしまうところに、人の、自分の力ではどうにもコントロールできない個性や魅力を感じます。特に少女買春についての『ルポ14歳 消える少女たち』は、切り取られた場面、言葉がとても強い。作られた年代や地域が違う強い酒がショットグラスでカウンターに並べられていて、それを順番に飲み干していくような読書体験です。忘れられない強烈な言葉がいくつも喉を灼きながら身体の中に落ちていきます。
『つかこうへい正伝』長谷川康夫(新潮社)

学生の頃は『蒲田行進曲』の面白さがわかりませんでした。面白いという輪郭だけがぼんやりと理解できる、という程度だったのに、久しぶりに映画の『蒲田行進曲』を観てみたら、破綻しかけた人間ばかりが出てくるのに、そのむちゃくちゃさ、身体中から端切れが飛び出ているような感じに「あ、人間ってこういうもんだよね」と心から納得できてしまいました。小さい範囲の倫理や正義をばんばん踏み抜いて走っていくような野蛮さと、自分で踏み抜いておきながら「大丈夫?」と純粋に心配の眼差しを向けてくるような矛盾をはらんだ人物像は、今のほうがより魅力的に見えるかもしれないし、もしかすると拒否反応を引き起こすかもしれません。
人たらしで自分の利益に貪欲、他人の犠牲をなんとも思わないのに、妙に情に厚い。つかこうへいの人物像は、そのままつかこうへいが描く人物像のようです。けれど、彼も最初は無名の一文学青年であり、おそらく自分で自分を演出し続けて「つかこうへい」になっていったのではないか。つかこうへいがつかこうへいになり、名を成すまでの物語は、どうしようもない若い日々の青春物語でもあります。
著者の「絶対に聖人君子になんかさせない。つかこうへいは俗人であり、だからこそあんな作品が作れたのだし、だからこそ愛すべき人物なのだ」という叫びが聞こえてくるような、死した人を過剰に持ち上げない筆致の正しさに心を打たれます。死した人を自分好みに持ち上げることこそが、死者を本当に殺すことです。それは、どんなに褒めていても、死者への冒涜だと私は思います。できる限り、生きているときと同じ高さの目線でつかこうへいを語ろうとする姿勢に、誠意を感じました。
私の場合、良い本であればあるほど、それについて語る言葉は貧しくなります。良い本とは、自分の書けない言葉が書かれている本だからです。届かないところにある言葉でできている本だからです。それは決して完璧な言葉ではありません。隙や欠点をむきだしにしながら、何かに食らいついていくような言葉です。いわば裸の言葉です。
この世に美しい言葉というものがあるとすれば、それはまず、なによりも裸の言葉でなくてはならないと思うのです。