変わらないものはなくとも、残り続けるものはある
人の気持ちは、驚くほど簡単に変わる。けれど、変わってしまった気持ちは嘘になるのだろうか。移ろいゆくものの中でも、信じられるものがあるとしたら――。エッセイスト・碧月はるさんが綴る、変わっていくことと、変わらないと信じたいものについて。

道に迷っていた。提灯に書かれた地名を見て、函館の湯の町を走っていることだけは理解できた。でも、私が当時住んでいたアパートは、湯の町ではなく中道だった。函館の道は、入り組んでいて迷いやすい。筋金入りの方向音痴である私は、暗い道端で車のハザードランプをつけ、ひとり途方に暮れていた。
せっかく温泉街に辿りついたのだから、いっそどこかに一泊してみようか。そんな誘惑が頭を掠めたが、通帳残高と財布の残金は悲しいほど惨めなもので、淡い妄想は一瞬にしてしぼんだ。温泉どころか、月末に納豆を買うことさえ危うい。迷子になってガソリンを消費している場合ではないのに、提灯の灯りが川辺りにゆらゆらと揺れている様はとてもきれいで、思わず見惚れた。
Googleマップなんていう便利なものがなかったあの当時、とにかく地図を買わないことにはどうしようもなかった。痛い出費に心の中で舌打ちをしながら、コンビニの自動ドアをくぐる。眉をしかめて地図をあれこれ値踏みしていると、突如頭上から低い声が降ってきた。
「道に迷ったの?」
背の高い、男の人だった。私はこのとき、まだ20歳そこそこで、その人はそんな私より10歳ほど年上に見えた。
「はい」
見知らぬ人ではあったけれど、気づいたら当たり前のように返事をしていた。その人が纏っている空気は嫌なものではなかったし、私が忘れられなかった人に少し声が似ていた。
「送ってやろうか?」
「いや、車で来たので」
「んじゃ、先導してやるよ。俺んちすぐそこで車持ってるし。家どこさ?」
「中道です」
「ああ、職場の近くだわ。待っとけ。地図なんか見てもわかんねえだろ、実際」
そう言って、その人は私の返事も聞かずにコンビニを出て行った。普通なら、待つべきじゃなかった。私はその人のことを何も知らなかったし、もしもおかしな人だったら危ないであろうこともわかっていた。でも、この夜の私の心は、警笛を鳴らさなかった。
函館でのひとり暮らしがはじまって数カ月。当時の私には、どうしても忘れられない人がいた。知り合いが誰もいない土地で、毎晩たったひとりで二度と会えない人の声と面影を思い出す毎日は、単純に寂しかった。あけすけな言い方をしてしまえば、誰でもいいから温もりがほしかった。

コンビニに戻ってきたその人に言われるがまま、住所を伝えて彼の車の後ろを追いかけた。見覚えのある道に入ったところで、ふいに焦燥感に襲われた。20歳も過ぎて迷子になって、見知らぬ男性にほいほいと住所を晒して、挙句の果てにあわよくば肌まで晒そうとしている。どれだけ思い続けても掠りもしない人の感触を身体ごと覚えているのに、その痛みを埋めるために身も知らぬ男とその真似事をしようとしている。そんな自分のバカさ加減に、呆れて乾いた笑いが漏れた。同時に、瞳からもやるせなさがこぼれた。
迷うことなく私のアパートに辿りついたその人は、私の顔を見て少し黙って、「何で泣いてんの」と呟いた。「何で」と言いながら、理由を聞くつもりはなさそうだった。泣きながら突っ立っていた私の唇は塞がれ、あっという間に深くなっていく感触に思わず足が震えた。全然違う、と思った。記憶にこびりついている人のキスは、もっと不器用で、拙くて、幼くて。でもだからこそ、抗う気になれなかった。いっそのこと、すべて塗り替えてほしかった。もう会えないのなら、記憶ごと全部消してしまいたかった。
部屋になだれ込み、そのままシャワーも浴びずに重なった。その人はどこまでもやさしい触りかたで、痛みを感じさせないよう丁寧にことを進めていった。明らかに慣れた手つきである様子に、私は安堵していた。今、この瞬間だけ私たちが持ち寄った寂しさを埋められたなら、もうそれだけでよかった。
シャワーを浴びて出てきた彼は、そこではじめて名を名乗った。私もつられてそうした。そして、ふたりで笑いあった。名前も知らない人と重なることができるくらい、あの夜の私たちはひたすらに寂しかった。

私の生い立ちは少し複雑で、その一部を知っただけで妙なスイッチが入る人を大勢見てきた。
「俺が一生守ってあげる」
「ずっと傍にいる」
「絶対にひとりにしない」
悦に入った表情でドラマみたいなせりふを言う相手を、いつも冷めた気持ちで眺めていた。人の不幸な生い立ちを餌に、自慰行為の真似事をされている気分だった。
果たされない約束が、何よりも嫌いだ。出会ってすぐに浮ついた言葉を発する人を、私は信用しない。人の気持ちは、驚くほど簡単に変わる。この世界に「絶対に変わらないもの」などない。でも、この夜出会った彼は、そういう類の言葉を一切口にしない人だった。
「また来てもいい?」
「いいよ」
たったこれだけの会話で、私たちは世間一般でいうところの恋人になった。
狭いアパートの一室で、私たちは会うたびに肌を重ねた。温もりを欲していたのは、多分お互い様だった。彼はあまり自分のことを話さず、私もまた、話さなかった。濡れた髪を彼がドライヤーで乾かしてくれるのが好きだった。
「熱かったら言えよ」
必ずそう言うくせに、私が「熱い」と文句を言うと「ちょっとくらい我慢しろ」と少年のように笑った。
魚焼きグリルで火傷をした私の指を慌てて冷やしてくれて、高熱があっても仕事を休もうとしない私に本気で怒ってくれて、肌に触れる前と後に必ずキスをくれた。『Leon』を観て一緒に泣いた夜、マチルダのせりふを真似て「大人になっても、人生はつらい?」と彼に問うと、「つらいさ」と答えてくれた。ジャン・レノとは似ても似つかない顔なのに、私はやけに切ない気持ちになって、彼の胸に顔を埋めた。
寂しいもの同士が重なり合ううちに、何かが育っていくのを感じていた。それはきっと、私側だけの自惚れではなかったろうと思う。

薄い敷布団の上でいつものように汗をかいていた最中、唐突に彼が言った。
「この気持ちがずっと変わらなければいいのにって思う瞬間が、たしかにある」
「え……?」
「そう思うこと、ない?」
ちゃんと答えたかったのに、口を塞がれた私は何も言えなかった。何だか泣いているように聞こえたその声を、20年経った今でも覚えている。私のなかを泳ぎながら苦しそうに眉根を寄せていたこのとき、彼はすでに私との別れを決めていたのかもしれない。
言葉をあまりほしがらず、体温と心だけでつながれていた私たちの関係は、このあと呆気なく終わりを迎えた。
「もう来れない」
ある日突然そう言われて、鍵を返された。ひんやり冷たい裸の鍵を掌に乗せられた瞬間、掌以外のところも冷えた気がした。でも、何でもないような顔をして「わかった」と答えた。引き留めても無駄な人の表情を見るのは、これで二度目だった。
「ちゃんと飯食えよ。よくわかんねぇ文章ばっか書いてないで」
小さな子どもにするみたいにくしゃくしゃと頭を撫でて、その人は出て行った。鍵と、もう読まないからと以前持ってきた小説を置いて。泣きたくないのにあふれる涙を止められない私を置いて。

この世界に「絶対に変わらないもの」などない。人の心は、その最たるものだ。でも、同時に「残り続けるもの」でもあると今は思っている。
彼の気持ちは、結果的に変わってしまった。でも、「変わらなければいいのに」と願ってくれた夜があったことを、私は覚えている。あの人が今どこで何をしているのか、私は知らない。ただ、幸せであれと願う。
自分を粗末にすることでどうにか生きていたあの頃、痛みを感じながらじゃないと、上手く息もできなかった。でも、彼の温もりは今でも私の内側にちゃんと残っている。ほんの少し痛くて疼く。そういう持て余し気味な感情とともに、案外しつこく居座っている。
終わった恋を丸めて捨ててしまえたら楽なのかもしれない。でも、私はそうしたくない。あの一瞬、たった数カ月だとしても、彼は間違いなく私を大切にしてくれた。終わってしまったからといって、その時間のすべてが嘘になるわけじゃない。
不変のものに憧れる気持ちは捨てきれない。それでも、移ろいゆくなかで与えられ、失い、時間にろ過されたのちに残ったものを眺めていると、私の人生も案外捨てたもんじゃないと思えてくる。そんな夜の月は大抵欠けていて、満ちるよりも欠けるときに見えてくるものがあるのだと、夜空を見上げながらぼんやりと彼方の人を想った。










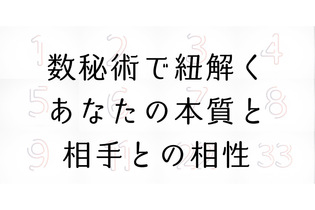










エッセイスト/ライター。各種メディア、noteにてエッセイ、コラム、インタビュー記事、小説を執筆。書くことは呼吸をすること。