『Black Box』彼女の元に問題が集約された【小川たまか】
すでに多くのレビューが出ている『Black Box』。著者であるジャーナリストの伊藤詩織さんは、自分の身に起こった事件を調べ、付随する司法・捜査の問題点を、国際比較なども加えながら一つひとつ明らかにしていく。この圧倒的な一冊を前にして、私たちは何を考えるべきなのだろう。

「別の記事」にも書いたが、私が『Black Box』の著者、伊藤詩織さんに初めて会ったのは、今年の2月だった。その後、5月に『週刊新潮』で初めて事件についての記事が掲載され、同月末に霞が関の司法記者クラブで詩織さん自身が記者会見。10月20日に『Black Box』が発売された。
週刊新潮の最初の記事では「27歳の女性」だった彼女が、記者会見で「詩織さん」となり、そして本名の「伊藤詩織」へ。この1年間で彼女の環境は大きく変わり、私はそのストーリーをハラハラしながら見守る脇役になったような気持ちがした。
■「被害者らしくない」被害者は排除される
詩織さんは早い段階から捜査に疑問を持ち、「ホテルの監視カメラを調べてほしい」などの要望を自分から口にする。捜査がなかなか進まないことには、性犯罪を現在の司法で裁くことの難しさが関係していることに気付く。
また、混乱の中でも、自分の尊厳の回復のために情報を調べる。そして、性暴力を取り巻く支援の不足、婦人科でも性被害を想定していない言葉をかけられるなど、傷ついた被害者がまるでひとりで放り出されるような現実に気付く。
この現状は、どこかおかしいのではないかと気付き、変えるために行動すること。それは大きな困難を伴う。
「周りが変わることに期待するのではなく、まず自分が変わろう」と言われることがある。もちろん自分が変わることが必要な場面もある。しかし、今回の詩織さんのような件があったときに、社会を変えようとする人を半笑いでたしなめたり、苦難を抱える人に我慢を強いて終わりにしたりする行為は、一体誰にとって都合がよいのだろう。
性犯罪の被害者が「あなたが黙っていれば終わること」「騒ぎ立てればあなたがもっと傷つくことになる」と言われ、沈黙を余儀なくされることは多い。そして、困難を社会に訴えようとした人が途端に敬遠されることは、性犯罪の被害者に限ったことではない。「被害者らしく」しない被害者、物を言う被害者は排除されることがある。
■加害者が裁かれない理由
あまりにも理不尽な現実を目にしたとき、それを受け入れたくない気持ちとの間で葛藤が起こる。だから性暴力の取材はとてもつらい。私が取材したり、出会ったことのある被害者たちの多くは、「加害者」が裁かれていない。理由はいくつかあるが、そのうちのひとつは「暴行・脅迫」要件の壁だ。
『Black Box』で引用されている、ゴルフのコーチが師弟関係にあった女子高生をホテルに連れ込んだ事件の判決は有名だ。高裁の判決は、女子高生が精神的な混乱から拒否ができなかったことや性交の同意がなかったことを認めたが、彼女より38歳年上だった男性コーチは「無神経」な性格だったために拒否に気付かなかったとし、「無罪」。2014年の判決だ。
1例で足りないのであれば、1999年の『犯罪被害者―いま人権を考える』(河原理子/平凡社新書)で紹介されているケースを挙げよう。
「有名な判決がある。
七八年広島高裁判決。自営業者が、知り合いの女性をだまして車で海辺に連れ出して、口説いたが応じなかったため押し倒し、『やめて、帰らせて』と泣き叫ぶ女性の下着をはぎとって性交を強行した刑事事件だ。一審は有罪。二審は、性交には力の行使が伴うのが通常だとしたうえで、殴るなどの『強力な暴行』を加えていない、下着も破いてはいない、女性は逃げなかったし激しい抵抗はしていないから、『到底、和姦とは言えないが、強姦ではない』と無罪にした」
裁判では「暴行・脅迫」がなければ強姦とは認定されないが、一方で上記の判例のように、性交にはある程度の力の行使が伴うのが通常と見なされている。強姦と認定されるための、「暴行・脅迫」のハードルが被害者にとっては高いのだ。
日本の裁判での有罪率は非常に高い。だからこういった無罪判決が膨大にあるわけではない。だからいいのかといえばそうではない。無罪判決を恐れる検察が起訴を躊躇することを、性犯罪に詳しい司法関係者らが指摘している。
警察で門前払いを受けることもあり、『犯罪被害者』の中でも、警察から「あなたの言う通りなら強姦ですね、でも、ドラマみたいに簡単にはいかないんですよ」と言われたケースが紹介されている。私がこれまで「捜査してもらえなかったケース」「不起訴となったケース」を聞いたのは一度や二度ではない。
なぜこのような理不尽が、あまり知られていないのかと思う人もいるかもしれない。ひとつには、性被害が非常にタブー視され、触れづらい問題であるからということがある。また、被害者があまりにも力を奪われ過ぎているということもあると思う。傷つき、混乱する被害者に、「この理不尽を訴えろ、闘え」と言える人はいないだろう。
さらに、被害者が世の中に訴えたくても、メディアが取り合わないこともある。立証が難しいし、加害者が有名人でもなければ「バリューがない」。詩織さんも、事件後から複数のメディアに接触していたが、結局報じられたのは約2年経ってからだ。これはメディア側の都合ではないかと個人的には考えている。
性暴力を、一方の性に偏った組織である警察と検察によって捜査され、裁かれること。それが被害者(男女ともにいる)にとってどれだけ絶望的な状況かを想像することができなければ、「ジェンダーバイアス」でググってほしい。もしくはこの字幕付き動画を見ては。
■被害者に沈黙を強いる社会が「安全な国」なのか
『ミズーラ』(亜紀書房)というノンフィクションがある。『Black Box』の中でも紹介されている。米・モンタナ州で連続して起こった複数のレイプ事件をベテランジャーナリストであるジョン・クラカワーが取材した一冊だ。
この本を読んで考え込んでしまったのは、レイプや二次被害の悲惨さだけが理由ではない。ある女性は、好意を持っていた男友達と自宅でDVDを見る約束をし、ルームメイトが隣の部屋にいる状況でレイプされる。また、ある女性は、自宅近くで意気投合した男性を部屋に招き、レイプされる。彼女たちは、相手にある程度の好意を持っていたが、その日はそんな気分ではなかった、自分の意思が尊重されず、尊厳が損なわれたと言う。
私は考えてしまう。日本で生まれ育ってきた女性がこのような被害に遭ったとき、それを「レイプ」と訴えられる人がどれだけいるだろう。「私にも隙があった」「少なくとも警察沙汰ではない」、そう思ってしまう人の方が、多いのではないか。
「男女が部屋の中でふたりきりになったら」とか「ふたりでお酒を飲んで泥酔したなら」、「性行為に及ばれても仕方ない」という“常識”。「イヤよイヤよも好きのうち」とか「据え膳食わぬは男の恥」といった言葉でもいい。これは一体、誰にとって都合がよいのだろう。性被害の中でも知り合いからの被害は、特に告発されにくい。
詩織さんは『Black Box』の中で、その生い立ちにも触れている。中学時代に長い入院生活を送った彼女は、その後10代前半で自分の意思から海外で勉強する道を選ぶ。このような圧倒的なノンフィクションを上梓した彼女が、入院生活を「生きているだけでいい場所」と感じたことや、早くから海外で暮らしたこと。私には無関係とは思えない。黙らされる構造、その支配が彼女には及ばなかった。
性暴力の捜査・司法の問題、支援の不足、世の中の無理解・無関心、二次被害、報道被害と報道の自粛。すべてが彼女の元に集約された。だからいいということではない。彼女が非凡な才能を持ち、いくつかの偶然が重なって告発の機会を得たことに、私たちは甘えてはいけない。
Text/小川たまか
文系大学院卒業後、フリーランスを経て2008年から編プロ取締役。主に性暴力、教育、働き方などを取材。2015年に自身の性被害を書いたことをきっかけに性暴力に関する取材に注力。近々、性暴力とジェンダーに関する本を出版予定。











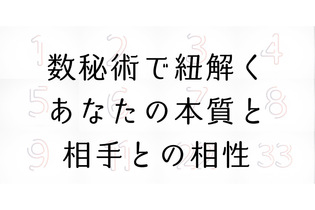










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。