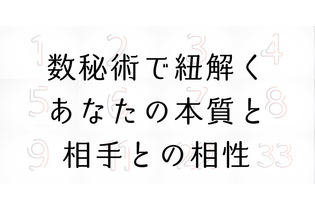ステージに現れた少年を見て、三枝子たち三人はあっけにとられた。
子供。
三枝子の頭に浮かんだ単語はそれだった(中略)
ステージが明るかった。
少年がピアノと触れ合っている(としか思えなかった)ところだけがほっこりと明るく、しかも何か極彩色のキラキラしたものがそこからうねって流れだしてくるように見えるのだ(中略)
いつのまにか曲はベートーヴェンになっていた。
極彩色の色彩が、変化している。
今度は、速度を感じた。何かエネルギーが行き交っているような、音楽の速度と意思を感じ取ったのだ。
(23~25ページより引用)
直木賞受賞作『蜜蜂と遠雷』から響き渡る麗しき音楽【積読を崩す夜#4】
連載【積読を崩す夜】4回目は、2017年直木賞と本屋大賞W受賞作『蜜蜂と遠雷』(著:恩田陸)をご紹介します。まるで、ストーリーの行間から音楽が響いてくるような作品。著名なピアノコンクールを舞台に、四人の奏者の才能と運命が展開していく……。

積んであるあの本が、私を待っている……。少し早く帰れそうな夜、DRESS世代に、じっくりと読み進めてほしい本をご紹介する連載【積読を崩す夜】。4回目は、2017年直木賞と本屋大賞W受賞作『蜜蜂と遠雷』(著:恩田陸)を取り上げます。
3年ごとに開催される、芳ヶ江国際ピアノコンクールを舞台に、4人の若い才能がそれぞれの形で花開き、新しい運命が展開されていく……。
■行間から音楽がこぼれ落ちていく『蜜蜂と遠雷』
芳ケ江国際ピアノコンクールは、3年ごとに開催され、今回で6回目を迎える。過去において、優勝者が世界屈指のSコンクールでも優勝した実績があり、近年評価が高まってきている。
この、芳ケ江国際ピアノコンクールには、風間塵、栄伝亜夜、高島明石、マサル・カルロス・レヴィ・アナトールといった、4人のピアニストたちが出場している。
ストーリーにおいて、音楽コンクールという特殊で閉鎖的な空間における、“音”の表現が、おそろしく緻密に、美しく描かれていて驚きを隠せない。
登場人物の一人である、風間塵は16歳で、“養蜂王子”の異名を持っている。彼は、ピアノを持っておらず、養蜂を仕事とする親と移動生活をしているため、音楽教育をほぼ受けたことがない。しかし、今は亡き伝説の音楽家であるホフマンから「ギフト」と称され、推薦された注目の若手だ。
その彼が棚引く音楽が、どれだけ色彩豊かであるか。そして、逆に言えば、好き嫌いの好みがいかに分かれるものであるかが、文脈から容易に理解できる。
本を読んでいるのに、音楽を聴いているような不思議な感覚に包まれていく。
■かつての天才少女と楽器店に勤務するサラリーマン それぞれの旋律
亜夜の場合、キャリアを断たれた原因ははっきりしていた。
彼女の最初の指導者であり、彼女を護り、彼女を励まし、彼女の身の回りのことをすべてやっていてくれた母が、十三歳の時に急死したのである(中略)
ねえ、お母さん、紅茶は?
亜夜はそう言いかけて、自分が楽屋に一人きりであることに気付いた。
いつも濃い目で甘く淹れた紅茶を、人肌の温度で魔法瓶に入れてきて渡してくれるはずの母の姿がそこになかった。
亜夜は動揺した。足元がすうっと沈み込んでいくような巨大な喪失感が襲ってきた。
(39~41ページより引用)
確かに、明石の家はごく平均的なサラリーマン家庭だったし、妻は幼馴染で高校の物理の先生、明石自身は大きな楽器店の店員、という見事に二代に亘って凡庸な家庭である。中略
俺はいつも不思議に思っていた――孤高の音楽家だけが正しいのか? 音楽のみに生きる者だけが尊敬に値するのか? と。
生活者の音楽は、音楽だけを生業とする者より劣るのだろうか、と。
(52~53ベージより引用)
栄伝亜夜は、ジュニアコンクールにおいて、天才の名をほしいままにしていた才能のある少女だった。圧倒的な実力でCDデビューをも果たしていたが、彼女をずっと導いてくれていた母が突然に死去してしまった。
亜夜は、母の死後、最初のコンサートにおいて、母が死んでしまった事実に、本当に気がついてしまった。そして、その日からピアノが弾けなくなってしまったのだ。
「消えた天才少女」と呼ばれるようになった彼女は、すでに20歳になっていた。通っている大学の学長であり、恩師のすすめで、芳ケ江国際ピアノコンクールに出場することになる。
一方の高島明石は、天才ではないものの、将来を嘱望されて音大に進んだ音楽少年であった。しかし、プロにはならず、現在は楽器店に勤務する、平凡な28歳のサラリーマンだ。
芳ケ江国際ピアノコンクールへの出場を決めたこの一年は、寸暇を惜しんで練習をしてきた。しかし、長年コンクールから離れ、しかも仕事をしながら出場する彼と、訓練だけに没頭する若い学生たちとでは練習量の差が歴然としている。
心に潜む怒りをもとに、明石はどう演奏していくのか……。
■不快感と悪が存在しない それでいて鋭い臨場感
オハヨウ、ニッポン。
マサルは日本語で呟いてみる。
五歳から七歳までの三年間、日本に住んでいたことがある。
正直なところ、あまりよく覚えていない。日常会話程度なら不自由しない日本語を話せたので、家からいちばん近い公立の小学校に入ったのだが、三カ月も持たなかったのだ(中略)
マーくん、迎えに来たよ!
マサルは思わず後ろを振り返る。
あの明るく澄んだ声だけは今でもよく覚えている。いや、もう十年以上経っているというのに、今なおますます鮮やかなのだ。
マサルがピアノと出会ったのは、日本でのことだった。
(82~84ページより引用)
マサル・カルロス・レヴィ・アナトールは、全米随一の音楽大学であるジュリアードにおいて、もっとも人気があり、実力が高いピアニストだ。「ジュリアードの王子様」の異名を持ち、芳ヶ江国際コンクールの優勝候補・本命である。
その彼は、かつて日本に暮らした時期があった。異端を許さない日本で、良い思い出はほとんどなかったが、ただひとつ、ピアノに導いてくれた少女“アーちゃん”の存在は、キラキラと今でも心に光っている。
彼ら4人を中心に、第一次予選から二次予選、三次予選、そして本選へと物語は進んでいく。それぞれが自らのバックグラウンドを振り返りつつも、優勝を目指して演奏をしていく。
奏者である彼らだけがメインではない。審査員や調律師、取材者や奏者のそばでサポートする人々に至るまで、生き方や考え方が交錯している。それなのに、どこにも不快感や悪が存在しない。しかもファンタジーではない。だからこそ、本当に不思議なのだ。
登場人物たちの苦悩と努力、そして天才性に酔いつつ、耳を使わずして、目で音楽を聴く時間。
不思議な読書体験を、静かにかみしめるにふさわしい作品だ。
■恩田陸 著『蜜蜂と遠雷』書籍情報
■著者 恩田陸さんプロフィール
1964年、宮城県生まれ。92年『六番目の小夜子』でデビュー。2005年『夜のピクニック』で第26回吉川英治文学新人賞および第2回本屋大賞を受賞。06年『ユージニア』で第59回日本推理作家協会賞を受賞。07年『中庭の出来事』で第20回山本周五郎賞を受賞など、多数の著書がある。『蜜蜂と遠雷』は、2017年直木賞と本屋大賞W受賞作。