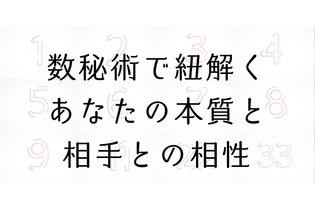とある街の、とある喫茶店の
とある座席には不思議な都市伝説があった
その席に座ると、その席に座っている間だけ
望んだ通りの時間に移動ができるという
ただし、そこにはめんどくさい……
非常にめんどくさいルールがあった
一、過去に戻っても、この喫茶店を訪れた事のない者には会う事ができない
二、過去に戻ってどんな努力をしても、現実は変わらない
三、過去に戻れる席には先客がいる
席に戻れるのは、その先客が席を立った時だけ
四、過去に戻っても、席を立って移動することはできない
五、過去に戻れるのは、コーヒーをカップに注いでから、
そのコーヒーが冷めてしまうまでの間だけ
(2ページより引用)
あの日あの時間に戻れるなら、誰に会いたい?【積読を崩す夜#2】
連載【積読を崩す夜】2回目は『コーヒーが冷めないうちに』(著:川口俊和)をご紹介します。過去に戻れるという不思議な噂がある喫茶店フニクリフニクラ。心温まる4つの女性のストーリーが展開される。もし、あの日あのときに戻れるとしたら、あなたは誰に会いに行きますか?

積んであるあの本が、私を待っている……。少し早く帰れそうな夜、DRESS世代に、じっくりと読み進めてほしい本をご紹介する連載【積読を崩す夜】。2回目は『コーヒーが冷めないうちに』(著:川口俊和)を取り上げます。
「ここに来れば、過去に戻れるって本当ですか? 」
不思議な噂がある喫茶店には、さまざまなルールがあって……。そこに訪れた人々に、心温まる奇跡が起きるのです。
■恋人・夫婦・姉妹・親子 それぞれの愛の記憶
もし、あのときこうしていたら、今の人生は変わっていたのかもしれない……。そんな風に思い起こす出来事は、どんな人の人生にも、ひとつふたつはあるだろう。でも、もし過去に戻る手だてがあるとしたら、はたして自分は誰に何を伝えるのだろうか。
過去に戻れるという噂がある、喫茶店フニクリフニクラ。
人気の少ない路地裏に小さな看板だけ、そして地下に降りると、その喫茶店があるという。想像以上に狭い店内には、カウンター3席にテーブル席が3つだけ。シェードランプの数が少ないから、店内はセピア色に染まっている。なんでも、この喫茶店は昭和7年にオープンして、約140年が過ぎているとか。なぜか真夏でもクーラーいらずで、ひんやりと涼しい。
この、秘密の取引現場のような喫茶店には、マスターとウエイトレスがいて、わけありの常連たちが入れ替わりでやってくる。このような状況では、「大事な話」は、よほどのひそひそ声でなければ、周りに筒抜けというものだ。
雑誌にも、過去に戻れる喫茶店として“都市伝説”のように紹介されたことがあるというが、戻るためのルールの多さと確証のなさから、それはあくまで“都市伝説”。
それでも、奇跡を求めてその喫茶店を訪れる人々は、今日も密かに絶えないのだ。
当初の目的は、五郎のアメリカ行きを阻止するために過去に戻る事だった。阻止するというと聞こえは悪いが、「行ってほしくない」と告白する事で五郎はアメリカへ行く事をやめてくれるかもしれない。あわよくば、別れなくてすむかもしれない。つまり、なぜ過去に戻りたいのかといえば、それは「現実を変えたいから」であった。
(39ページより引用)
「三年……」
五郎が二美子に背を向けたまま、つぶやいた。
「……三年待っててほしい……必ず帰ってくるから」
小さい声ではあったが、狭い店内である。五郎の声は湯気になった二美子の耳にもハッキリと聞き取れた。
「帰ってきたら……」五郎は右眉の上をかくような仕草で二美子に背を向けたままボソボソと何か言った。
(86~87ページより引用)
本書の登場人物・二美子には、今まで仕事以上に好きな人が現れなかった。こんなにも一目をひく、美しいキャリアウーマンなのにだ。そして、五郎は世にいうゲームオタク、ただし、ものすごく優秀なプログラマーで、アメリカに本社がある世界規模のゲーム会社に転職することを目標としていた。
そんなふたりがふとした仕事の縁で、恋人同志となる。どちらかといえば、二美子からの熱烈アプローチ。でも、はたから見れば、才色兼備な二美子とオタク気質の五郎は、不釣り合いな組み合わせだったのしれない。
そんなさなか、五郎はかねてからの夢が叶い、アメリカ行きが現実のものになった。しかし、五郎はそれを二美子に相談してはくれなかった。結局のところ、二美子ではなく、夢を選んだのだ。
そして、出発の日。フニクリフニクラでせっかく会っていても、別れの言葉もままならないふたり。それどころか、旅立とうとする不器用な五郎に対して、二美子は感情のままになじってしまった。結局そのまま、五郎はアメリカに旅立ってしまった。
後悔しても、どうにもならない。しかし、二美子はマスターや常連たちから、過去に戻るたくさんのルールを教えてもらい、意を決して、あの日のフニクリフニクラに戻ることにした。
五郎に会いに戻る、言えなかったことを伝えなければいけないと。
……あの日に戻った二美子、それなのに五郎とのぎくしゃくとした会話が続くばかり。でも、二美子は「相談してほしかった」の一言を、やっと伝えることができたのだ。その一言で、ふたりの会話が変化していく。
五郎の本当の想い……美しい二美子と自分は、釣り合わないと思っていたこと。いつか二美子が、自分のもとを離れていってしまうのではないかと思っていたこと……。
短い時間でふたりの心が通い合ったとき、五郎は言うのだ。「3年待っていてほしい」と。
現実は変わらないけれど、未来はどうなるかはわからない。大切な人に、大切な一言を伝える勇気。これこそが、未来を切り開く鍵になりうることを、若いふたりの物語が教えてくれるようだ。
「やっぱ、忘れちまうのか? 俺は、お前の事……」
房木が、うつむきながら、ぼそりとつぶやいた。
その言葉を聞いて、高竹の頭は真っ白になった。中略
だが、返事をしない高竹は、房木の質問にイエスと答えたようなものだった。
房木は、そんな高竹を見て、
「そうか……やっぱりな……」
と、悲しげにつぶやいて、首が折れそうなほど深くうなだれた。
高竹の目から涙がこぼれた。
アルツハイマーだと診断され、日々、記憶が消えていく恐怖と不安を抱えながら、それでも妻である高竹にはそれを気づかせず、一人で耐えていた夫。
その夫が、高竹が未来から来たと知って最初に確認したのは、妻である高竹を忘れていないかどうか、という事だった。
(162~163ページより引用)
フニクリフニクラの常連である房木は、アルツハイマーの病のため、極めて大事なこと……ついに妻のことをも忘れるようになっていた。妻の高竹は、房木を混乱させないために、旧姓で自分のことを呼ばせるようにしていた。
ところが高竹は、昔から文字を書こうとしないはずの房木が持っている手紙が、気になって仕方がない。それが何なのかという話も、もはや夫とはできない状況。だから過去へと、まだ記憶がある房木に会いに戻ることを決める。
……ぶっきらぼうで照れ隠しばかりの、懐かしい夫と再会。
しかし、房木は常連であるからこそ、妻が未来から来たことを察してしまう。こうして妻が過去に戻ってきたということは、自分の病が進行しているのだと気がついてしまうのだ。なぜならこのとき、既に自分の病を房木は知っていたから。
そして、一番に気がかりであったことを房木は口にする。自分が妻を忘れてしまうのかどうか、ということを。
高竹は言えなかった。大丈夫だから、治るから、安心して、と伝えることが精いっぱいだった。
……手紙を預かり、夫に背中を押されて現在に戻った高竹は、涙なしにその手紙を読めなかった。ずっと夫婦でいたいという夫の不器用な言葉の数々。深い愛情が手紙にはあふれていたから。
高竹は、それから旧姓での呼び方を皆に禁止することにした。どんなに夫の記憶から、自分がいなくなっていったとしても、房木の妻として、笑っていることにしたのだ。
抗いようのない運命であったとしても、夫婦の間に確かにある絆と愛情。言葉にできるときに、照れずに伝えておくこと。それさえあれば、未来永劫に相手に気持ちを伝えられなくなったとしても、未来を迎えていけるという真実に、胸がいっぱいになってしまう。
■現実を超えるために、伝えなくてはいけない
たとえ過去に戻っても、できることは限られていて、現実を変えることはできない。
だからこそ、人は今このとき、目の前にいる人に気持ちを伝えなくてはならないのだ。あなたが大切であること、あなたのことが大好きであるということを。
あたりまえのように過去に戻れる非日常が、あたりまえの現実のように描かれているからこそ、よけいにリアリティを感じてしまう喫茶店フニクリフニクラ。そう、コーヒーが冷めないうちに、目の前に座っている人へ、自分の気持ちを伝えたくてはいけないと素直に感じる。
そんな気持ちが駆り立てられる1冊、それが「コーヒーが冷めないうちに」。
「コーヒーが冷めないうちに」
著者: 川口俊和
発行:サンマーク出版
定価:1300円(税別)
川口俊和 著『コーヒーが冷めないうちに』書籍情報
著者 川口俊和さんプロフィール
元・劇団かたつむり脚本家兼演出家。本作の元となった舞台、1110プロヂュース公演「コーヒーが冷めないうちに」で、第10回杉並演劇祭大賞を受賞。本作が小説デビュー作。