「すっぴんを褒められてもうれしくない」ギャル文化の研究から見えた、“自分らしさ”のつくり方
“自分らしさ”は決して生まれ持ったものではなく、あとから「つくる」ものだということを、ギャルファッションに身を包んだ女の子たちに教えられた──。日本女性の「盛り」文化の研究者である久保友香さんが、研究を通して見えてきた“自分らしさ”の正体について綴ります。

私が高校生だった1990年代半ばはちょうど、肌を焼いて、髪を脱色し、強いアイメイクをした、いわゆる「ギャルファッション」と呼ばれるスタイルの女の子たちが広がり始めた頃だった。DRESSの読者の中には、実際にギャルファッションをしていた方々もいるかもしれないし、逆にそれを不可解な目で見ていた方もいるかもしれない。
私はといえば、当時、全国の女子高生による売上1位だったファッション誌『non-no』を愛読するような平均的な女の子で、ギャルファッションはしておらず、それを不可解に思いながらも、彼女たちに対して好感を持っていた。
それからしばらく経った2010年頃から、私は女の子たちの「盛り」という行動を研究するようになった。「盛り」というのは、デジタル・テクノロジーの発展によりさかんになったバーチャル・コミュニケーションにおいて、リアル・コミュニケーションとは異なるビジュアルを作る行動だ。当時は、プリクラやガラケーでの自撮り写真で「デカ目」を作ることがさかんで、その中心にいたのもギャルファッションの女の子たちだった。ただし肌は焼いておらず、区別するため、1990年代半ば以降の「黒ギャル」に対し、「白ギャル」と呼ばれることもある。
私は彼女たちに「なぜ盛るのか?」とインタビューした。彼女たちは最初答えに迷うのだが、最終的に辿り着くのは意外な答えだった。「自分らしくあるため」と言うのだ。私には、「デカ目」にした女の子たちの顔がそっくりに見えていた。それなのに、彼女たちがそこに“自分らしさ”を感じているとは、どういうことなのだろうか?
■「デカ目」は一見、ぜんぶ同じに見えるけれど
私はインタビューした女の子のうちのひとりに、1日行動観察をさせてほしいと頼んだ。彼女は快く受けてくれて、週末、渋谷に出かけるのについて行かせてもらった。まずは、ゲームセンターでプリクラを撮るという。
順番を待っているとき、彼女は「プリクラはトレーニングが重要」と言った。どういうことかと聞くと、プリクラにはいくつもの機種があり、それによって、画像処理の特徴も、シャッタータイミングも違うと言う。だから、その機械のシャッタータイミングや画像処理に合った目の見開きをできるように、同じ機種を何度も使って慣れる必要があるということだった。
続いて、ドン・キホーテでの買い物について行った。つけまつげ売り場で、今つけているのはどれかとたずねると、彼女は3つの商品を指さした。なぜ3つもあるのかと驚いたが、それらを組み合わせてつけているという。私はさっそくその3つを購入し、組み合わせ方を見せてほしいと頼んで、近くのカフェに入った。彼女は自身の化粧ポーチからはさみとピンセットを取り出し、慣れた手つきで、3つの商品を切り刻み、組み合わせていく過程を見せてくれた。
こうした行動を観察してから、私にはもう女の子たちの「デカ目」の顔が、そっくりには見えなくなった。よく見ると、プリクラ写真での目の見開き方も、つけまつげの複雑さも、皆それぞれ違っていて、彼女たちの言う“自分らしさ”が見えてきた。
■日本の女性にとっての“自分らしさ”
彼女たちの言う“自分らしさ”とは、生まれ持って「ある」ものではなく、画像処理や化粧などによって「つくる」ものなのだ。
このような考え方は、他国の人からは理解されないことが多い。以前、フランス人の女性と話していたら、彼女は日本の女の子たちがギャルファッションなどでする濃い化粧を、「“自分らしさ”を否定する行為ではないか」と指摘した。それは“自分らしさ”が「ある」ものだという考え方を前提にしている。しかし日本には古くから、“自分らしさ”は「つくる」ものという考え方があったのではないか。
一例として、日本の歴史的美人画を見てみよう。絵巻に描かれている平安時代の貴族の女性たちも、浮世絵に描かれている江戸時代の高位の遊女たちも、顔を白粉で塗り、眉を剃って描き、唇に紅をさしている。これだけ濃い化粧をしていたら、顔は皆、そっくりに見えただろう。
しかし、平安時代の貴族女性たちは、他人とは対面せず手紙でやりとりしており、”その人らしさ”は、女性たちが書く手紙の中の、歌や筆跡に表されていたという。また、江戸時代の遊女たちは、顔のみならず、言葉も「ありんす言葉」に統一されていたが、歌や踊りなど芸事によって “その人らしさ”が表されていたという。高位の遊女を「太夫」と呼ぶことがあるが、それがもともと芸事に長けた人の呼び名であることからもわかる。つまり、生まれ持って「ある」容姿ではなく、歌詠みや芸事など努力で「つくる」ことができる能力を評価するシステムが、日本には古くからあったのだ。
同じことはギャルファッションの女の子たちにも言える。後になって私は、1990年代に黒ギャルのファッションをしていた女の子たちにもインタビューをしたのだが、2010年頃の白ギャルの女の子たちと共通して彼女たちが言うのは、「すっぴんを褒められてもうれしくない、化粧を褒められたい」というようなことだった。「盛れてる」が、彼女たち同士の最上の褒め言葉だった。
■ギャルファッションの女の子たちは、文明的なシステムの体現者だ
このような、生まれ持って「ある」能力より、努力で「つくる」能力を評価し合うシステムは、文明社会において当然とも言える。原始時代は、腕力の強い人が権力者になったが、道具が誕生してからは、道具を所有したり、使いこなしたりできる人が権力を持つようになった。生まれ持った能力を評価し合うことは、ある意味では、原始的なシステムだと考えることもできる。
それなのに、こと容姿に関しては、その原始的なシステムが今でもはびこりやすい。しかし、未来社会のあるべき姿は、生まれ持って「ある」容姿ではなく、「つくる」容姿でそれぞれの個性を表現し、互いに評価し合うシステムの方なのではないかと、私は考える。
日本にはその成功事例がある。再び歴史美人画を参考にすると、平安貴族たちは平安京、江戸時代の遊女たちは遊郭という「閉鎖系」(閉じられたコミュニティ)の中で、「つくる」容姿で自分らしさを表すシステムを成り立たせていた。
また、私がギャルファッションの女の子たちをインタビューしていた2010年頃は、女の子向けのケータイブログの利用が広がり、全国の「白ギャル」の女の子たちの間で、「盛れてる」を褒め言葉とするコミュニケーションがさかんにおこなわれていた。これらはガラケー向けのサービスで、パソコンからはアクセスしづらく、特に人気のあった『デコログ』は検索エンジンからアクセスできないようにするなどの徹底した管理で、女の子以外がアクセスしづらい閉鎖系をつくり出していた。ただし遊郭やケータイブログなど、建設的につくられる閉鎖系は、政府や企業の支援なしには成り立たない。
そこで参考になるのが、「黒ギャル」の女の子たちのやり方である。彼女たちは、渋谷などのオープンな場に集まりながらも、その奇抜とも言えるビジュアルで、価値基準の異なる人を寄せつけなかった。彼女たちにインタビューをすると、口々に「わかってくれない人は、わかってくれなくてよかった」と言った。一人ひとりがそのような意識を持つ中で、政府や企業の力を借りずとも、自然と閉鎖系がつくられていったのだ。
「つくる」容姿で“自分らしさ”を表す文明的なシステムを導くために、我々に今、求められているのは、「わかってくれない人は、わかってくれなくてよい」という姿勢ではないか。かつてのギャルファッションの女の子たちが、それを教えてくれる。
Text/久保 友香
メディア環境学者
2000年、慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業。2006年、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。博士(環境学)。専門はメディア環境学。東京大学先端科学技術研究センター特任助教、東京工科大学メディア学部講師、東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員など歴任。著書に『「盛り」の誕生ー女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識ー』(太田出版、2019年)。
DRESSの6月特集は「意思を纏う装い」
— ProjectDRESS (@ProjectDRESS) June 1, 2020
人のファッションやメイクにあれやこれやと口を出すなんてナンセンス。そこにはきっとその人自身の生き方や哲学が詰まっていたり、潜んでいたりするから。そんな意思を表現する人たちの話を特集していきます。https://t.co/toJzVfMWvm










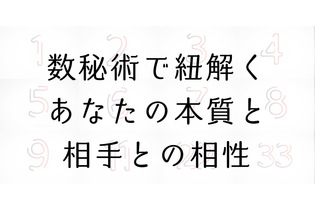










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。