
「私は君を忘れるだろうけれど、君は私を一生忘れることはできないよ」
10連休のリレーエッセイ企画「忘れ得ぬあの人の言葉」。かつて好きだった人から受け取った、忘れられない言葉の思い出を振り返ります。今宵はライター・編集者 サカイエヒタさんの寄稿。本と靴が好きなギャルのアミちゃんと過ごした4年間のこと。

ギャルのアミちゃんは、基本的に「ウケる」「ダルい」「ヤバい」しか使わない。限られた語彙で生きる一方、彼女は異常なほどの読書家で、いつも熱心に本を読み込んでいた。夢野久作「ドグラ・マグラ」を読み終えると、アミちゃんは「ヤバい」とだけ言い放ち、そのまま眠ってしまった。
2008年、この年の冬もまた寒かった。
そして離婚をしたばかりの26歳の僕は、順調に荒んだ生活を謳歌していた。
ギャルのアミちゃんとは、たしか西新宿にある服飾専門学校の喫煙所で知り合ったと思う。どちらかがどちらかにライターを借りて、たまたまアミちゃんが読んでいた本が僕も先週読み終えたばかりの本で、僕らはそのまま近くの「さくら水産」に行き、そのあと歌舞伎町のラブホテル「K」でセックスをして、事後のベッドの中で清い交際をスタートさせた。
アミちゃんに、こんな貧乏なバツイチ男のどこが好きなのか聞いてみたら「顔と体型」と即答された。
見た目以外を尋ねても「ない」とこれまた即答された。
僕はとにかく毎日寂しくて、実際に「寂しい」とよく書き込み、口にしていた。そう言葉にするたび「ウケる」とアミちゃんに笑われる。「そんなに笑うなよ」と傷ついた僕が言うと「笑うし」とアミちゃんはムッとして、また本の世界へ戻っていった。
僕はそんなアミちゃんと、その後4年間一緒に生活することになる。
アミちゃんは靴が大好きだ。ふたりで暮らしていた狭い部屋の玄関はアミちゃんの靴でいっぱいだった。一度数えてみたら52足あった。いい加減整理するよう提案したら、翌週58足に増えていたためさすがに諦めた。
それからも靴は増え続け、部屋はアミちゃんのサンダルやブーツで埋め尽くされていく。
靴だけじゃない。服やカバンやウィッグが僕らの狭い部屋を占領していた。彼女が築き上げた洋服の塚をかき分け、僕はデスクトップパソコンにやっとたどり着く。
その頃の僕は、サラリーマンの傍ら、文章を書いて飯を食うことを夢見て生きていた。カタカタとキーボードを叩き、自分なりのおしゃれな文章を並べていく。
何度か読み直し、胸を張ってアミちゃんにチェックを依頼する。彼女が読書中のときは、少し時間を空けてから見てもらった。プロの文章を読んですぐに僕の文章を見てもらうのはさすがに恥ずかしかったし、そりゃあ多少の嫉妬もあった。
インターバルには、ネットに落ちているくだらないアニメを一緒に観たり、僕が風呂に入る様子を脱衣所から見守ってもらったりした。
下着姿のアミちゃんは爪をカリカリと噛みながら、僕が書いた文章を目で追っていく。彼女の大きな黒目にデスクトップパソコンの白い四角い画面が写り込む。瞳の中で揺れる無機質で小さな光を、僕はこっそり覗き見ていた。
しばらくすると「うーん」とアミちゃんは唸り、「よくわかんない」と任務を放って、本の世界へと戻ってしまう。
「ヤバい」はおろか「ダルい」さえもらえない。そんな毎日を僕は繰り返した。
それから3年が経ち、僕は文章で小さな賞をいくつかもらうくらいにはなっていた。そしてライターとして報酬をいただくようになり、いつしかサラリーマンを辞めても食べていけるようになった。
その頃にはもう、アミちゃんの文章チェックは不要だった。「ヤバい」も「ウケる」も要らない。代わりにプロの編集者さんが僕の文章をチェックしてくれるようになったからだ。
僕はもう寂しくなかった。
周りには僕を褒めてくれる人、主張をぶつけ合える同業者、いつか本を出そうと誘ってくれる大人、憧れてくれる若者、そして隣にいたいと言ってくれる女の子までいた。
そんな彼らとばかり過ごしていたら、ベッド脇のテーブルに手紙を置いて、アミちゃんは家を出ていってしまった。
手紙には「私は素敵な男性と出会い、君のことは忘れるだろうけれど、君は私のことを一生忘れることはできないよ」と書かれていた。

別れてから最初に迎えた夏、アミちゃんは突然僕の家を訪ねてきた。正直、「忘れてないじゃないか」と安心した。
彼女はなぜか派手なビキニをカバンに入れていたので、ベランダに置いた子ども用プールに、ふたりでデリバリーピザを食べながら入る。アミちゃんの身体には、いま着ている水着とは違う形の日焼け跡がくっきりついていて、それは僕の知らない水着のようだった。
生ぬるい水に浸かりながら、僕はアミちゃんに褒められたくて懸命に半年分の自慢話をした。
帰るとき、「プール、また入りに来る」とアミちゃんは言った。それから7年経つが、彼女はあれから一度もプールへ入りに来ていない。
久しぶりにのぞいたInstagramには「素敵な人と一緒になりました」と書いてあった。
アミちゃんからもらった手紙には、こんなことも書いてある。
「もし君が、この先も書く仕事を続けていくのなら、いつか私について一度書いてみてね」
はたしてアミちゃんは、この文章を読んで「ウケる」と笑ってくれるだろうか。
Text/サカイエヒタ( @_ehita_)
コンテンツプロダクション株式会社ヒャクマンボルト代表。日々丁寧に寝坊しています。










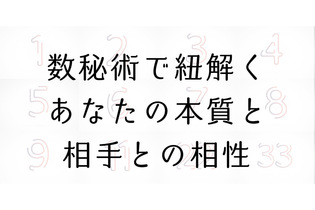










いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。