「この人と恋愛しても幸せにはなれない」。なのに、身体が勝手に相手を選ぶ
エッセイスト・吉玉サキによる連載『7人の女たち』では、とある7人の女性たちが抱えてきた欲望や感情を、それぞれへのインタビューを通じて描きます。今回は、強い色欲を抱いてきた恭子さんのお話し。強烈な欲望こそが人生を動かすエネルギーだと彼女は言います。
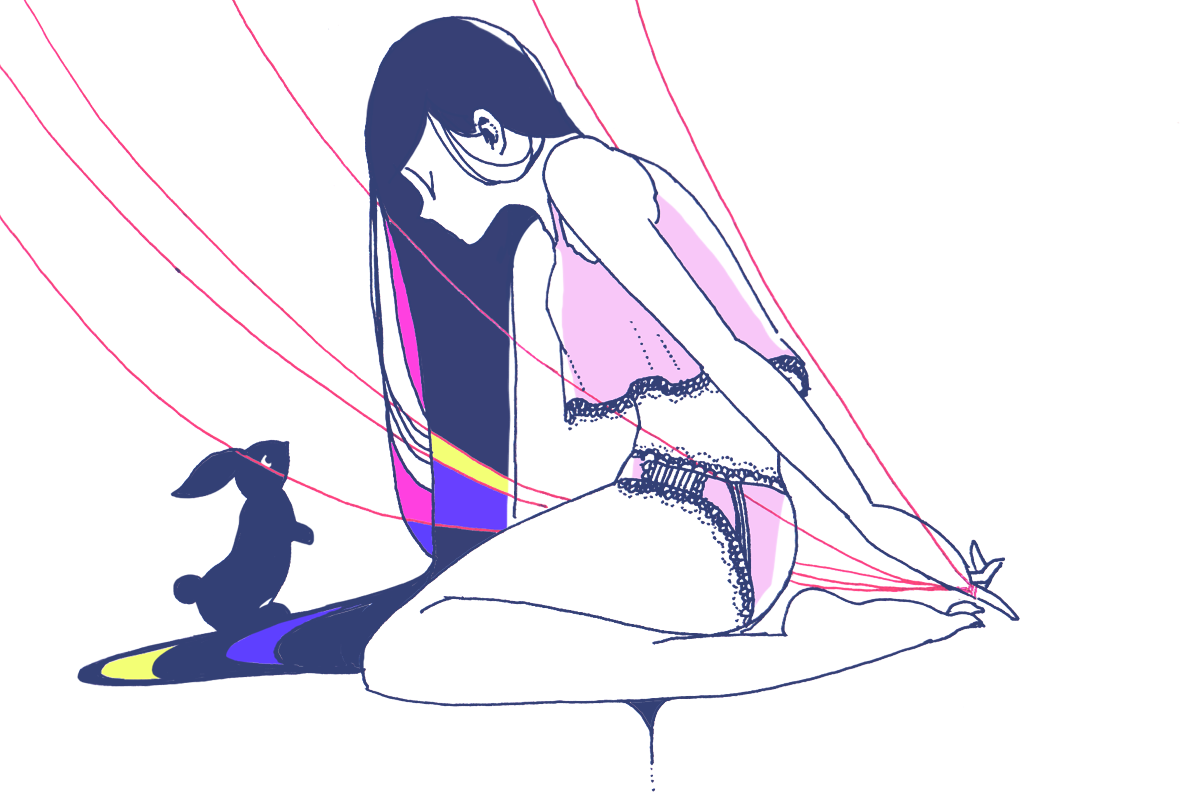
恭子さんは特定の相手にのみ、強い欲望を感じることがあるという。
「性欲よりもさらに生々しいエネルギーかな。セックスだけじゃ物足りないの。この動いているカタマリが丸ごと欲しくてたまらない、っていうか。相手の身体も魂も食らいたい感じ」
彼女にとって、色欲は人生を動かすエネルギーだという。
だから下品なものだとはまったく思わない。罪だとも、手放したいとも思わない。けれど、今はその色欲を失ったそうだ。
新宿ゴールデン街のバーで、彼女の物語を聞かせてもらった。
■身体にドカンとくる相手とは、必ず恋愛関係になる
恭子さん(仮名)は46歳。ある有名企業に勤務し役職もついている、いわゆるキャリアウーマンだ。数年前に結婚し、現在は夫と猫と暮らしている。
彼女は今までの人生で何度も、強い色欲に突き動かされて恋をしてきたという。
「そういう相手と出会うと、身体感覚でわかるのよ。出会った瞬間にものすごい風圧を感じたり、彼の周りがキラキラ光って見えたり。比喩じゃなくて、本当にそう見えるの」
恭子さんはその感覚を「身体にドカンとくる」と言い表す。彼女は語彙が豊富で、話していてとても面白い。その豊かな表現力に圧倒される。
「身体でドカンときた相手とは必ずセックスできるし、恋愛関係になるの。出会った瞬間にそうなる確信がある。相手に恋人がいても『悪いけど、あなたは私と付き合うことになるから』って思うだけ。猛禽類が狙った獲物を逃さないみたいなものよ」
その彼女の言葉には、自信が満ち溢れているように感じられる。しかし、恭子さんは「自信なんてない」という。
「だって、私は美人でもセクシーでもないじゃない。だから別に自信があるわけじゃないんだけど、この人と結ばれるんだって直感的に“わかっちゃう”の。実際、気づいたらもう寝てるし、その後は絶対に付き合うし」
恭子さんは性欲が強いことを自認しているけど、「誰でもいいからセックスしたい」というわけではないそうだ。性行為をしたくなるのは、あくまで身体にドカンときた相手。そして、その相手は自分の意思では選べないという。
「誰にドカンとくるのか、自分でもわからないの。相手が外国人だったり、障害のある人だったり、既婚者だったり……。自分でも『えっ、この人⁉』ってビックリすることがあるの。ドカンとくるかどうかは私の身体に聞いて?」
そう言って、恭子さんは豪快に笑った。
■色欲によって不幸な恋をしてきた
恭子さんが初めて「身体にドカンときた」のは大学二年生のとき。
たまたま入った写真のグループ展で、あるひとりの作品に目が釘付けになった。どうしても感動を伝えたくて、感想と自分の電話番号を書いたメモをギャラリーの人に託した。
しばらくしてその写真家の男性から電話があり、新宿で待ち合わせた。彼と会った瞬間、ドカンときた。心臓を強く殴られたような、体中の血が沸騰するような感覚。
彼とはすぐに恋人同士になった。当時の彼は売れない写真家で、とても貧乏だった。恭子さんは彼の作品がいかに素晴らしいかを伝え続け、精神的に支えていたという。その後、大学を卒業して一流企業に就職した恭子さんは、経済的にも彼を支えた。
彼はどんどん世間に評価されるようになり、売れっ子になった。しかし、5年付き合った後、恭子さんは彼に振られた。
その後も彼女は、欲望の赴くままに恋をした。相手はヒモだったり、離婚した元妻とずるずる付き合っている男だったり。友達には「ダメンズばっかり」と呆れられる。
「しょうがないのよ。この人と恋愛しても幸せにはなれないって、頭ではわかってても、身体が勝手に相手を選ぶんだから」
恭子さんは恋人がいない時期がなく、恋愛遍歴は実に華やかだ。けれど、相手を献身的に支えるものの、最終的にはさよならを告げられる。
■色欲の根底にある自己肯定感の低さ
彼女は自分の恋愛と色欲を誇りに思っているという。
「他人からすれば『痛い目に遭ってる』ように見えるかもしれないけど、付き合ってるときはお互いに愛し合ってるし、別に搾取されてるわけじゃないもの。後悔はひとつもない」
そう言うものの、彼女は何度か意識を失って緊急搬送されたことがあるそうだ。医師には「ストレス」と診断されたという。支えるばかりの恋愛により、知らず知らずのうちに磨耗していたのではないだろうか?
私がそう尋ねると、彼女は少し考えて「たしかに、今思うとそうかもね」と言った。
「でも、私にとって恋愛は人生の核だし、色欲は人生を動かすエネルギーなの。恋愛とセックスがあったから、がむしゃらに頑張ってこれた」
恭子さんは自他共に認める頑張り屋だ。難関大学に合格して、一流と言われる企業に就職。その後は20年以上も激務をこなし、結果を出し続けている。子どものときからずっと「頑張り屋」と評されてきた。
「頑張ってない自分には価値がないって思ってたから。だからこそ、頑張り続けてきたの」
自分の価値を認められなかった原因は両親にある、と彼女は話す。
子どもの頃から、どれだけ頑張っても褒めてもらえず、できないところばかりを叱られた。親に認められたかった恭子さんは、勉強でも他のことでも、すべてにおいて努力してきた。けれど、親だけはどうしても認めてくれなかった。
そんな彼女にとって、人生を頑張り続けるためのガソリンが色欲だったのだろうか。
「そう、まさにガソリン。私にとっては必要で、大切なもの」
恭子さんは何杯目かのウイスキーを飲み干した。
■セックスレスでも満たされている
40代になった恭子さんは、趣味を通じて出会った10歳年下の男性と結婚。今は色欲を失っていると話す。
そのきっかけは、心の調子を崩して休職したことだった。
「ある日、急に視界に黒い靄がかかって目が見えにくくなったの。眼科に行っても異常が見つからなくて、産業医には過労が原因で鬱になりかけてるって言われて。すぐに復帰するつもりで休職したら、起き上がれなくなっちゃった。そこでようやく、自分が疲れてたことに気づいたの」
休職は2年に及んだ。夫のサポートもあり、彼女は2年の歳月をかけて少しずつ回復し、職場に復帰した。けれど、一度失った色欲は戻らない。
「あれほどの性欲がね、今は枯渇してる。この私がなんとセックスレス……って、笑っちゃうでしょ」
そう言って、恭子さんはおどけた表情を見せる。
「でもね、セックスレスが不幸なことだとは思わない。お互いに愛してるもの。セックスしなくてもすごく満たされてる」
それを聞いて疑問に思う。恭子さんにとって、色欲は生きるエネルギーだったはず。エネルギーが枯渇したにも関わらず満たされているとは、いったいどういうことだろう。
そう尋ねると、彼女は「あれ? ほんとだ」と目を丸くした。そして、首を傾げて考え込む。しばらく沈黙が流れた。
もしかしたら、恭子さんは心から安心できるパートナーを得たことで、「頑張らなくてもいい」と思えるようになったのかもしれない。だから、頑張るためのガソリンが必要なくなったのではないだろうか。
そう考えを伝えると、彼女は真剣な眼差しで私を見つめた。
「……そういえば、いつの間にか『頑張らなきゃ』って思わなくなったわね。夫は鬱で寝込んでる私でも肯定してくれるから……」
彼女は一言ずつ、噛みしめるように言う。その横顔はとても幸せそうで、私もつられて暖かい気持ちになった。
恭子さんには、ずっと幸せでいてほしい。
ふいにそんな勝手な気持ちがこみ上げてきて、泣いてしまわないよう唇を噛んだ。

7人の女たち#1
どうせ食べるなら、罪悪感なく笑顔で食べたいじゃない
7人の女たち#2
「この人と恋愛しても幸せにはなれない」。なのに、身体が勝手に相手を選ぶ
7人の女たち#3
親になっても、自分のために怒っていいのだと思えた










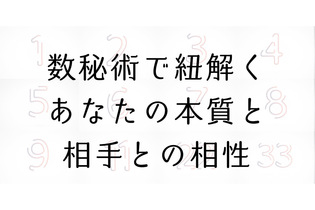










1983年生まれ。noteにエッセイを書いていたらDRESSで連載させていただくことになった主婦です。小心者。