ホテル街、赤ウインナー、ダンスホール──幻を見せる街「鶯谷」【夜を歩く 】
エッセイスト・生湯葉シホさんによる連載「夜を歩く」では、不思議な出会いがある東京の夜を描きます。ほんの少しの高揚感を胸に、異世界のような夜の街をご堪能ください。今夜紹介するのは、ラブホテルと霊園が共存する街「鶯谷」です。

初めて朝帰りをした日を覚えている。
空には裾のぼやけた入道雲が浮かんでいて、駅前のタクシープールは前の晩の賑わいが嘘のようにがらんとしていた。暑い日だった。
寝ているあいだにコンタクトが片方外れてしまったので、片目だけを頼りに駅を歩いた。そろそろと階段を降りていくと、ちょうど向こう岸のホームに電車が入ってきたところだった。山手線からスーツ姿の人たちが降りてくるのを見ていたら、ノーメイクでハイビスカス柄の浮かれたロンパースを着ている自分が突然ものすごく場違いに思え、恥ずかしくなった。
電車が去ったあとのホームには、スピーカーから流れる鶯の声が響いていた。
■ラブホテルと霊園が共存する街、鶯谷

夜の街を歩くこの連載が始まったとき、最初に歩きたい街として思い浮かべたのは鶯谷だった。人生で5回くらいしか降り立ったことのない場所だったが、その5回すべてが夜だったから、夜、イコール鶯谷というイメージが強かったのかもしれない。
鶯谷は不思議な街で、正確には“街”ではない。
というのも、鶯谷という名前はあくまで俗称で、行政上存在する地名ではないからだ(JR鶯谷駅の周辺は、地図上は根岸や桜木という地域にあたる)。江戸時代に鶯の名所であったことがその名前の由来らしいが、いまや鶯谷という地名は山手線の駅名としてしか残っていない。
鶯谷駅は、ラブホテル街と霊園に挟まれている。夜になると街の東側、ラブホテル街サイドだけにホテルのネオンが一斉に灯り、駅前には風俗店の待ち合わせ客がぽつぽつと立ち始める。平均乗車人員が山手線の中でもっとも少ない駅だというデータがあるとおり、週末の夜でも駅周辺が人で溢れかえるようなことはまずない。
率直に言って、“いかがわしい”イメージの強い街だ。だからこそ自分の足で改めて歩くことで、この街の知らない面に触れてみたいと思った。
■夏の夜、ホテル街を歩く
夜7時。鶯谷駅に着くと、南口の改札前には数人の男女がスマホをいじりながら立っていた。女性は皆若いひとたちで片手に小さな鞄やポーチを提げており、男性の多くは40代から60代くらいに見える。
大学生のころ、ホテル街の近くの喫茶店でカップルの会話に聞き耳を立てるのに凝っていた時期があり(本当に悪趣味です)、そのときに「目の前にいる男女が交際しているカップルなのか、金銭的なやりとりがあって一緒にいる人たちなのか」を見分ける力がすこしだけ上がった。
南口に立つひとたちをぼんやりと見ながら、たぶんこの中の7割くらいがデリバリーされる人たちとデリバリーする人たちの組み合わせだろう、と無責任な想像をする。
しばらくして犬柄のシャツを着た編集のOさんが来た。
王子のときもそうだったけれど、特にルートは決めていないのでぼんやりと歩き出す。
JRの線路にかかる橋を渡りながらOさんに「元気ですか」と聞いた。Oさんが笑顔で「ぜんぜん元気じゃないですよ」と言うので、たしかに、こんな暑さなのに元気な人のことは信用できないなと思った。
橋のたもとの階段を下り、ローソンのある狭い路地を左に曲がると、ホテル街の入口がある。ここを抜けて北口のほうまで歩いてみようと提案すると、Oさんは左右にそびえるカラフルなホテル群に圧倒されながらも頷いてくれた。
ホテルの立ち並ぶ通りは、通り抜けるだけでも独特の“圧”を感じる。噴水やシャンデリア、真実の口のレプリカといった突き抜けた装飾品は見ていて楽しいけれど、駐車スペースに無造作に積み重ねられたリネン類などにふっと目をやってしまうと、そのリアリティに急に緊張してしまったりする。

歩いていると、ホテルとホテルの間に時折、バーや居酒屋風の小さい飲食店を見つけた。
そういう場所にあるお店はさぞかしカップルたちで溢れかえっているのだろうと思いきや、「ホテル街の中にあるお店には意外とサラリーマンや常連さんしか来ないんですよ」と昔、某ホテル街で20年以上営業を続けているバーのマスターに教えてもらったのを思い出す。
マスター曰く、ホテルに入る前にわざわざすぐ近くのお店でお酒を飲むカップルは少ないし、ホテルを出たあとはすこしでも早くホテル街から出たいと思う人が多いからじゃないですか、ということらしい。
「OPEN」「FULL」の文字を横目に見ながら縫うようにホテル街を歩く。
すれ違った女性から日焼け止めのようなココナッツの匂いがして、ああ、夏の夜だと思った。
■ビールとホッピー、赤ウインナーで1杯
南口に着いて最初に目に入ったのが「信濃路」だった。
24時間営業の居酒屋として有名で、鶯谷といえばここ、と言う人も多いほどファンの多いお店だ。
1杯やりましょうかと話して、駅の目の前に建つ信濃路に入る。
赤ウインナーと牛すじ煮込みに、私はビール、Oさんはホッピーを頼んで、カウンターで飲んだ。隣のサラリーマンが食べている炒めもののような料理が美味しそうで気になったが、ちょっと強面の人だったので、なんですかそれと聞く勇気がなかなか出ない(結局最後まで出なかった)。
夜もまだ浅いというのに店の中は賑やかだった。なんの肴もなしに瓶ビールをどんどん空けていく40代くらいの男女のグループや、近くの女性に熱心に声をかけては無視され続けているおじさん、「あそこに美人がいる! 隣にイケメンもいる!」とハイテンションでほかの客の容姿を褒めまくる若いカップルなど、文化祭の日のような異様な熱気に満ちている。
ふとカウンターの奥に目をやると、厨房の中では外国人の店員たちがせわしなく、無表情で鍋を振ったり皿を洗ったりしていた。たまに注文の声が客からかかると、「ハイ」と顔も上げずに言ってまた各々の作業に戻る。
カウンターの向こうとこちらがまるで違う世界のようで、それぞれを交互に見続けていたらすこし混乱した。
■都内に2軒のみとなった「ダンスホール」へ
鶯谷にダンスホールがあるらしいんですよ、と話すと、へーいいじゃないですか、とOさんは言った。
その軽いひと言で、ダンスのことなどなにも知らない素人がそんなところに入っていっていいのか、という迷いは驚くほどシュッと消えた。
「ダンスホール新世紀」というその店は、半世紀近い歴史を持つ都内随一のダンスホールらしい。
ダンスホールというのはいわゆる“社交ダンス”をするための場所で、華やかな音楽(時には生バンドによる演奏)のもと、男女がペアで自由に踊ることができる。
一時期は東京にも多くのダンスホールがあったというが、いまはもう東京にもたった2軒を残すのみで、そのうちの1軒が「ダンスホール新世紀」だ。
酔いも手伝ってか、行ってみましょうと簡単に話が決まり、その店を目指すことになった。ダンスホールなるものはもちろん、社交ダンスをする人たちの姿を見てみたいという純粋な好奇心が私たちを衝き動かしていた。

■異世界の中で踊る人を見る
南口からほど近くに「ダンスホール新世紀」はあった。ビルの狭い入口を進んでエレベーターに乗り、「ラウンジ」と書かれた3階のボタンを押す。
ドアが開くと、まず右手に衣装ラックにかかったきらびやかなドレスが並んでいるのが目に入った。
左手のカウンターには黒いベストに蝶ネクタイをつけた女性が立っている。
踊らなくても入って大丈夫かと女性スタッフに聞くと、テーブルチャージはかかるが、ラウンジの利用なら誰でもOKとのこと。
案内されて奥に進んでいくと、ベルベットのような布張りのソファ席がガラスの周りを囲むようなコの字型に並んでいるのが見えた。
ソファ席には入口で見た華やかなドレスやスラックスできめた男女が集まり、シャンパンやビールをワイワイと飲んでいる。
席に近づいて初めて、ガラスの向こう側が吹き抜けのホールになっていると気づいた。ガラス越しにホールを見下ろすと、吹奏楽のバンドが演奏をする舞台のその下で、5組ほどの男女が手を握り合って踊っている。
目の前に広がる光景があまりに非日常そのもので、しばらく無言でガラスの向こうを凝視することしかできなかった。
向かいに座ったOさんが急に笑い出すのでどうしたのと聞くと、「ちょっとあまりに非日常で」と私が思っていたのとまったく同じことを言う。この異世界に早く体を慣れさせなくてはと思って、ビールをふたつ頼んだ。
舞台の上方、ラウンジと同じ高さに小さなステージがあり、そこで女性のボーカルがブルースを歌っていた。
眼下に広がるダンスフロアでは、ブルースに合わせて男女がステップを踏んでいる。天井から降り注ぐミラーボールの光がダンスをする人たちに時折重なっては、その姿を明るく浮かび上がらせる。
フロアをずっと見ていると、自分がひとりの女性を目で追いかけていることに気づいた。
50代後半くらいだろうか。白髪をボブカットにして、タイトな黒いドレスで踊っている。
彼女が舞台のほうを向くたびに、大胆に空いたドレスから引き締まった背中が見えた。その様子はセクシーというよりも健康的で品があり、彼女がダンスの最中怒っているのかと疑うほどに真剣な顔をしていたことも相まって、強く目を奪われた。
「男性は黒子みたいですね」とOさんが言うとおり、フロアで踊る人たちの主役は完全に女性なのだった。
ペアで踊る男女は、ダンスが巧ければ巧いほどふたりでひとつの生き物のように見えたが、男性がステップを踏んだり女性の歩みをリードしたりする役目を担っているのに対し、女性は踊りのうちの美しさや激しさを一身に担っているかのようだった。
■女性たちの踊り方は一人ひとり違う
もっと近くでダンスが見てみたい、とワガママを言い、ダンスフロアのある2階に降りた。フロアの端にあるバーカウンターの前に移動して、ふたたびビールを飲む。
目の前にすると、3階から見ていたときよりずっとダンスは迫力があった。熱心にステップを踏み続けるペアもいれば、2,3分ごとに離れて互いの動きを確認し合うペアもいる。
ひと組ひと組を目で追っていたら、女性たちの踊り方は一人ひとり違う、という当たり前のことに気づいた。ステップや動きという技術的な話ではなく、なんのために踊っている(ように見える)か、という話だ。
ある若い女性は、見られている自分の姿を強く意識しているかのように、終始笑みを絶やさずに踊っている。
おそらく夫婦でペアを組んでいる別の女性は、相手の男性と会話をしながら楽しげに踊っている。
そして、最初に目を奪われた白髪の女性は、所作の中にある美を一心に追求しているように見える。
バックミュージックがスローワルツからタンゴに変わっても、動きのテンポが変わるだけで、彼女たちの表情や踊り方はほぼ変わらない。いま自分が見ているものは単なる踊りではなく、彼女たちそれぞれの美学なのだという気がした。
風船のように膨らんだりぱっと閉じたり、あるときは翻ったりする色とりどりのドレスを見ながら、いつか私も急に踊りたくなったりするんだろうか、そうなったときのために素敵なドレスを1着くらい買っておこうか──と思った。

ダンスホールのエレベーターを降りると、外はやはり昼間のように暑かった。
駅に向かって歩き出すと、往来を行く人たちの服装や会話から2018年のリアリティが一気に感じられ、たったいま見てきた光景はすべて幻のように思えた。
駅のホームでOさんと別れて、山手線を待っていた。
頭上のスピーカーに気づき、そこから昔聞いた鶯の声が聞こえないかとしばらく待ってみたが、結局電車が来るまでなんの音もしなかった。
蒸し暑いホームに立ってホテル街のネオンを見ながら、今日の出来事が最初から最後まで夢だったとしても驚かないな、とふと思った。
参考文献:本橋 信宏『東京最後の異界 鶯谷』(宝島社)
取材場所:信濃路 鶯谷店
取材場所:新世紀ダンスホール







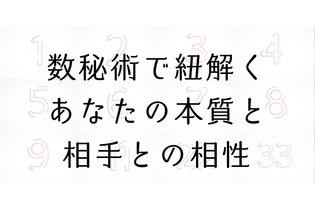










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。