思い出さなくていいことばかり思い出してしまう。因縁の街「江古田」【夜を歩く】
エッセイスト・生湯葉シホさんによる連載「夜を歩く」では、不思議な出会いがある東京の夜を描きます。ほんの少しの高揚感を胸に、異世界のような夜の街をご堪能ください。今夜紹介するのは、生湯葉さんにとって“三軍の思い出“があふれる街「江古田」です。

ただ歩いているだけで、思い出さなくてもいいことばかり思い出してしまう街がある。
たとえば、そのうちのひとつは池袋で、飲みの約束などをしてとろとろと東口を歩いていると、キャッチのお兄さんの頼みを断わりきれずに出会い喫茶のサクラをやっていた4年前のことだとか、某商業施設のインフォメーションのバイトをしていたとき、どの指も綺麗なのに「怪我したので絆創膏を巻いてください」と受付までやってくる謎の老婆がいて恐かったことだとか、記憶の引き出しの中の永遠の三軍みたいなエピソードばかりが次々と浮かんでくる。
だからできれば正直あまり行きたくないのだけど、そういう街にはなぜか、仕事や付き合いなどで「絶対に行かなきゃいけない用事」が頻繁に発生し、結局は事あるごとに足を運ぶことになってしまう。
これは街と自分との腐れ縁のようなものだと思っていて、私にとっては「江古田」も、そういう街のひとつだ。
■すべての江古田関係者に通じる「魔法の言葉」
江古田の大学に通っていたと人に言うと、「江古田って『エコダ』ですか『エコタ』ですか」とよく聞かれる。
そのたびに気分で「たぶんエコダですよ」、もしくは「エコタですよ」と答えていたのだけれど、今回これを書くにあたって調べてみたら、正式な地名は「エゴタ」と読むのだと知って度肝を抜かれた(「アボカド」に近い難易度だと思う)。
江古田は東京の中野区に属する街で、その大部分が住宅地から成る。武蔵大学・武蔵野音楽大学・日大芸術学部の3つの大学のキャンパスがあるので一応は「学生の街」ということになっているのだけれど、たとえば高田馬場のような賑やかさはなく、よく言えば落ち着いた、悪く言うなら地味な街だ。
私の通っていた日大芸術学部は、西武線江古田駅から徒歩1分の場所にある。大学時代は(いまもだけれど)付き合いの非常に狭いタイプだったので、同じ学部出身の人に仕事などで出会って「〇〇先生はまだ元気?」などと聞かれるといつもオロオロしてしまう。
けれど、どんな世代の江古田関係者にも通じる魔法の言葉がある、ということに最近ようやく気づいた。
それは、「そういえば、江古田コンパはまだありますよ」だ。
■江古田の地で50年営業を続ける謎の「コンパ」
夜、江古田駅の改札の向こうに編集のOさんの姿が見えたとき、妙にホッとした。その理由は、「三軍の思い出」だらけの街を、学生時代の自分をよく知る人と歩きたくなかったからということに尽きる。
別に当時のことを思い出したくないというわけではなく、江古田の街を歩く隣に学生時代の友人がいたら、過去の出来事を細部までリアルに思い出して突然泣いたりしてしまいそうで、それが嫌だった(私は急なノスタルジーにものすごく弱い)。
Oさんと並んで駅の階段を下り、商店街を歩きながら、余計なことを思い出さなくていいよう過剰に喋った。夜の風は生暖かく、いままさに自分たちは夏の折り返し地点にいて、今晩を境に秋に向かってゆくのだという気がした。

目的地の前に着いて「ここです」と言うと、Oさんが「大丈夫なところですかここ」と言った。江古田コンパ、というぎらついた文字の看板と、その下に掲げられた「女性は夜10時まで半額」という怪しげな惹句を目にすると、100人中100人がそう言う。
「わからないけどたぶん大丈夫です」と答えると、Oさんは何度かためらいながらも店に続く階段を上がってくれた。
江古田コンパは、その名の通り江古田の地で50年営業を続けている「コンパ」だ。コンパ、というのは安価で本格的なカクテルを出す店の一業態のことで、昭和の中期にはお酒の飲める夜の店として、スナックやバーと並ぶメジャーな存在だったという。
かつては日芸出身の有名人も足繁く通った店だという話はよく聞いていて、学生時代にも行ってみようとしたことは何度かあった。けれど、そのたびに入り口のなんとも言えないギラギラ感に圧倒されてしまって、絶対一度は行ったほうがいいところだという予感を抱えながらも中には入れないまま、大学を卒業してしまっていた。
■かき氷のシロップのようなカクテル

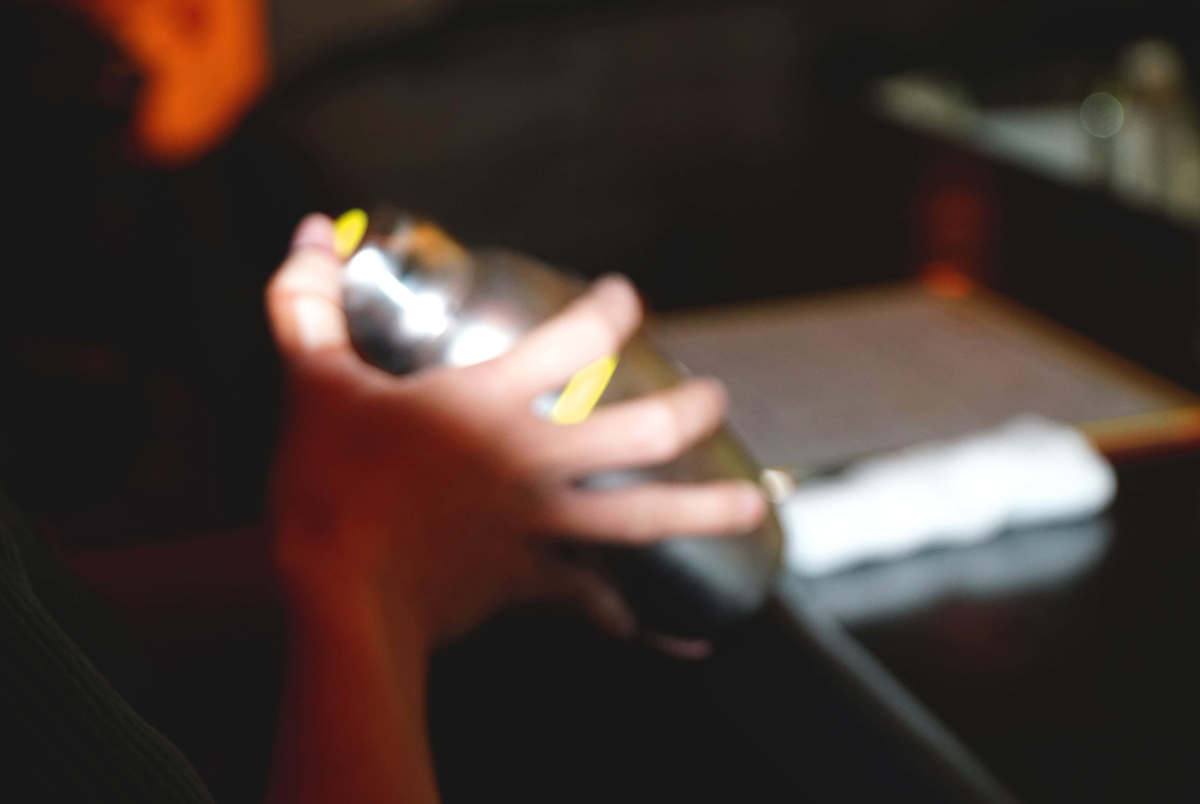
いざ足を踏み入れた江古田コンパは、拍子抜けするほどにフレンドリーな空間だった。
赤い絨毯のフロアの両側にずらりと並んだカウンターには最初すこし威圧感を覚えたけれど、その中に立つママの明るさが恐い店という印象を一瞬で払拭してくれた。
「初めてですよね? ホラ、そんな重そうな荷物その棚に置いてこっちいらっしゃい!」と声をかけられて言われるがまま席に着くと、膨大な数のカクテルの名前が書かれたメニューを手渡される。
そのどれもが600円、700円という良心的な価格設定で、しかも女性は10時までならカクテルが半額だと念を押された。これは飲んじゃうやつだな、とすぐに悟って、1杯目は度数が低めのカクテルを注文する(Oさんは最初から30度くらいのやつを頼んでしまって項垂れていた)。
ママは終始朗らかに江古田コンパの歴史や江古田という街のことについて話してくれ、私が日芸出身だと言うと「あら、野田さん(学部長)は元気?」と聞いてきた。本当にこの街に根づいている店なんだなと思って、学生時代に来なかったことをしばし後悔した。
何枚かあるメニューのひとつにふと目をやると、「創作カクテル」という文字がある。
聞けば、数十種類のリキュールやシロップの中から3種類を自由に組み合わせて、オリジナルのカクテルがつくれるのだという。ほどよく酔ってきたこともあって、それを注文してみた。
決して夏らしい日ではなかったけれど、夏の夜にこの店に来たという証明のようなものが欲しかった。
ラムとココナッツリキュール、ブルーリキュールを選んで見よう見まねでシェイカーを振り、その中身をショートグラスの中に注ぐ。

できあがったのは、想像よりも綺麗な青色をしたカクテルだった。ひと口飲んでみると、かき氷のシロップのような甘ったるい味がした。
創作カクテルにはオリジナルの名前もつけられるのだけど、どんな名前にしたかは恥ずかしいのでここには書かない。Oさんもオリジナルカクテルをつくっていたけれど、名前は教えてくれなかった(編集者とライターがネーミングのセンスを明かし合うというのはなかなかリスキーだから正しい判断だったと思う)。
■夜の江古田を歩き回りながら、怒っていた
9時ごろ、店には私たちのほかに、60代くらいの男性客がいた。
何杯か飲んでOさんと互いの近況などを話していると、その男性客が声をかけてきた。「結婚してるの」と聞くので、「私はしてます、Oさんは独身です」と答える。
「なんでしないの」と言う男性客にOさんが「いい人がいたら」と答えると、「駄目だよ早くしなきゃ、男は結婚して初めて一人前になれるんだから」という言葉が返ってきた。
そのムードがちょっと説教じみていたので嫌だなあと思いつつお茶を濁していると、男性客の言葉はどんどんヒートアップしていく。
結婚しないでフラフラしてるのは甘えだよ、と言われたとき、Oさんが穏やかな口調のままで、「それはちょっと古い考えだと思いますけどね」と口にした。
思わずハッとして、隣に座るOさんを見る。彼はいつも通りの顔で真っ直ぐに男性客を見て、「結婚って必ずしもしなきゃなんですかね」と首を傾げていた。
男性客はしばらくのあいだ、Oさんに絡み続けた。
その日、Oさんにはもともと用事で早く帰る予定だと言われていた。10時ごろに改札前で解散したあと、私はひとりであてもなく江古田の街をぶらぶらと歩いた。
予想していたとおり、江古田を歩いているとあまりにもさまざまなことを思い出してしまうのだった。
大学時代に1年だけ所属していた軽音楽部のライブを近くのライブハウスでやったこと、そのとき同じバンドだったボーカルの女の子がヒョウ柄のスキニーばかり履いていて「亀甲」というあだ名だったこと(新歓のときの一発芸で亀甲縛りをしたことが由来だった)、私だけが彼女のことをなぜか名前で呼んでいて、私が軽音楽部を辞めると明かしたときの飲み会で「いなくならないでよ」と言われて、一緒になってワンワン泣いたこと。
部活帰りに何度も寄ったマクドナルドの前を過ぎ、バンドの先輩によく連れてきてもらったラーメン屋の前を過ぎても、行くべき場所が見つからなかった。
夜の江古田を歩き回りながら、私は怒っていた。
もちろんOさんにではなく、彼に絡んできた男性客にでもなかった。
あのとき、なにも口を出せなかった自分にだ。
江古田駅の階段を上がりながら「ああいう自分の価値観で他人を抑圧しようとする人と闘っていかなきゃいけないと思うんです。しんどいけど」と言ったOさんと、その横で「いい店だったのに、すみませんほんと」としか言えなかった自分のことを思い出していた。
私はあの男性客に対して、きっと苛ついていた。結婚しないのは甘えだなどという暴言に対して、そんなことないでしょうとすぐにでも言ったほうが良かったのかもしれない。それでも「まあ、ニコニコしてりゃこの場が凌げるだろう」と一瞬でも思った自分が、あまりにも情けない。
めちゃめちゃだせえじゃん、と頭の中で繰り返しながら小路をさまよっていたら、「Blues Bar」と書かれた小さな看板のある店を見つけた。
店名も見ず、反射的にそこに入った。
■「下手なのは知ってるっつうの」
店の中は狭かった。薄暗い数席のカウンターの横で、ギターとボーカルの男女がブルースを演奏していた。
カウンターには先客の女性がいて、缶のままのオリオンビールを飲みながらその曲に合わせて体を揺らしている。演奏の途中で座っていいものか迷っていると、カウンターの奥から無造作に髭を生やしたマスターが顔を覗かせて「キャッシュオンだから、その冷蔵庫からなんでも好きなのとってきな」と言った。
それは愛想のある言い方ではなかったけれど、「あ、いい店だ」と思って嬉しくなる。冷蔵庫を開けていちばん前にあったチューハイを手にとり、すぐにカウンターの前の木の椅子に腰かけた。
何曲か知らない曲の演奏が続いて、終わるたびに拍手をしながらそれを聴いた。ライブが終盤にさしかかったとき、不意に先客の女性が「あたしもなにか弾こうかな」と言い出した。
マスターは「奥にキーボードあるけど、セッティング自分でしてくれるならいいよ」と言う。明らかに酔っている女性客の挙動が心配になって、思わず奥の機材倉庫までついていった。
彼女を手伝って黒いカバーの楽器を開けると、KORGの電子ピアノが出てきた。
本当に弾いてもいいのかと思ったけれど、マスターはカウンターから「それけっこう高いんだから壊さないでよ」と声をかけたきり、なにも言ってこない。
セッティングに迷っている女性客の後ろで、カバーのポケットの中に入っていたペダルとケーブルをピアノに繋いだ。
「楽器やってるの?」と彼女に聞かれて、ギターでした、いまは弾けないけどと素直に答える。「じゃあお姉さん歌ってよ!」と言われて、困ってしまった。
演奏者のふたりが手元の楽譜をめくりながら、「なになら弾けます?」と女性客に聞いた。彼女がぱらぱらとそれをめくって1曲を指差し、スティービー・ワンダー「Isn't she lovely」の即興セッションが始まる。
ところどころ止まりながらも続く演奏に体を揺らしていると、「お客さんはなにか弾かないの」とマスターがカウンター越しにこちらを見た。
「いや、ほんと下手なので」と断ると、マスターは「ここに来る人みんな『下手なんで』って言うのよ」と笑う。
「でもさ、こっちはプロの演奏死ぬほど見てきてんのよ。下手なのは知ってるっつうの」
結局、私はそのあと調子に乗って何曲かその下手な歌を歌ってしまった。
演奏者のふたりも、女性客もマスターもみんな酔っていて、「お姉さんの歌いいじゃん」と言ってくれた。もちろん本音じゃないとわかっていたけれど、それはその夜に聞いた言葉の中でいちばん嬉しかった。
酔いに任せて直後に来た常連客とも打ち解け、彼らが秋にやるというライブにも行く約束をした。
帰り道、ふらつく足どりで西武線を待ちながら、iPodで好きなバンドの曲を聴いていた。ここは地獄でも天国でもなく、ちょうどそのミシン目のような場所なんだとそのバンドは歌っていた。
すべての場所がきっとそうだ、と不意に思った。私は好きでも嫌いでもない、けれど縁の切れない江古田という街に、たぶんそう遠くないうちにまた来てしまう。







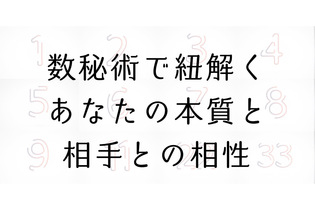










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。