余命2年のスナックで──王子「さくら新道」【夜を歩く】
エッセイスト・生湯葉シホさんによる連載「夜を歩く」では、不思議な出会いがある東京の夜を描きます。ほんの少しの高揚感を胸に、異世界のような夜の街をご堪能ください。今夜紹介するのは王子駅から徒歩3分ほどの場所にある「さくら新道」です。

陶酔が、流行らなくなっている。
気がつけばみんな「自然体」とか「日常」が好きで、背伸びしたものや非日常的なものは、やさしく黙殺されるようになってしまった。
格好つけた俳優は流行らないし(菅田将暉は例外として)、身の丈に合わない振る舞いやファッションはダサいとされる。SNSにほんのちょっとドラマティックなエピソードを書けば、嘘松、と秒速でリプライが飛んでくる。
映画やライブは簡単に“陶酔”させてくれるイベントだけれど、お金がかかるし、なにより毎日毎週そういう場に足を運ぶのは難しい。お酒や煙草や恋愛で陶酔できるのも、いまはもう、ほんの一部の人たちだけだ。
でも、と思う。
なににも酔わないでいつも素面でいるのは、ちょっとだけ寂しい。
せめて1日のうち、たとえば夜の数時間くらいは、季節に、人に、あるいは自分に、陶酔してもいいのではないか。
10代のころ、目的もなく夜の街を歩いて感じたあの高揚や全能感を、大人になったいま、恥ずかしげもなく追い求めたい。
だから私は、夜の街を歩いてみることにした。
■夜に1軒だけ残ったスナックを訪ねて「さくら新道」へ
夜8時、メトロの王子駅で降りると、先に着いていた編集のOさんがスヌーピーのTシャツ姿で現れた。ひと言ふた言話してすぐに、「ええと、どうしよう」みたいな空気になる。その夜、「さくら新道」をめざして歩くということ以外は、なにも決めていなかった。
さくら新道は、JR王子駅とその目の前にそびえる飛鳥山公園のあいだに挟まれた、木造長屋の呑み屋横丁だ。戦後すぐに建設されたごく狭い通りで、駅の線路と平行にすっと伸びている。
王子駅のある北区の隣、板橋区出身の私は、幼稚園や小学校の遠足で何度か飛鳥山公園に来たことがあったのだけれど、さくら新道の存在には大人になるまで気づかなかった。……と、いうくらい、目立たない道なのだ。夜になると、人とすれ違うこともほぼない。
2012年に火災が起き、さくら新道の長屋は、3軒あったうち2軒が全焼してしまった。
連なっていた呑み屋も火災の影響で店を閉めてしまい、いま営業しているのは「まち子」というスナックただ1軒だけという。その話を聞いて、どうにかしてお店が開いているうちに行きたい、と思った。
■さくら新道を通って、飛鳥山公園を歩く
JRの駅に着くと、目の前に「さくら新道」と書かれた背の高い看板が立っていた。

おそるおそる路地に入ってみると、街灯の少ない通りは暗く、足元さえよく見えない。
靴の裏がやけに滑るのは散った桜が一面に落ちているからだと気づいたのも、歩き始めてしばらくしてからだった。
右手に飛鳥山、左手に線路を見ながら、あてもなく足を進める。
ちょっと飛鳥山公園をぶらぶらしてみませんか、という提案にOさんが乗ってくれたので、公園に入れる道を探しながら散歩することにした。
さくら新道を進み続けると突き当たりに坂があり、その坂を上ると大通りに出た。暗闇の中、円を描くように公園の外周を歩く。
途中、道の左に小さな建てものの灯りが見えたので目を凝らすと、中で喪服姿の男性たち何人かがせわしなく立ったり座ったりしながら話していた。葬儀場だ。部屋の奥のほうには白い花が並び、手前に故人の写真が飾られている。
ふと、「ラブホテルの隣に葬儀場ができ明るいほうが人のいる場所」という虫武一俊さんの短歌を思い出した。ここでは逆で、人のいる場所のほうが暗く、死者のいる場所のほうがはるかに明るかった。
昔、どういう理由があったのか知らないが、実家の1階部分を母が近所の葬儀屋さんに貸していたことがある。夜中に急に電話がかかってくることもある仕事だから、事務所になった1階の電気はいつもついていた。帰り道にその灯りを見るたびホッとしていたときのことがふと蘇り、懐かしくなる。
葬儀場のほうを見ながら、Oさんが「母親がね、『私が死んだら桜の木の下に骨を埋めてくれ』って言うような人なんですよ」と言った。
Oさんの母は、絶対にお墓には埋めてほしくない、自然のあるところで眠りたいとおっしゃっているという。Oさんが続けて「この前母と会ったときは『空から海に骨を撒いてくれ』って言ってました」と話すので、喪服で骨壷を持って颯爽とヘリコプターに乗り込む彼の姿を(不謹慎だけれど)すこしだけ想像した。
それから、私はどこがいいかとちょっと考えてみて、たしかに桜の下は素敵だけど、虫多そうで嫌かもと思った。
■缶ビール2本の小さなお花見
公園の入り口はほどなくして見つかった。近くのコンビニで缶ビールを2本買い、中に入る。
しばらく歩くとアスレチックの広場があった。
遊具の周りでは大学生のサークルと思しきグループがレジャーシートを広げ、花見を兼ねた新歓をしていた。自己紹介で順番に立ち上がる女の子たちを見ながら、自己紹介ってなんでなくならないんですかね、という話をした。
繰り返される自己紹介とまばらな拍手を横目に見ながら、子どものころ大嫌いだった鉄棒に掴まってみる。
小学校の夏休み、実家の裏の公園で、母に毎日逆上がりの練習をさせられたことを思い出した。結局一度もできず、途中から諦めてブランコで本を読みはじめる私に、母はよく「あんたは運動ができないことで落ち込まないからすごい」と言った。たしかに、一度も落ち込まなかった。
広場の真ん中のベンチに座って、Oさんと缶ビールを飲んだ。
その日、私は足元まである長いスプリングコートを着ていた。コートが地面について土まみれになっていくのを見ながら、いつかの春、同じ時期に同じコートを着て、新宿のゴールデン街で飲んだことがあったのを思い出した。
雨があがったばかりの日で、その夜もコートは土でぐしゃぐしゃだった。好きだった人を呼び出して一緒に飲んだことや、そのとき店の中でポルノの「サウダージ」が流れていたことまで急に思い出し、広場の端にあるSLをぼんやりと見ていた。
なにかを見て、急になにかを思い出すことってありますかとOさんに聞くと、「僕けっこう、見なくても思い出します」と言う。なにそれ、毎日めっちゃ大変じゃないですかと思わず声が大きくなった。
■2020年にはなくなるスナック「まち子」へ
さくら新道に戻り、「まち子」に入ったのが9時半だった。

中の見えない扉をちょっとびびりながら開けると、センター分けのボブヘアがよく似合うママが、いらっしゃいと声をかけてくれた。先客はいない。ママが下手に愛想よく笑顔をつくったりしなかったことに、なんだかホッとした。
お店はカウンター中心で決して広くはないが、圧迫感のある狭さではなかった。まち子ママが立っているカウンターの向こう側にずらりと並ぶキープボトルが、さくら新道の「最後の1軒」が現役で愛されていることを物語っていた。
まち子ママは私とOさんが席につくなり
「ここね、来年の3月まではやれるのよ」と言う。
すこし前、役所で店の営業の契約更新をしてきたのだそうだ。
「1年契約なんだけど、また次も更新しようと思っててね。でも、オリンピックで、どっちみち2020年にはなくなっちゃう」
ハイボールを注文すると、開けていないウイスキーの瓶とソーダをどん、と出してくれた。ちょっとどうかと思うくらい濃い目にハイボールを作っても、好きに飲んで、とママはニコニコしている。出してもらった野菜の浅漬けが絶品でそればかりかじっていたら、「だんだん野菜も安くなってきたよね」とママが言うので、冬のあいだ本当に高かったですよね、特に白菜、とひとしきり盛り上がった。
カラオケもありますからね、と言われたころにはすっかり酔いが回っていた。同じく酔ったOさんが「糸」を歌い出すと、ママがすかさずタンバリンを手渡してくる。振ると7色に光るギミックがやけに凝っていて馬鹿馬鹿しく、叩いたこともないタンバリンをゲラゲラ笑いながら鳴らし続けた。私が表拍でタンバリンを叩くと、ママが裏拍を入れてくる。
シャン、シャン、シャン、とスローペースで絶え間なく鳴り続けるタンバリンを、Oさんは見ないようにしていた。
歌い終えたあとに「そういうの絶対にやらない人でしょう、なにしてるんですか」と言われ、恥ずかしさで爆笑してしまう。
ママがOさんを見ながら、「やっぱり顔が格好いいとなに歌ってもいいわよね。これで顔が出川だったらちょっと違うわよね」と身も蓋もないことを真顔で言った。

私はハイボールを、Oさんは瓶のビールを、カウンターに並んでだらだらと飲み続ける。
沈黙が生まれると、ママがすぐさま口を開いてなにか喋ってくれた。おしゃべりな人と言うよりも、たぶん、店に立っているあいだは喋ると決めているんだろうなと思った。
ママは、「まち子」にかつてたくさんのフロアレディがいたという話や6年前の火事のことを滔々と語る合間、ふと思い出したように、でも昔はお店開けるのが怖かったのよ、と言った。
隣にある飛鳥山公園で寝泊まりをするホームレスの人や、たちの悪い酔っぱらいが、お金を持っていないのに入ってきてしまうことがあったのだという。ママは、「だからあたし昔はずっとお店に鍵かけてたんだけど、いまはもういい常連さんしか来ないし、開けっぱなしにしてるの」と言って、手元のお酒を静かに飲んだ。

ママの顔を見ていたら、いいお店はいつも扉を開けている、という誰かの言葉が頭をよぎった。
もちろん、限られた人にしか扉を開けさせないことでお店の品格みたいなものを保っている名店もたくさんある。けれど、いつも扉を開けているお店は、私の知る限り例外なくいいお店だ。
「あの葉が落ちるまで私は死なない」と1枚の葉っぱに希望を託す人が出てくる小説があったけれど、たぶん、お店も同じなのだと思う。
自分にとってどんなにだめな日でも、あそこが開いてるなら大丈夫、あの人がカウンターに立ってるなら大丈夫、と思えるお店がある。「まち子」は、たぶん私が想像するよりはるかにたくさんの人にとって、きっとそういうお店なんだろうと思った。
顔色ひとつ変えず、いつの間にかお酒を飲み終えたママが、「こうやってお店やってるとね、生きてるって感じがする」と言うので、「いいなあ」と馬鹿みたいな返事をした。
本心だったし、カウンターに立っていないときのママがどんな人なのかは知るよしもないけれど、この人はここに立っているときがいちばん綺麗なんだろうと思った。
11時半、コートを着て店を出た。
深夜だというのに風は生ぬるく、酔った体が冷えることはなかった。さくら新道は短いので、振り返る間もないほどあっけなく駅に着いてしまう。ディズニーランドからの帰り道、京葉線に乗った瞬間“日常”にチューニングを合わせなくてはいけなくなる、あの感覚を思い出した。
Oさんと別れ、ホームに向かって歩き出すと、ロングコートの影が駅の階段に映った。私はその大きな影を踏んづけながら、上機嫌で1段ずつ階段を上った。黒い靴は気がつけば公園の砂で真っ白になっていて、濡れて縮んだ桜の花びらがつま先に1枚だけついていた。
電車の中でそっとそれを剥がすと、靴に花びら型の跡が残った。
翌朝家を出るときも、跡はなかなか消えなかった。








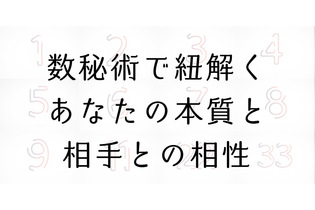










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。