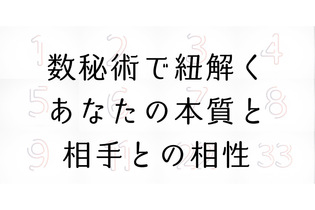わたしたちは、氷砂糖をほしいくらいもたないでも、きれいにすきとおった風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。(中略)わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾きれかが、おしまい、あなたのすきとおったほんとうのたべものになることを、どんなにねがうかわかりません。
その音は、何色?――「共感覚」という感覚
色は目で見るもの、音は耳で聞くもの、味は舌で感じるもの、とされていますが、色を味わったり、音にさわったり、文字に色彩を感じる「共感覚」と呼ばれる感覚があることをご存知ですか? 共感覚の持ち主である島本薫さんは、この感覚をより多くの人たちに知ってもらいたいという想いから、幼少期のエピソードも交えて詳細に語ってくれました。

こんにちは、島本薫です。
樹々の緑や空の青さ、光と色彩のあふれる季節になりましたね。
「風薫る」という言葉もあるこの季節。本日は、風に色を見たり、色に音が聞こえたりする「共感覚」という一見不思議な現象について、当事者の目からお伝えできればと思います。
■色を聞き、音を味わう――「共感覚」とは
これは、宮沢賢治の『注文の多い料理店』の序文です。
透き通った風を食べる、桃色の朝の光を飲む――賢治の詩人としての感性があふれた美しい言葉ですね。でもそれだけではなく、賢治には、実際に風に色を見たり光を味わうことのできる「共感覚」という感覚があったのではないかという指摘もあります。
人は普通、色は目で、音は耳で、味は舌で、香りは鼻で、触感は皮膚で感じるもの……とされていますが、時々、比喩ではなく「音を味わう」「言葉の声を聞く」感覚を持つ――もしくは、成長してもその感覚をなくさない――人もいます。
色を「見て、聞く」、音を「聞いて、触れる」。このように、ひとつの刺激で複数の感覚が動く現象は「共感覚」と呼ばれています。こうした感覚を持つ人たちの例も多数報告されていますが、わたしがそれを知ったのは大人になってからでした。

■「音に色を見る」「文字に色を見る」という感覚
この音はこんな色じゃないんだけど、まあ教科書っていうのは仕方がないんだよね。
音楽教室に通っていた5歳のわたしは、テキストを見ては、そんなおませなことを考えていました。当時は自分が「共感覚」という感覚の持ち主だとは知らなかったので、誰もが音に色を「見ている」のだと思っていたのです。
子ども用のテキストには、ドレミの音がカラー表記されていたのですが、その色がわたしに見えている音の色とは違うのです。わたしが音から感じる色と似通った色(本当はレモン色なのにただの黄色になっているものなど)で印刷されている音については「本物とはだいぶ違うんだけど、近い色だから、まあいいことにしてあげる」「本当の色を紙の上に出すのは、とっても大変なことにちがいない」と、子どもながらに違和感の理由をいろいろ考えていました。
まったく違う色で表現されている音(ピンクの音なのに青で印刷されている、など)については、どうしてかなぁと思いつつ、頭からはらいのけていました。聞こえているのと違う色のことを考えているのは、気持ちが悪いものですから。
どうして周りの人たちは、友人も先生も母も、音の色が違ってることを言わないのか、不思議でたまりませんでした。ただ、やっぱり子どもながらも「どうやら他の人は音の色を見ていないらしい」ことを薄々感じていたので、そのことを口にすることはありませんでしたが。
また、基本は黒い活字で書かれている文字も、上手く言えないけれど「色がある」のに、誰も何も言わない。名前だって、本当は正しい色で書きたいのに、できない。でも誰もそんなことを言わない。
「自分はどこかおかしいのかも、音の色も文字の色もみんな気のせいなのかもしれない」
漠然とした不安を抱えていたある日、忘れられない体験をしました。
当時わたしは、ドレミファソラシドの8つの鐘がついた、かわいらしい楽器のおもちゃを持っていました。眺めているぶんには美味しい(!)色の鐘なので、大好きではあったのですが、いざ鳴らしてみると、聞こえる音と鐘の色が全然違う。
複雑な気分で、いつもちょっと遊んでは元に戻してしまうおもちゃでしたが、音の色がおかしいなんてあるわけない、気のせいに違いない、と意を決しておもちゃの鐘を鳴らし続けたところ、強烈な吐き気に襲われたのです。
あぁ、誰が何と言っても、自分の中にこの感じはあるんだ――それを、強烈に悟った瞬間でした。

■色がいろいろ――わたしの場合の「共感覚的」世界
たとえば、わたしにとって数字はこんなふうに見えています。
「2」は光を含んだ群青色
「3」は明るくて軽い蜜柑色
「4」は鮮やかなフューシャピンク
「5」は沈んだビリジアングリーン
「6」はちょっと蛍光色がかった黄緑
「7」は上目遣いのセルリアンブルー
「8」はぼけた茄子紺
「9」はぼやけた茶色
1と0はとても説明しにくいのですが、大体こんな感じです。
「1」は刃物のような色(濃い部分と薄い部分がある硬質な鉛色)
「0」は淡い卵色がかったプラチナリングのような色(光の感じと金属の質感を伴う)
文字にしろ数字にしろ、実際にある色のほかに何かしらの「色」を感じてしまう。成長するにつれ、だんだん「流す」ことを覚えましたが、全体的に文字は何らかの色や光の集合体と捉えています。
楽器の音も、まさに「音色」というか色や光や質感を伴います(多かれ少なかれ皆さんもそうだと思うのですが)。人の声も、はっきり「〇〇色」と言える人はとても少ないのですが、感じます。
いいなあと思う人の声はたいてい茶色で、茶色にこんなに色合いがあったのかと思うほど。
たとえば、歌手の藤井フミヤさんの声は「コーラ味のグミキャンディの色」(透明感のあるきれいな茶色)で、おまけにそれが「星になってはじけたような」味と質感を覚えます(ううん、言葉にするとわけがわからないたとえですね……でも、そうなんです)。
俳優の加藤健一さんの声は、「ベルベットのような質感の深い深い焦茶色」。あの声でなでられると、文字通り身もだえしてしまいます。
また、「美味しい色」「話しかけてくる色」にはこたえられない魅力があって、ついそうした色の小物やハンカチは衝動買いしてしまったりします。
逆に、食べるものには色よりも「形」を感じることのほうが多いような気がします。周囲と溶け合っていない砂糖の形なんかは苦手ですねぇ……。

■「不思議で特殊な感覚」から「そういう感覚もあるよね」に
こうした自分の「感覚」についてお話しするのは、今回が初めてのことです。
(書いてみて、なぜ共感覚が「不思議な世界」とか「特殊な知覚」と言われてしまうのか、よくわかったような気がします……)
誰にも言わずにきたのは、「話してもわかってもらえない」「変だと思われる」「嘘だと言われる」のが嫌だった子ども時代の名残りのため。
でも、誰しもある程度はこうした感覚を持っている、もしくは持っていた(けれど大きくなるにつれて忘れていった)のではないかなと思うのです。
「澄んだ音色」「甘い声」「苦い思い」「やわらかな香り」「真っ赤な嘘」。
――そうした共感覚的な表現はたくさんあるし、誰もが受け入れ、想像できるもの。
もし、こうした感覚があるということが広まっていけば、「特殊」なものじゃなくなるかもしれない。悩んだり、不安になったりする人は減るかもしれない。それが、今日皆さんにお伝えさせていただいた理由のひとつです。
研究によって数千人~数万人にひとりと幅はありますが、共感覚者はある一定の割合で生まれてくるそうです。
もしも、周りで小さなお子さんが「月曜日はなんで赤紫なの?」とか「ここはもっと緑色に演奏したい」と言ったなら、そうなんだね、とただ受け止めてあげてほしい。
その子たちは、目や耳に、ひいては精神に異常があるわけではありません。また、「嘘をついている」わけでも「目立とうとしている」わけでもないのです。当人にとっては、ただ当たり前の事実を口にしているだけ。
誰かが自分と、常識と言われるものと、違うものの見方をしていても、受け止められる。
みんな違って、みんないい。そんな世の中に、近づいていくといいなあと思うのです。