
ノーメイクで土気色の頬をしていても、そこに美は宿る
「美しい」ってなんだろう。造形が整っていること? 自分に合ったメイクがやファッションを身にまとっていること? 立ち振る舞い? 「美的感覚は、時代によって変わる」なんて言われる。「美」ってどこにあるんだろう。

ノーメイクの自分の顔は好きですか、と聞かれたら、「無理、むりむりむり、本当に無理」と食い気味に言うくらい自分の素顔が嫌いだ。
どうしてそんなに、と聞かれても、うまく理由が答えられない。実際に嫌いなパーツもたくさんあるけれど、強いて言うなら「自分の顔だから」嫌いなのだ。
自分のことが好きになれないという強い気持ちが先にあって、それに伴って自分の顔も嫌いだと感じている。乱暴に言うと、自己肯定感の低い人間にありがちな思い込みの一種に囚われているのだ、と思う。
そう自分でわかっていても、ノーメイクの顔を人に見せることには長らく抵抗があった。けれど最近、その考えがほんの少しだけ変化しつつある。
■みんながメイクをし始めるのを待っていた
18歳くらいから、ノーメイクで外に出るのが怖かった。
校則の厳しい中高一貫の女子校育ちだったこともあり、メイクに興味を持ち出したのはたぶん、一般的な高校生女子よりもちょっと遅かったと記憶している。
高1の冬休み、年賀状の仕分けのアルバイト(これが私の生まれて初めてのアルバイトだった)をしていたら、同じ幼稚園出身のミキちゃんという子に偶然会った。
都立高校に通っているというミキちゃんはばっちりめのメイクをしており、すごい可愛いね、と本心で言ったら、「シホちゃんは私立だからメイクとかできないし……うち都立だからたぶんそういうのゆるくて……」とプライドを傷つけないタイプのかばい方をしてくれた。そのとき初めて、「するもんなんだな、メイク」と思ったのだった。
そこから友達にメイクの仕方を聞いたり、美容雑誌を読んだりしてメイクを学ぶ……ということをすればよかったのだが、私にはそれができなかった。自意識が超過剰かつ自分の顔にコンプレックスがあったので、「自分のような人間がメイクをしようとしているということを同級生に知られたくない」という気持ちが先立ってしまったのだ。
だから、大学に進学して“どんな子でも基本はメイクしている”という土壌ができたのは、私には正直ありがたかった。もちろん、面倒で肌に負担もかかるメイクというものを憎んでいる人も周りにけっこういたし、ノーメイクで大学に来ている子もたまにいた(それは当然まったく悪いことではないから)。
けれど私にとっては、「みんなメイクしているから、自分がしても悪目立ちしない」という免罪符が与えられたことは、ぶっちゃけてしまえばすごくありがたかった。
■メイクが“武装”になってからの日々
一度ハードルを乗り越えてみれば、メイクは便利だった。
始めのころこそ自分に合うファンデーションが見つからなくてひどい肌荒れを起こしたり、つけまつげがうまくつけられなくて母親に手伝って糊を塗ってもらったりしていたが、そういった作業に徐々に慣れてくると、メイクは完全に“武装”だった。
自分の顔が嫌いな私でも、メイクが上手くいった日は、「いま自分は人並みの顔をしている」と感じられる。そうでない日でも、なんとか自分が人から虐げられないくらいのビジュアルになれている気はして心強かった。
自分の顔の美醜を異常に気にする人間は、他人のことも同じものさしで見ていそうで怖い、と言われたことがある。
けれどそれはまったくの見当違いで、別に友達がノーメイクでいようがフルメイクでいようが、あるいは街ですれ違う男性がメイクをしていようが、「あ、きょうノーメイクだな」とか「アイシャドウの色似合ってるな」とか思うだけだ。
自分の顔のことばかり気になるのは、私が単に自意識過剰だからなのだ。そんなのずっと前からわかっていたのだけど、でも、なかなか自分の見方だけは、自分ではすぐには変えられなかった。
■プリクラ機の前で言われた「つらくない?」
話は少し戻る。
高校生のころ、同級生にこはるという友達がいた。
こはるは少しだけ釣り目で眉がきりっとしていて、リスのように表情がくるくる変わる可愛らしい子だった。はっきりとした物言いをするので部活の先輩たちからは若干怖がられていたが、実際はとても優しく、中学のころ、虐められていた私に唯一「私はイジメって本当にバカらしいと思ってるんだ」から始まる手紙を書いて送ってくれた子でもあった(私はその手紙をいまでも持っている)。
彼女と池袋にプリクラを撮りに行った日だった。自分の顔が嫌いなのにどうしてプリクラはいいんだよ、と思われるかもしれないが、ゼロ年代のプリクラというのはどちらかというとラクガキがメインのコンテンツで、街中や空を模した背景と自分たちを合成した写真をいかに面白く仕上げるかが勝負、みたいな側面も大いにあったのだ。
私がプリクラ機の列に並びながら「私、自分の顔すごく嫌いだからさあ」と言うと、こはるが言った。「いつもそれ言うけど、自分の顔を自分が好きになってあげなかったらどうするの? ずっとつらくない?」
彼女がそう言ったときの口の動き、興奮してちょっとだけ飛んだ唾、並んでいたプリクラ機の機種、いまでも覚えている。
その言葉を言われた瞬間、「ああ、たぶんこれはずっと私のなかに残るやつだな」と思ったけれど、まさか10年経っても忘れられない言葉になるとはさすがに自分でも思わなかった。
こはるは自分の顔が好きだし、シホの顔も好きだ、と言っていた。
私もこはるの顔が好きだった。でもそれは(たしかにこはるは客観的に見て可愛らしい子だったけれど)、こはるの美醜は一切関係なく、私がこはるのことを好きだから、こはるの顔も好きというだけの話じゃないか、と思った。
■「人は機能的な状態がいちばん可愛い」のか
むかし付き合っていた人は、「人は機能的な状態がいちばん可愛い」とよく言った。機能的、というのは、見た目の美よりも動きやすさや身支度の面倒でなさを重視した、自然な状態という意味だろう。
「それはもともと目鼻立ちが美しい人だけでは……」と元も子もないことを私が言うと、彼は、そうじゃないと強調した。高校教師だった彼は、10代の女の子たちのノーメイクの顔を見慣れていた。
自分が日々学校で働くなかで、メイクをしていない生徒にもたしかに“美”が宿っている、と感じることがあるということ(注釈をつけるまでもないが、それはもちろん恋愛感情や性的な消費とはまったく別の話だ)。なりたい顔や印象を目指して着飾るという行為はもちろんそれ自体が美しく愛らしいが、でも、自分は“自然”の状態によりいっそうの美を感じるということ。
始めはそんな話を聞いても、よくわからなかった。
でも最近、自分が27歳にもなろうというのにノーメイクで家の外に出る勇気がないことを顧みるたび、こはるの言葉や、彼の言葉がふと頭をよぎる。
■美を相手のなかに見出す人たちのこと
これはたぶん、すべての人がそうというわけではないからあまり大声では断言できないのだけれど、「好きな人のことは美しく見える」という人間が、この世には一定数いる。
自分はそうで、こはるもたぶんそうで、彼は間違いなくそうだった。サンプル数3かよ……という感じだが、シェイクスピアも「俺の女の頬はバラみたいではないけどバラよりずっとまし(フォーリンラブ)」みたいな詩をむかし書いていたから、たぶんシェイクスピアもそういう人だったと思う。
それがなんの助けになるかと言うと、(こんなことを言うのは頭がおかしいと思われても仕方ないのだが、)私のことを好きだと思ってくれている人の何割かは、私がノーメイクで土気色の頬をしていても、美しいと思ってくれるのではないか、ということだ。
そしてそういう人たちは、別に恋人や友達じゃなくても「この人なんとなく好きだな」と思う相手に対して、相手が急にノーメイクで来ようが整形してこようが歯に矯正器具をはめてこようが、「肌が綺麗だな」とか「二重幅はっきりしたな」とか「歯が真っ直ぐになったら大人っぽく見えるだろうな」とか、なんらかの好意的なことを思うはずなのだ、たぶん。
なぜなら、そういう人たちにとっての“美”とはもともとどこか1カ所に宿っているものではなく、もっと流動的で、自分から対象物のなかに見出すものだから。
このまえ時間がなくて、かろうじてファンデと口紅だけをつけた顔で地下鉄の階段をダダダダと下りていたら、トレンチコートを着た就活生とすれ違った。
彼女はショートカットで、勢いよくホームに入ってきた南北線の風に煽られて髪がぼさぼさになっていた。メイクはほとんどしていなくて、花粉症なのだろうか、鼻のあたりは少し赤く火照って見えた。
彼女が上りのエスカレーターに一歩足を踏み出したとき、彼女のすらりとした首と短く揃ったまつ毛を見て、ああ綺麗だな、と思った。
楽観的すぎるかもしれないけど、人が人の見た目に対して勝手に美を見出してしまう力みたいなもののことを、私はもうしばらく信じてみることにする。
Illust/兎村彩野(@to2kaku)
Photo/Nanami Miyamoto(@miyamo1073)










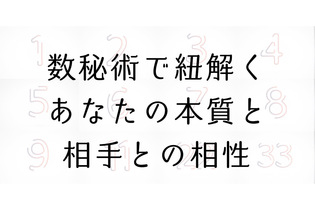










1992年生まれ、ライター。室内が好き。共著に『でも、ふりかえれば甘ったるく』(PAPER PAPER)。