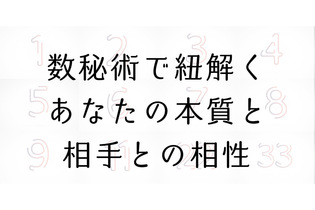好きな男の甘い思い出は、死ぬほど苦い【恋愛難民、王子様を探す】第3話
男日照り暦5年の恋愛初心者・鎌谷素子は、同窓会で再会した長嶋に心を奪われ、デートの約束をとりつける。しかし、長嶋は腐れ縁の腹黒女・高山聡子の元カレ。恋愛難民と化した女は、無事運命の王子様を見つけて失われた青春を取り戻せるのか? 連載「恋愛難民、王子様を探す」#3をお届けします。

■赤いハイヒールでカラダもココロも背伸びして

14時スタートの試合チケットを購入した私を、聡子は盛大になじった。「なんで夜にしないんだ、実力もないのに酒の力を借りなくてどうする、この馬鹿」と。しまったと思ったものの引っ込みがつかず、「いきなり夜集合だなんてはしたない、素面で話してこそ価値がある、この尻軽」と応戦して不毛な口論をした。
しかし、デート前日にクローゼットをひっくり返してうんうん唸っていると、聡子が乱入してきて白いトップスと赤いスカート、そして赤いハイヒールを放り投げてきた。
「赤は女の魅力を引き立てる色だからマスト。でもあんたが真っ赤なワンピース着ても服に着られちゃってみっともないから、スカートと靴だけ赤にしなさい。ハイヒールも足が細く見えるしエスコートしてもらいやすくなるから欠かせない。白いトップスはレフ版効果で顔が明るく見えるわよ」
「なるほど……」
「コーディネート代として冷蔵庫のプリンもらっといたから」
「ねえ、事後報告は単なる窃盗だって何度言ったらわかるわけ?」
「この素晴らしいコーディネートがプリン1個でお願いできるなんて安いもんよ」
聡子は空になったプリンを私の部屋のごみ箱に捨てた。そして私が文句を言おうと口を開くより早く、特大の爆弾を落とす。
「昔付き合ってた男の趣味くらいわかるしね」
「ふーん……って、え!?」
「は?あんた知らなかったの?長嶋と付き合ったことくらいあるわよ」
「いや、いやいや、振られたんでしょ?」
「やっぱり付き合いたいって懇願されたから付き合ってやった」
聡子はぶっきらぼうに答えると、口をぱくぱくする私には目もくれず去っていった。しばらくフリーズした後「うまくいっても聡子のおさがり」と思ったが、長嶋くんには何の罪もない。うら若き少年時代だったから、聡子の性悪に気づかなかったのかもしれないし……いやいや、さすがにあのレベルの性悪に気づかないことはない、赤子でも一目見た瞬間に泣くだろう。一体なぜだ、長嶋くん。
しかし、聡子がなぜここまで私のフォローをするのかも謎だ。しかも元カレ相手の恋愛サポートなんて。本来プリンの1個や2個で動く女じゃない。自分のメリットにならないことは断じてやらない。私に彼氏ができたとして、聡子に何の得があるというのだ。
■ライオンみたいな女の子に恋をした

デート当日、ランチのあとにサッカーの試合観戦をする流れになった。
なんてことない定食屋に入って(聡子がいたら怒るだろう)オーダーしたものの、混み合っていてなかなか料理がこない。長嶋くんは紺色のシャツに黒いチノパン姿で、骨ばった手首やしなやかな首筋を見ると心臓のふちがじんわりと熱くなった。
なにか話さなきゃ、と焦ってひねり出した単語は「聡子」だった。
「聡子と……付き合ってたんだよね、長嶋くん」
「うわー懐かしいわ。そっか、聡子と仲いいんだっけ?」
「仲いいっていうか、腐れ縁っていうか。なんで付き合うことになったの?」
「そうだなあ。聞いたこと、あいつに言わないでおいてくれる?」
なんでこんなこと訊いちゃったんだ、よりによって聡子の話なんて、と後悔しても時すでに遅し。「うん、言わない」と頷いてそろりと相手を伺う。
「実はさ、あいつ、バスケ部のメンバーに嫌がらせされてた時期あったんだよ。当時からさ、尖ってたじゃん。イケメンの先輩とばっか付き合ってたし、気は強いし、遅刻して怒られても素知らぬ顔でツンとしててさ」
聡子が嫌がらせをするならまだしも、嫌がらせをされていたなんて初耳だ。当時もそれなりに交流はあったが、そんな素振りは微塵も見せなかった。
「俺も、美人だけどこえーなーって思ってたわけ。だから一度向こうから告白された時も『俺の手には負えねーよ』と思って断ったしね。でも、その数カ月後かな、あいつが放課後に下駄箱開いたまま立ち尽くしてた時があって」
長嶋くんは烏龍茶についているストローをくるくるとやさしく回転させながら、静かな目でゆらめく氷を見つめた。
「ちょうど他に誰もいなくて、よくよく見てみたら上履きが真っ黒にマジックで塗りつぶされててさ。思わず『うわ、ひでーなー』って言ったら、すごいびっくりしてこっち振り向いて。その後、あいつ何したと思う?」
「走って逃げたとか?」
「いーや、逆だよ。いきなり胸ぐら掴まれて、『だれかに言ったら殺す』って言われた。すごい目つきでさ、本当に殺気感じたよ。でもなあ、これが不思議なんだけど」
長嶋くんは心底懐かしそうに目を細めて、ふわりと笑った。
「見惚れちゃった。ライオンみたいな目してさ、茶色い髪の毛が夕日できらきらしてて、うそみたいに綺麗だった。こいつになら噛みつかれてもいいやって思ったんだよね」
私にはその光景が手に取るように想像できた。聡子の本性は真っ黒だけど、その本性をむき出しにするとまぶしいくらいに光るのだ。綺麗なはずないのに、目を奪われる。なぜかは未だにわからない。
「で、本当にバカみたいなんだけど、『やっぱり俺と付き合ってよ』って言っちゃった。向こうもびっくりしてたけど、俺もびっくりだったよ。1秒前まで心にもなかった言葉がポーンと出てきちゃったんだからさ。聡子は3秒くらい固まってたけど、すぐに手を離して『ばか、死ね!』って言ってどっか行っちゃったよ。『殺す』とか『死ね』とか、物騒だよなぁ」
長嶋くんは喉の奥でくっくっと笑った。聡子の話をしていると、長嶋くんの表情がくるくる変わる。感情の息遣いが聞こえてきて、私は逆に息が詰まる。
「次の日、ホームルームが終わって帰ろうとしたら教室の前で聡子が仁王立ちしてて。すごい剣幕だったから、ビビッて『昨日は悪かったよ』って謝ったら『今日の方が悪い』って言われたんだよね。わけわかんなくてポカンとしてたら、『帰りに迎えに来てくれない彼氏なんて論外なんだけど』って言われた。それから卒業まで付き合ったかな」
「聡子らしいね」
「うん、あいつらしいよ」
あいつ、という言葉の響きがやわらかい。やわらかいのに、なかなかどうして、私の心には鋭く突き刺さるのだった。視線を落とした先で、聡子に渡されたハイヒールの赤がじわりと滲んだ。